ICCサミット FUKUOKA 2025 にスカラシップ制度を利用して参加した外資コンサルティングファーム勤務の碓井 麻理子さんに、運営スタッフ参加の感想と、そこで学んだことについて聞きました。スタッフレポートとしてご紹介します!
Industry Co-Creation (ICC) サミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。毎回500名以上が登壇し、総勢1,200名以上が参加し、参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。
次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜 9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。
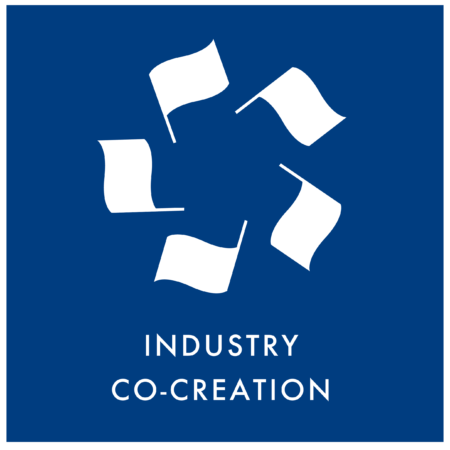
ICCサミットは、宿泊・交通費など自己負担によるボランティアの運営スタッフで運営されています。優秀なメンバーがより多く参加してもらえるように、ICCサミット KYOTO 2018より、ICCサミット参加企業に支援していただく取り組みを始めました。遠方から参加する若手社会人・学生スタッフを対象に、スカラシップ制度として最大60%程度の宿泊・交通費を補助をしています。個人としてスカラシップを提供いただいている方々もいらっしゃいます。
運営スタッフに応募したきっかけや、なぜ応募したいと思ったかを教えてください

きっかけは、シェアハウスメイトのICC運営チーム青山 奈津美さん(以下、なっちゃん)が声をかけてくれたことでした。
いつも熱量高く面白いプロダクトや人を紹介してくれるなっちゃんが勧めるコミュニティに興味があり、説明会に参加しました。

ホームページから熱量の高さは感じていましたが、これだけの規模のイベントをほぼボランティアスタッフで運営していること、想像以上の社会人参加率の高さに驚きました。
ICCスタッフ採用説明会で出会ったスタッフも素敵な方が多く、純粋に「この組織ちょっと気になる」という興味が後押しして、応募を決めました。
どのような気持ちで今回のICCサミットに臨みましたか?

今回が初参加でした。最初は運営スタッフと聞いて、学園祭の延長のような雰囲気を想像していました。
しかし、プレイベントに参加してみたら、「ボランティアスタッフ」ではなく、「場を創る責任者」という意識を持っている人ばかり。
新人に対するオンボーディングチームや、新人ワークショップ、ストレングスファインダーの実施および個別コーチングやグループセッションなど、人員配置やチームビルディングへの本気さが見えました。
熱量の高い人が集まるのは理解していましたが、ここまで運営そのものに本気な組織だとは思っていませんでした。
この組織がどう成り立っているのか?なぜここまで人を惹きつけるのか?
そんな視点で「ちょっと気になる」から「全力で飛び込んでみたい」という気持ちに変わっていきました。
ICCサミットで学んだこと、気づいたこと、深く印象に残っている出来事、エピソードなど、実際に参加した時の感想を教えてください

正直、「ボランティアスタッフをなめていた」というのが率直な感想です。
ICCの凄さは、洗練されたオペレーションや仕組みがあることではなく、「ICCスタンダードの精神を持った人たちがいること」にあると実感しました。
もちろん、クオリティの高いマニュアルや、KPT(継続すること、課題点、次回への改善)の継承は徹底されています。
でもそこに満足するのではなく、「なぜこのトラブルが起きたのか?」「この場の価値を高めるには?」そんな問いを、スタッフ一人ひとりが持ち続けていました。
例えば、私が担当したカタパルトの現物配布。
登壇者のピッチ中に、約40名の審査員へプロダクトを一斉配布する役目です。なんと書籍から豚汁まで対応!
一見シンプルに見えますが、登壇者は7分間のピッチに人生を賭けています。
「この瞬間に登壇者の想いがどれだけ伝わるかで、人生が変わるかもしれない」
その視点から、スタッフは温度管理や配布タイミング、角度一つまでこだわっていました。
カタパルトに限らず、会場運営、チームの動き、新人のオンボーディングに至るまで「どうすればもっと良くなるか?」 を考える文化が根付いていました。
そして、誰もその一生懸命さを笑わない。
普段の仕事では「求められるクオリティをいかに効率よく担保するか?」 を優先していました。
でもICCでは、「どうすればもっと良くできるか?」を皆が追い求めていた。
「一生懸命って、こういうことだったな」
そんなことを思い出させてもらえた、特別な体験でした。

運営スタッフとして参加してよかったことを教えてください。また、どんな人に参加をおすすめしたいですか?

ICCに参加して得たものは、「未来へのポジティブな気持ち」です。
私は学生の頃から「Living well, Dying well」な社会をつくることを目指し、現在は、コンサルタントとして医療業界の経営支援をしています。
支援をしながら、少子高齢化をはじめとする重い課題に直面する中で、もどかしさや諦めを感じることも増えていた気がします。
ICCでは、登壇者も、審査員も、スタッフも、諦めずに皆がそれぞれの分野で未来を切り拓こうとしていました。
私は、登壇者のプレゼンにもらい涙もしました。
「情熱を持って挑戦している人がこんなにもいる。」
「課題は山積みでも、一歩一歩進んでいる。」
この場を通して、未来へのワクワクする気持ちを取り戻せた気がしています。
本気で社会に向き合う人たちの情熱の渦に触れ、改めて素敵な会期だったと感じます。
ICCは、本気で産業を創りたい人たちが、一生懸命に挑戦できる場。
単なるイベント運営ではなく、自分自身も未来を創る一員になれることが、ICCスタッフの魅力だと思います。
だからこそ「自分の仕事やキャリアにモヤモヤしている人」「社会を変える側に回りたい人」にICCのスタッフをおすすめしたい。
この熱量の渦に飛び込めば、きっと何かが変わるはずです!
ICCでの経験を、今後どのように生かしていきたいですか?

一生懸命になることを仕事や人生の軸として大切にしたいです。
ICCではスタッフも登壇者も審査員も、誰もが本気でした。
特に、クロージングパーティでのチームカタパルト(運営チーム対抗のピッチコンテスト)で、SAKE AWARDチームを代表してプレゼンし、3位に終わったなっちゃんが悔し泣きした瞬間は強く心に残っています。
オンボーディングからSAKE AWARDまで、本気で頑張ってきた姿をずっとシェアハウスでも見ていたからこそ涙する姿に胸を打たれました。
正直、ここまでICCに胸を動かされるとは思っておりませんでした。
この何事も一生懸命やることの尊さを、忘れたくないなと思っています。次回9月のICC KYOTO 2025でも熱量の伝播に貢献したいと思います。

また、この経験を自分自身のキャリアにも生かしていきたいです。
単なる業務改善や仕組みづくりだけでなく、熱量をもって人を動かすことが、価値を生む。
ICCで学んだ人や組織の可能性を引き出していく視点を持ちながら、業務に向かいたいと思います。
加えて、たくさんの方々の本気を見てきたからこそ、自分自身は「Living well, Dying well」な社会づくりに向けて何ができるのか?何がしたいのか?もっと思考と行動を重ねていきたいと思います。
スカラシップ提供企業への感謝のメッセージをお願いします

この度は、貴重な機会をご支援いただき、本当にありがとうございました。
ICCは、ただのイベントではなく、本気の挑戦者たちが集まり、未来を創る場だと実感しました。
その一員として関わる機会をいただき、視野が広がる経験ができたことに心から感謝しています。
ICCで得た学びと刺激を、今後のキャリアや人生に活かし、「ともに学び、ともに産業を創る」 精神を体現していきたいと思います!
本当にありがとうございました。
(終)
今回の提供企業は以下の会社です。ご協力いただいたスカラシップ支援企業の
- コミスマ株式会社 (14) 佐藤 光紀 さん
- 株式会社キュービック(14)世一 英仁 さん
- 武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部(10)伊藤 羊一 さん
- 株式会社マネーフォワード(9) 金坂 直哉 さん 竹田 正信 さん
- 株式会社THE GROWTH (6)山代 真啓 さん
(()内は支援回数)
そして、個人サポーターの皆さん、本当にありがとうございました。

編集チーム:小林 雅/北原 透子/浅郷 浩子

