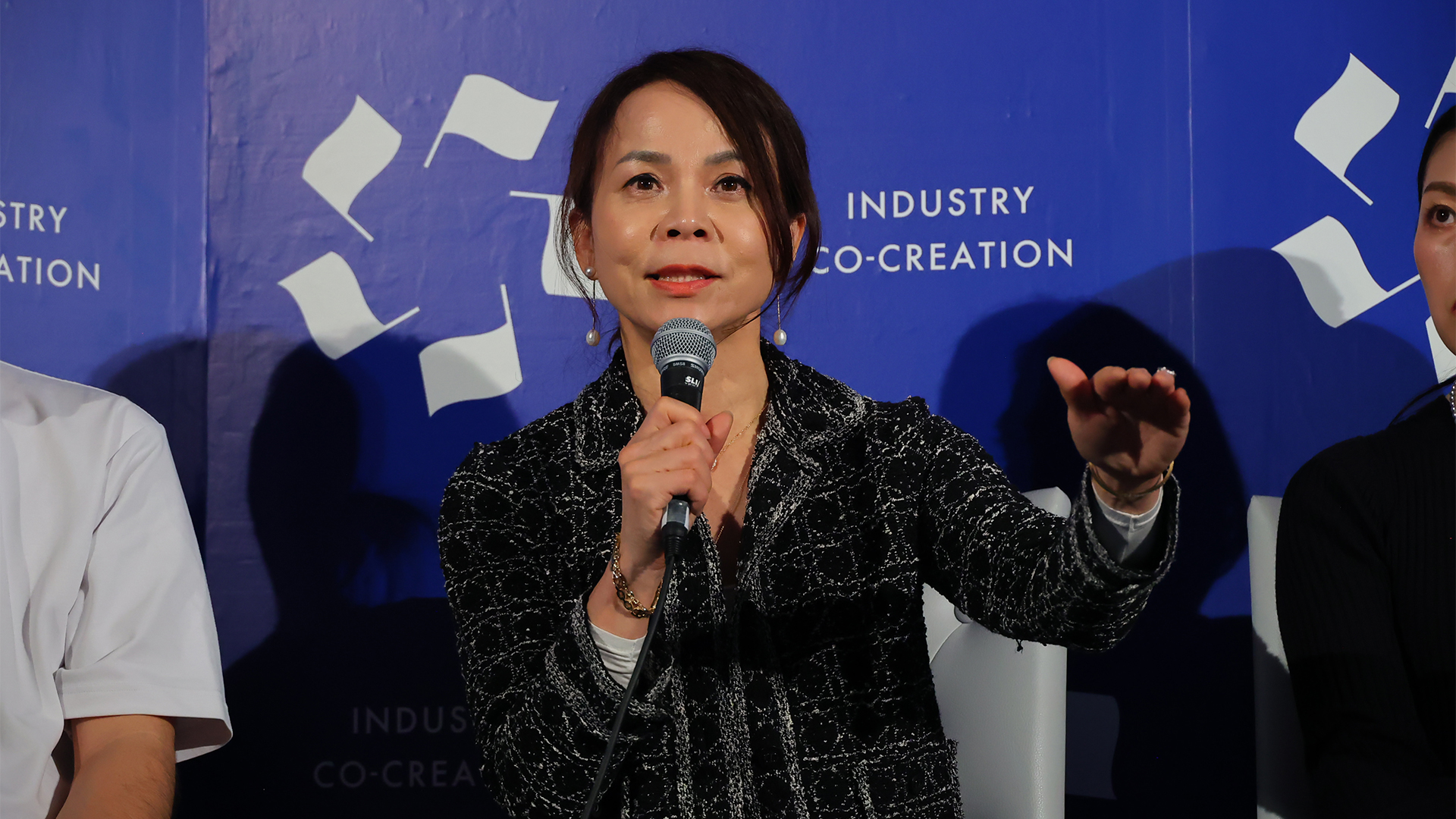▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!
▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!
ICC FUKUOKA 2025のセッション「-Well-beingビジネスの今後(シーズン6) -〜2025 くるぞ、ウェルビーイング〜」、全5回の最終回は、ウェルビーイング・テクノロジーに投資するNIREMIA Collective奥本 直子さんによる、米国内の多様性とメンタルヘルス、Well-being for Planet Earth石川 善樹さんによる、心の問題へのアプローチの話題です。質疑応答も含め、最後までぜひご覧ください!
ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。
本セッションのオフィシャルサポーターは住友生命保険です。
▼
【登壇者情報】
2025年2月17〜20日開催
ICC FUKUOKA 2025
Session 7E
-Well-beingビジネスの今後(シーズン6) -〜2025 くるぞ、ウェルビーイング〜
Sponsored by 住友生命保険
▲
▶「-Well-beingビジネスの今後(シーズン6) -〜2025 くるぞ、ウェルビーイング〜」の配信済み記事一覧
アメリカにおけるWell-beingビジネス
藤本 奥本さん、大統領が代わってから状況が違うかもしれませんが、アメリカは民族を含めて多様性のある国ですよね。
Well-beingビジネスにおいて、インクルーシブデザインなどはどう意識されているのでしょうか?
奥本 アメリカは人種のるつぼと言われていて、すごく多様性が大事にされています。
そうは言っても、企業がいろいろな経済をドライブする国で、例えば大統領選ではどの企業による寄付がどれくらい多いかといった経済的なパワーの大きさがみられる国で、マイノリティの方々に対してとても良い国か言うと、かなり境界線があるように感じます。
最近、アメリカでは人口の2人に1人が何らかの精神疾患を持っており、それがグローバル経済に及ぼす影響は2,400兆円だと言われています。
メンタルヘルスはコロナ禍以降顕在化し、またソーシャルメディアの影響で6~19歳のティーンエイジャーにも影響があると言われています。
また、同じ精神疾患を抱えていても、人種によってその対応はそれぞれです。
米国では、文化や教育的背景の違いがメンタルヘルスへの向き合い方に色濃く表れます。白人系の人々は世代を重ねるなかで、うつ症状を「心の風邪」と捉え、精神科受診への心理的ハードルが比較的低い傾向があります。
一方、インド系やその他のアジア系コミュニティでは、心の不調を周囲に打ち明けたり、治療に費用を投じたりすることへの抵抗感が根強く残っています。
さらに黒人コミュニティでは、「強くなければならない」「弱みを見せてはいけない」という価値観が強いため、精神疾患の治療に対するハードルはインド系・アジア系以上に高いといわれています。
問題が大きくなればなるほど、社会課題を解決しようというソリューションが生まれてきています。
例えば、私の知り合いの日本人起業家が、米国在住のインド系移民の方々へのメンタルヘルス・ソリューションを開発しています。
米国では、女性も社会的マイノリティとして扱われることがあります。
例えば、創薬の現場では、治験参加者の約90%が白人男性で占められているため、小柄なアジア系女性にとっては投薬量が過剰だったり、錠剤が大きすぎて飲み込めないといった問題が生じることがあります。
これは、最近になってようやく声が上がり問題になっています。
こうした事例が示すように、AIによるパーソナライズ化が進むと、今後ますます多様化が進み、それに伴って新たなビジネス機会が創出されると考えています。

体と心の問題はアプローチ方法がかなり違う
石川 今日参加のうちお二人は、体のWell-beingというテーマに取り組んでいると思います。
奥本さんが今お話しされた、心のWell-beingは少しややこしいです。
アメリカにはもともとカウンセリング文化がありますが、これは第二次世界大戦後、戦争に勝ったはずなのに兵士が鬱々として引き上げてきたので、なんとかしなければと、心理カウンセラーの数とサービスが爆発的に増えたからです。
体の問題は体にアプローチすればいいのですが、心の問題は、問題とその原因を特定してもどうにもならないことが多いのが難しい点です。
ようやく2000年代からアプローチが変わり始めます。
心の問題は、一旦その問題を脇に置いて、その人がどういうことに喜びを見出す人なのか、何を楽しみに生きているのかという、その人の良い部分をふくらませることで心の問題だと思われていたことがパーンと消えることがあるのです。
例えば、少年院で「なぜあんな悪いことをした、反省文を書け」という対応すると、なぜ悪いことをしたかについて繰り返し脳に刻むことになり、出所後も再度罪を犯してしまう確率が高くなるのです。
そうではなく、これまでの人生で行った良いことをひたすら書かせると、脳がそういう思考回路になって再犯率が低くなるようです。
つまり、体の問題と心の問題は、アプローチ方法がかなり違うのかもしれないということが今、言われているのです。
ペインと言った時、身体的ペインなら身体的にダイレクトにアプローチ、精神的ペインの場合は患者さんとしてみるよりも生活者として、何がWell-beingなのかをふくらませてあげる方が解決しやすいということです。
奥本 アメリカで最近すごく売れている、“Gratitude Jornal”という日記帳があります。
感謝日記、みたいな意味ですね。
朝起きて日の光が射して深呼吸できたことに感謝、起きてキッチンに行くと美味しそうな目玉焼きを作ってくれているパートナーに感謝、みたいな小さいことを書いていきます。
アメリカでは2人に1人がなんらかの精神疾患を持つので、大学でも研究がかなり進んでいて、例えばイェール大学ではCenter of WellnessやThe Science of Well-Beingという講座があります。
ハーバード大学のアーサー・ブルックス教授がハーバード・ビジネス・スクールで開いているハピネス講座は、最も人気です。
▶︎<知の挑戦>ハーバード大学 リーダーシップ&ハッピネス研究室 幸福度高めるリーダー育成(日本経済新聞)
彼は、幸せは目的ではなく方向であり、昨日よりも今日、幸せなことを小さくても見つけ出せればいいと考えており、心のあり方を語る研究も進んでいます。
それで幸せやWell-beingへの注目度も上がっており、産業が生まれています。
藤本 楽天の(小林)正忠さんがいつもおっしゃる「空を見上げていますか?」を思い出しました。
従業員の心と体の健康のために意識していることは?
藤本 ではここで、会場から質問を受けようと思います。
福島 弦 株式会社SANUの福島と申します。

▼
福島 弦
株式会社 Sanu 代表取締役CEO
2010~2015年McKinsey Company, 2015~2019年日本初プロラグビーチーム「Sunwolves」創業メンバー/ ラグビーワールドカップ組織委員会を得て、2019年にSANUを創業。 2021年11月、セカンドホーム・サブスクリプションサービス「SANU 2nd Home」をローンチ。現在、11拠点64室を運営。 北海道札幌市出身。雪山で育ち、スキーとラグビーを愛する。
▲
Well-beingビジネスを行うグローススタートアップにおいて、従業員の心と体の健康を大事にしないといけないけれど、めちゃくちゃ一生懸命働いて、数値達成が必要です。
そういう組織を運営されている皆さんは、従業員に対して、何か気をつけていること、意識されていることはありますか?
宮脇 我々はフルタイムが4名の小さい会社ですが、大きいことをしなければいけないので、特に開発においてはかなりのハードワークになりがちです。
私自身が気をつけているのは、現場にできるだけ行って、何をしているか、何に困っているかを細かく見ていますね。
まあ、昔から言われている基本的なコミュニケーションですが、私が気をつけているのはそれくらいですかね。
藤本 今の質問は、まさにWell-being経営をされている正忠さんに、何かヒントを頂きたいのですが…。
小林 正忠さん(以下、セイチュウ) 個人のWell-beingと組織のWell-beingがあると思います。

▼
小林 正忠
楽天グループ
Co-Founder and Chief Well-being Officer
1994年慶應義塾大学卒業(SFC1期生)。1997年楽天創業から参画し、6人の日本人組織が100人、1,000人、20,000人、30,000人に拡大し、100ヶ国超の多国籍人財のマネジメント手法の違いを体験。2012年米州本社社長、2014年アジア本社社長を歴任。現在は人々を幸せにする役割を担うチーフウェルビーイングオフィサーとして、コーポレートカルチャー部門を立ち上げDEIやサステナビリティ領域をリード。2001年慶應義塾大学に「正忠奨学金」を創設するなど若者の育成にも力を入れている。2011年世界経済フォーラムYoung Global Leadersにも選出。5児(娘3人息子2人)の父
▲
個人のWell-beingを考えた時、会社で一緒に働く際、各個人が人生において大切にしているものが実現できていれば、個人のWell-beingは実現できているということです。
その人が会社にいる理由、つまりミッションと担当業務がきちんとつながっているかどうかを定期的に確認しなければ、数字や開発など目の前に追われてしまいがちです。
これらが接続されていて、会社のミッションを全員が体現できている状態が作れれば、組織のWell-beingは実現できていると私は解釈しています。
ストレスは高すぎても低すぎても良くない
石川 グロースステージで一番しなければいけないことは、ストレスマネジメントです。
ストレスは高すぎても低すぎても良くないので、適正なストレスにマネジメントしなければいけません。
グロースステージでは睡眠不足にもなりがちです。
そういうハードな環境下でのストレスマネジメントを開発したのは、超ハードワーク環境であるアメリカの海兵隊です。
そこで開発されたストレスマネジメントを実践しているのが、relate社です。
重要なのは、僕らは、人の心についてあまりにも習っていないという点です。
例えば、何がストレスになるか、ストレス特性は人によって違います。
ストレス特性にはどういうタイプがあるか、それぞれのタイプにどうアプローチすべきかについて、単に習っていないだけという状況が多いです。
そういう基本的なことをせずに、理念だけで解決しようとするのは難しいと思います。
基本のストレスマネジメントがある前提で、理念やミッションが結ばれるといいですね。
楽天市場も初期は相当ハードワークでしたが、仲山(進也)さんがお客様からの声を「魂のご馳走」だと表現するストレスマネジメントをされていたようです。
ですので、両輪で考えるべきですね。
藤本 仲山学長にもコメントを頂きたいところですが…。
仲山 進也さん(以下、仲山) 僕が楽天に入社したのは20人くらいの時ですが、採用基準は、体力があるか、もしくは家が近いかでした(笑)。

▼
仲山 進也
仲山考材
代表取締役
創業期(社員約20名)の楽天に入社。2000年に楽天市場出店者の学び合いの場「楽天大学」を設立、人にフォーカスした本質的・普遍的な商売のフレームワークを伝えつつ、出店者コミュニティの醸成を手がける。2004年には「ヴィッセル神戸」の経営に参画。2007年に楽天で唯一のフェロー風正社員(兼業自由・勤怠自由)となり、翌年、仲山考材を設立。2016年に「横浜F・マリノス」とプロ契約、コーチ向け・ジュニアユース向けの育成プログラムを実施。20年にわたって数万社の中小・ベンチャー企業を見続け支援しながら、消耗戦に陥らない経営、共創コミュニティ、自律自走型の組織文化育成、夢中で仕事を遊ぶような働き方を研究している。著書『サッカーとビジネスのプロが明かす育成の本質』『まんがでわかるECビジネス』『組織にいながら、自由に働く。』『あの会社はなぜ「違い」を生み出し続けられるのか』『あのお店はなぜ消耗戦を抜け出せたのか』『今いるメンバーで「大金星」を挙げるチームの法則』ほか。
▲
長い時間働くことが悪いとも思わず、フロー理論で言えば、適度なプレッシャーがかかっている状態だと夢中になりやすいです。
ですので僕は、退屈ではないか、不安ではないか、夢中に取り組めているかを確認するフロー面談をおすすめしていますね。
藤本 ありがとうございます。
本日のまとめ
藤本 最後に一言ずつ、感想、まとめを頂いて終了にしたいと思います。
宮脇 普段、業務をする中でWell-beingをあまり気にしていないのが正直なところです。
WE ATに参加させていただいてからWell-beingについて考えることが増え、今日登壇していろいろなご意見を聞けたので、すごくありがたいと思っています。
松本 宮脇さんと我々の事業領域は違いますが、誰かの困りごとを起点に発想するという点が似ていると思いました。
後半のメンタルヘルスの話では、アプローチがそれぞれ違うということで、Well-beingを考えていく上で多様性、それぞれの人たちにとってのWell-beingという視点が大事なのかなという発見がありました。
奥本 今日のテーマは「くるぞ、Well-being」ですが、コロナ禍により、人々が自身の心と体の健康に注意を向けるようになり、また、Z世代など若い世代が生きるためのバランスを取ることに注力をするようになり、Well-beingのマーケットが急成長しています。
そのような中で、人のWell-beingをサポートするさまざまなソリューションがどんどん開発され、世に出てきています。
私はかつて米国の巨大テック企業で「企業は利益を上げてこそ価値がある」という教えのもと働いていました。しかし、孫泰蔵氏が設立したソーシャルインパクトファンド Mistletoe の米国代表を務めた際、泰蔵氏から「社会課題を解決すれば、必ずそこにビジネス機会が生まれる」という示唆を得て、大きな視点転換を経験しました。
当初は半信半疑でしたが、市場の動向を見渡すうちに、その潮流がすでに現実となっていることを実感しました。その意味でも、Well-being市場は、今後も成長の一途をたどるでしょう。
起業家も企業人も、それぞれのアセットを活かして社会に貢献し、Well-beingな未来を共創できればと願っています。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

石川 これまでのシーズンを振り返ると、最初は議論しかできなかったですが、今では具体的な事例が次々と出てきています。
市場も大きいということですし、「きたぞ、Well-being」という感じがします。
Well-beingは本人がどう感じているかという話なので多様でいいのですが、正忠さんがおっしゃったように、個人のWell-beingと組織のWell-beingは分けて考えなくてはいけないということを、改めて強調したいです。
個人のWell-beingは多様でいいですが、組織のWell-beingは仲山さんが言った通り、フローや適切なストレスマネジメントができていることが重要です。
あと、「未だにWell-beingがよく分からないです」という声が多いです。
それはWell-beingという言葉のせいではありません。
Well-beingは自分が何を良いとするかですから、Well-beingが分からないのではなく、自分が何を良いとするか分からないと言っているのと同じなのです。
僕らは社会に出ると、社会の期待に応えていく方にどうしても軸足が移っていきますので、自分の感情がだんだん分からなくなるのです。
でも、例えば家族や子どもというきっかけで、改めて自分が何をしたいのか、何がWell-beingなのか気づきやすくなるのではないでしょうか。
この会場にいらっしゃった方が外でWell-beingの話をする機会があれば、分からないと言われても、それはWell-beingのせいではなく、あなたが何を良しとするかが不明瞭なだけだと投げかけてもらえればいいと思います。
藤本 ありがとうございます。
次回はWell-being経営についても話したいですし、前回宣言した石川善樹さんのWell-beingの歌を披露する時間もなかったので……。
石川 タイトルだけは決まりました、「うれしい、たのしい、ICC」です(笑)。
藤本 (笑)次回があるかは皆様のアンケート結果次第ですので、ぜひよろしくお願いいたします。
本日はありがとうございました。

(終)
▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!
▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!
編集チーム:小林 雅/小林 弘美/浅郷 浩子/戸田 秀成