▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEで配信しています。友だち申請はこちらから!
▶過去のカタパルトライブ中継のアーカイブも見られます! ICCのYouTubeチャンネルはこちらから!
2月17日〜20日の4日間にわたって開催されたICC FUKUOKA 2025。その開催レポートを連続シリーズでお届けします。このレポートでは、emome森山 穂貴さんが優勝を飾ったスタートアップ・カタパルトの模様をお伝えします。ぜひご覧ください。
ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページのアップデートをお待ちください。
ICCサミットのメイン会場でプログラムが始まる、2月17日の朝は早い。各所で前夜祭が行われた翌日の朝イチのプログラム、スタートアップ・カタパルトに登壇するプレゼンター、審査員、運営スタッフたちは、12時間たたずして、また顔を合わせることになる。

朝7時前、運営スタッフの宿舎から会場のヒルトン福岡シーホークへ向かう道すがら、どんどん空が明るくなっていく。プレゼンターたちは朝7時半に集合の予定で、この景色を見ながら会場に向かっているのかと思う。
朝の7時30分に集まったチャレンジャーたち
メイン会場へ向かって歩いていくと、背後にふと気配を感じた。Tomoshi Bitoの廣瀬 智之さんだ。
いつもはRICE MEDIAの動画で見たまんまの快活なトムさんこと廣瀬さんだが、事前に前夜祭欠席の連絡が入っており、体調は絶不調。原因不明だが、どうやら食あたりらしい。声が弱く、カメラを向けるのも申し訳ないほど目に見えてげっそりとしており、まるで電気が消えたようである。

「でも、頑張ります……」そう言ってしばらく座っていたトムさんだが、時々席を外している。
すでに会場に一番乗りで到着していた、オプティアム・バイオテクノロジーズ西岡 駿さんに話を聞く。
「昨晩はチャレンジャーズナイトの後、プレゼンのスライドを見直してから寝ました。
▶︎ICC FUKUOKA 2025開幕を告げる2つのパーティ「 ICCデジタル名刺交換ナイト powered by Eight」と「チャレンジャーズ・ナイト」
CAR-T細胞は、がんの治療をされている方や、情報収集をしているならご存じの方もいて、希望をかけている分野かもしれません。会場は健康な方たちが多いと思うので、誰もがわかるように、極力専門用語を使わずに伝えたいと思っています」
西岡さんは、元は証券会社で金融マンとしてヘルスケアセクターに関わっていて、がんの治療を劇的に変えるアプローチとしてCAR-T細胞の活用を知った。固形がんにも適用できる可能性を見据え、技術を世に届けたい一心で会社を起こした。
「ものすごく難しいことをしているわけではなく、発想の転換で、治療のブレイクスルーを果たすのがうちの技術。シンプルで細かい要素技術をたくさん組み合わせてできるもので、技術としては複雑なものではない。でも、業界にいればいるほど意外と見えないアプローチだったかもしれません。
共同創業者の先生がそこに着眼し、僕も技術的にすごく腹落ちする考え方でした。世界的に見ても、こういうアプローチでCAR-Tを創っているところはないので、それを伝えたい」

今回西岡さんはリアルテック・カタパルトにも登壇したが、日本人の死因1位を占めて長いがんの治療には本当にさまざまな人々が挑戦していて、カタパルトでは毎回、治療の進化を知ることができる。医療者や研究者に限らず、西岡さんのような専門家でない人たちも加わって、不治の病と戦っている。
次世代の経営者たち、現る

Quwak合田 瞳さんは、共通の知り合いがいるという前回スタートアップ・カタパルト優勝者のレコテック大村拓輝さんと話している。合田さんの右手に、マイクロチップが埋められていることを知っているか?と聞くと、早速携帯電話をかざしてみて、右手の一箇所の皮膚が緑に光ったことに驚いている。
「すごっ! これ何が開かれるの?」
「Facebookです。自分の免許証とか、アイデンティティを証明するものを我々のプラットフォームに登録すると、チップをインターフェイスとして認証ができるというのを作っていて」
プレゼン中にデモをしないことを残念がりつつ、でもきっとみんな驚くよ!と言う大村さん。共通の知り合いはICCサミットには全く関係のない方らしく、偶然の出会いに喜びあっている。
スタートアップの経営者と聞くと、とんがって強いイメージがあるかもしれないが、新しい概念を世に伝えることに日々向き合い、地道に努力を重ねている人たちである。スタートアップ・カタパルトは特にICCには知り合いがいない初参加の方が多く、緊張感も桁違いだ。こんなふうに少しでも緊張を和らげ、応援されると大きく勇気づけられることだろう。

話を聞きたくて様子をうかがっていたのだが、ピックユーの冨田 理央さんは、リハーサルが終わると待機する席から姿を消してしまった。今回の登壇者のなかでも最も若い世代に訴えかけるであろう、インフルエンサーのファッションリセールプラットフォームを運営、平均年齢23歳のチームを率いる。
冨田さんをはじめとする、今回のチャレンジャーたちの着眼点や事業は、審査員たちにある意味衝撃を与えた。世代が入れ替わりはじめているという実感、将来性は理解できる事業だが、自分たちでは発想しえない事業を作る、そんな起業家たちがたくさん登壇したからである。
ピックユーのインタビューコンテンツ「今日は何着てますか?」をはじめとするSNSで配信した動画コンテンツの総再生回数は1.5億回を突破、すでにファッション業界の新たなスタンダードとなっており、ブランド価値の構築や、ロジ周りの投資にも抜かりがない。グローバルのトラクションも加速中だという。

もちろんトライ&エラーを続けて事業を作っているけれども、レバレッジを効かせる新しい勘所を知っている、若い世代が新しい事業を作っている、今回のカタパルトの登壇者たちにそんな印象を得たのは、プレゼンがすべて終わったあとの審査員、UntroD永田 暁彦さんらのコメントでも明らかだ。
強い原体験を持つ起業家たち
とはいえ強い原体験を持って起業していることには変わりない。たとえばrecri栗林 嶺さんのケース。

栗林さんは、興行のチケットのサブスク事業を営んでいる。素晴らしいクリエイターたちによる舞台や演劇などの興行は日々開催されているが、そのすべてが満席になり売り切れるわけではない。それを新たなエンターテインメントとの出会いを待つ観客とマッチングさせる事業だ。
「前職がクリエイターだったので、自分でも作ったり出たりしていて、業界の課題というか、旧態依然とした古い体質に気づいたんです。
友人も多く、みんなが経済性より感情のほうが優先されるような業界の側面に課題を感じていました。どうにかそれを解決したいと考えるなかで思いついたのが始まり。プロデューサーや役者さんたちがサービスを構想する段階から一緒に入って、意見や現状を聞きながら作っています」
いわばプロダクト側の目線から作ったサービスで、サブスクする顧客側の反応が気になる。
「まさにこういうのを求めていたという声が多いです。嗜好性の高いお酒やファッションなどで、初心者向けのサービスは多いのですが、エンタメやアートの領域には全くない。どこから初めていいかわからないというなかで、ようやく現れた、求めていたと熱狂していただいています」
たしかに、ファッションなどよりエンタメはよほど間口が広そうだ。現在カバーしている分野は、ステージでやっている演劇、ミュージカルから伝統芸能、クラシックバレエまで幅広い。サービスを立ち上げて間もないが、ニッチな音楽ジャンルや、席を埋めるニーズのあるスポーツ業界からもニーズがあるという。
「AIやオンラインが進化していくなかで、最後に変わらないところ、人間の創造性やウェットなところ、生の体験の素晴らしさを伝えたいと思っているし、エンタメや文化芸術のポテンシャルは、日本が最後に勝てる領域じゃないかと思う。世界的にも日本のコンテンツやIPは評価されているので、それを見捨てずに、注目してほしいと思っています」
たしかに、オンラインで国境を越えたIP展開は盛んでもリアルの領域はまだまだ限定的である。今後オンライン化が進めば進むほど、リアルにも可能性が広がっていくだろう。
「ICCも、生の人の出会いや化学反応を重視されていて、通じるところがあると思っています。過去にICCに登壇した先輩の知り合いや審査員が何名かいて、素晴らしいから出てみたらと、どんな仕事よりもICCを優先したほうがいい、絶対いい学びや出会いがあるからとおすすめいただいたんです」と言う。
その栗林さんと話していたのは、すらりとした長身で一際目を引くMONAの山本 安奈さん。今回初参加の運営スタッフの碓氷 真理子さんと「高校生のときから友達で、一番最初のアルバイトも一緒で」と言い、偶然の再会だという。

山本さんは、過去にカタパルトに登壇したガラパゴス中平 健太さんからの紹介だ。
「事業をするというのは毎日、日々何かを淡々とやり続けることですが、このカタパルトは1回だけ、7分間にすべてをかけること。その一瞬にかける頑張りというのがめちゃくちゃ久しぶりだなと。大人になって、そういう機会はなかなかないじゃないですか。10代の頃の気持ちを思い出しました」
山本さんは現在の姿から想像もできないが、幼少期からずっと重いアトピー性皮膚炎に悩まされてきたという。その症状が抑えられることによって、さまざまなことに向き合える時間を得た実感から作った、人に言えない悩みを相談しやすいオンライン診療クリニックの事業を伝える。
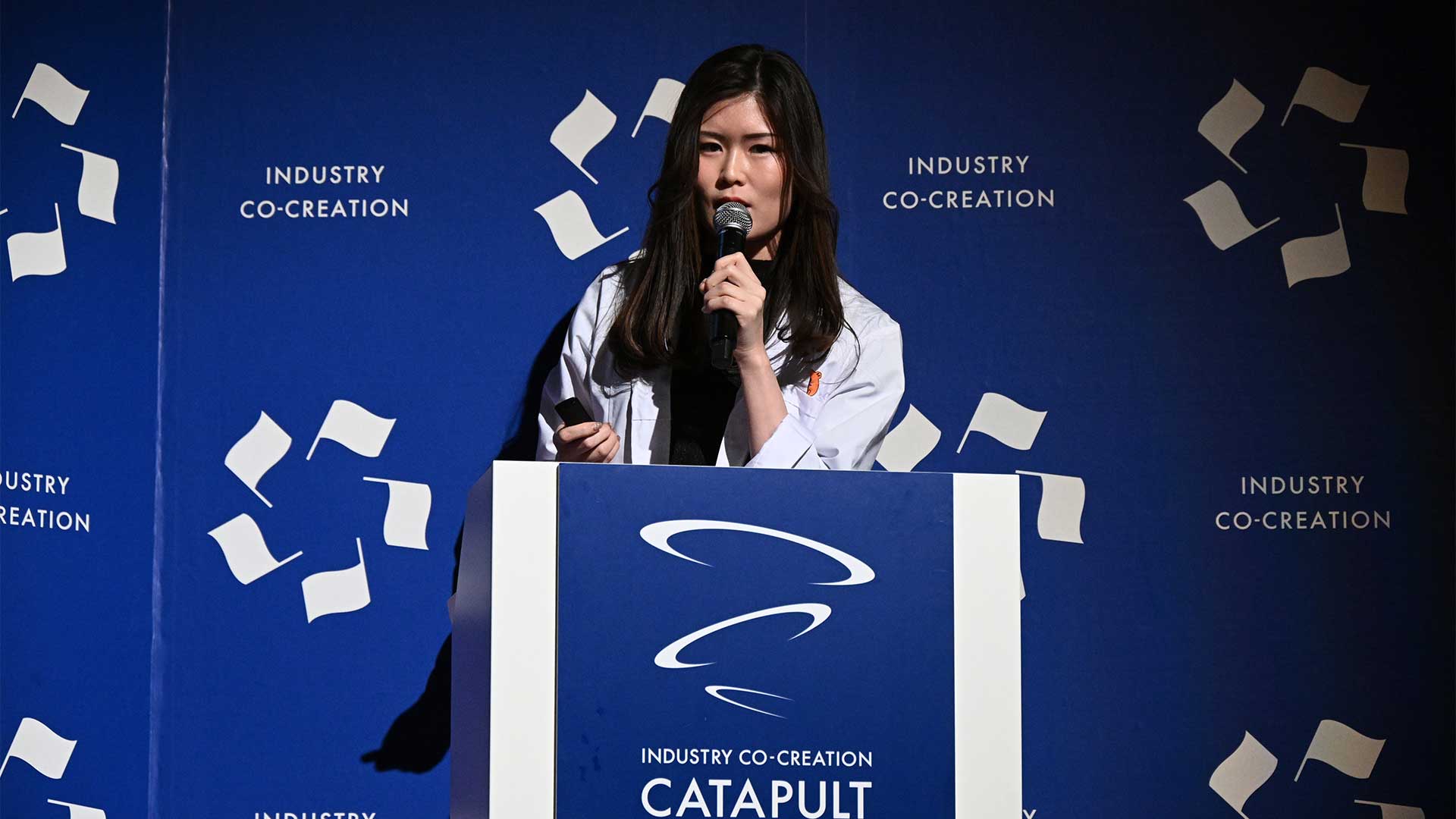
「今も完全に治ったわけではなくて、1カ月に1回注射をしないとまた戻ってしまう。外見が全てではないけれど、それによって自分の心も、相手の反応も影響されることがあるので、自分に自信が持てるというのは生きていくうえで、仕事していくうえで大事だなと思う。
もし悩んでいる方がいたら、もっとベターな生活ができる手段があるかもしれないし、解消するかもしれない。悩みは、ずっとそこに向き合わないといけないわけではないんです。解決する手段があれば、本当にやりたいことにもっと力を入れられます」

こぼれそうな笑顔を向けてくれるiiba 逢澤 奈菜さんは、その実「緊張してます。この会場の皆さんの雰囲気にのまれてます。これだけ準備してもらって、失敗しちゃいけないっていうプレッシャーを感じてます」と言う。
街なかの子連れに優しい場所を口コミ情報で集めて、プラットフォームアプリで提供する。今も子育て中で、リアルな課題をそのままプロダクトにしたプレゼンはわかりやすく、3位に入賞した。しかし子育て中の起業というのが凄い。
「それをよく言われるんですけど、子育て中だから起業大変とか、何も考えていなくて、ないから作るしかない、当事者がやるしかなくて、不便なので作ろうかなって」
たった5人のメンバーで泥臭くtoCヒアリングを続け、インフルエンサーを強化するために1時間刻みで説明会を毎夜5本行ったりしていたそうである。何百人に話を聞いたかなぁ?と首をかしげる。
「子育てしていないからとか、もう子育ては終わったからではなくて全員に関わる話だととらえています。自分もできることがあるのではと当事者意識をもって、皆さんに1つひとつのパーツになってもらいたいなと、自分ごととして聞いてもらえたらなと思います」
課題の当事者がサービスを作っているのだから説得力がある。いずれも昔からある課題の解決であり、サブスクやオンライン、アプリといった作り手・受け手の双方の環境が整い、「こうあるべき」に縛られない起業家たちが事業化する。常識を覆すその勇気と実行力を、スタートアップ・カタパルトは祝福する場でもある。
「助けられた恩を返して、苦境の業界を変える存在になる」

「正直昨日までは不安だったんですけど、今日はものすごいワクワクしています」
と言うのは、emomeの森山 穂貴さん。2年前の福岡では運営スタッフをしていた。当時は学生団体や企業インターンの経験も豊富な現役の大学生で、スタッフを続けないのは、起業して忙しいのだろうというのと、どこか一匹狼的なところがあった。
「そのあと2年間、かなり苦しいこともたくさんあったんですが、助けてくれた人がいたから今日がある。また同じ会場に来れたことに喜びを覚えています。会場の皆さんに対して伝えるとなると緊張しますが、助けてもらった人に感謝の気持ちを伝えることならそんなに緊張はしないので、全力でやっていきたい。
介護業界はなかなか苦境ですが、そんな中でも私たちは高齢者の皆さんに生活の豊かさを提供する事業を持続的にできる。今まで業界には、なかなか救世主的な存在や、本当に変えられる人は現れなかったんですが、介護業界ができて25年目の節目に、変えられる人がいよいよ出てきたということを感じていただけたら」

自分で事業を立ち上げもしたが、家業に近しいところへ戻った。自分がいつか継ぐとは思っていたのだろうか?
「(即答で)思っていなかったです。でも自分の事業がなかなかうまくいかない時に家業に戻らざるを得なくなって、その時に自分が肩肘張って横の人と背比べしていることや、本当に誰を笑顔にしなきゃいけないのかを我に返って感じた。それが非常に大きかったと思っています。
私も助けていただいたと感じているので、その恩を返したいって思いが一番大きいかな」
事前にオフィスで開催したカタパルト必勝ワークショップ&公開リハーサルで、森山さんはグループ内で1位だった。そのときに実施して大いに盛り上がった、施設で入居者たちが楽しんでいるレクリエーション映像を会場でも実演する予定だ。
「思いの外、楽しみっていうか。うん。なんかちょっと伝えたい。しみじみと」
無断キャンセルに対する飲食店のソリューション

AccordX安井 一男さんは、事業にかけるなみなみならぬ想いがある。当然ながら優勝を狙っている。
「今回このような機会をいただいて、改めて自分の事業を深く考えるきっかけになりました。まだサービスが出て6、7カ月ぐらいなので、まずは皆さんに知っていただきたい。ニッチな課題に取り組んでいますが、それを解決することが、社会を良くすることにつながるところまで伝えたいです」
ニュースでも騒がれた、飲食店の予約を無断キャンセルする問題。店側としては当日の営業だけでなく、仕入れや人員確保にも関わる問題で、損失の回収は難しく、泣き寝入りせざるを得ないことも話題になった。AccordXは店に代わってキャンセル料を回収するサービスで、督促電話と比べて20倍の回収率を誇る。
「昨年のケミカンの清水さんと結構近しいのですが、僕たちも実は2019年から色々外食事業でピボットをしてきていて、なかなかうまくいかなかったんです。
事業をたたんだ後に、投資家のご理解のもと3カ月くらい自分を見直す期間をいただいて、ずっと外食事業のドメインだったので、改めて毎日飲食店でスポットバイトを3カ月ぐらいしていました。
今の事業のきっかけは、実際に現場で働いて、こういった痛みを感じている方をたくさん見てきたので、それを解決したいという思いが原点にあります。
全国2000店舗超(2025年2月現在)で使ってもらっていますが、最初は4店舗でした。こういったものが今までなかったので僕ら自身もなかなか分からないままやったのですが、実際に回収できて、かつ喜んでいただいて、非常に感動していただけることが多いですね。
実際使ってくださる方がアンバサダーみたいになって、ご自身の知り合いを紹介していただける。35%ぐらいはリファラルで入ってくださっています。
業界全体を魅力的に、より持続可能なものにしたいという思いが強いので、課題を伝えて、正当な努力が報われる仕組みを作る、社会的な挑戦を応援していただけると嬉しいです」
貴重な学生たちに、投資が回ってこないのはすごく変なこと

Alumnote中沢 冬芽さんが事業を始めたきっかけは、「なぜ海外の大学はカッコいいのか」というから面白い。
「海外では、ハーバードやスタンフォードなど大学本体が企業のように通常の業務として、寄付を集めること、収益化を当たり前にやっている。日本は内製でそれをやるチームがいないので、我々は外の業者ですが、それをやろうとしてます。
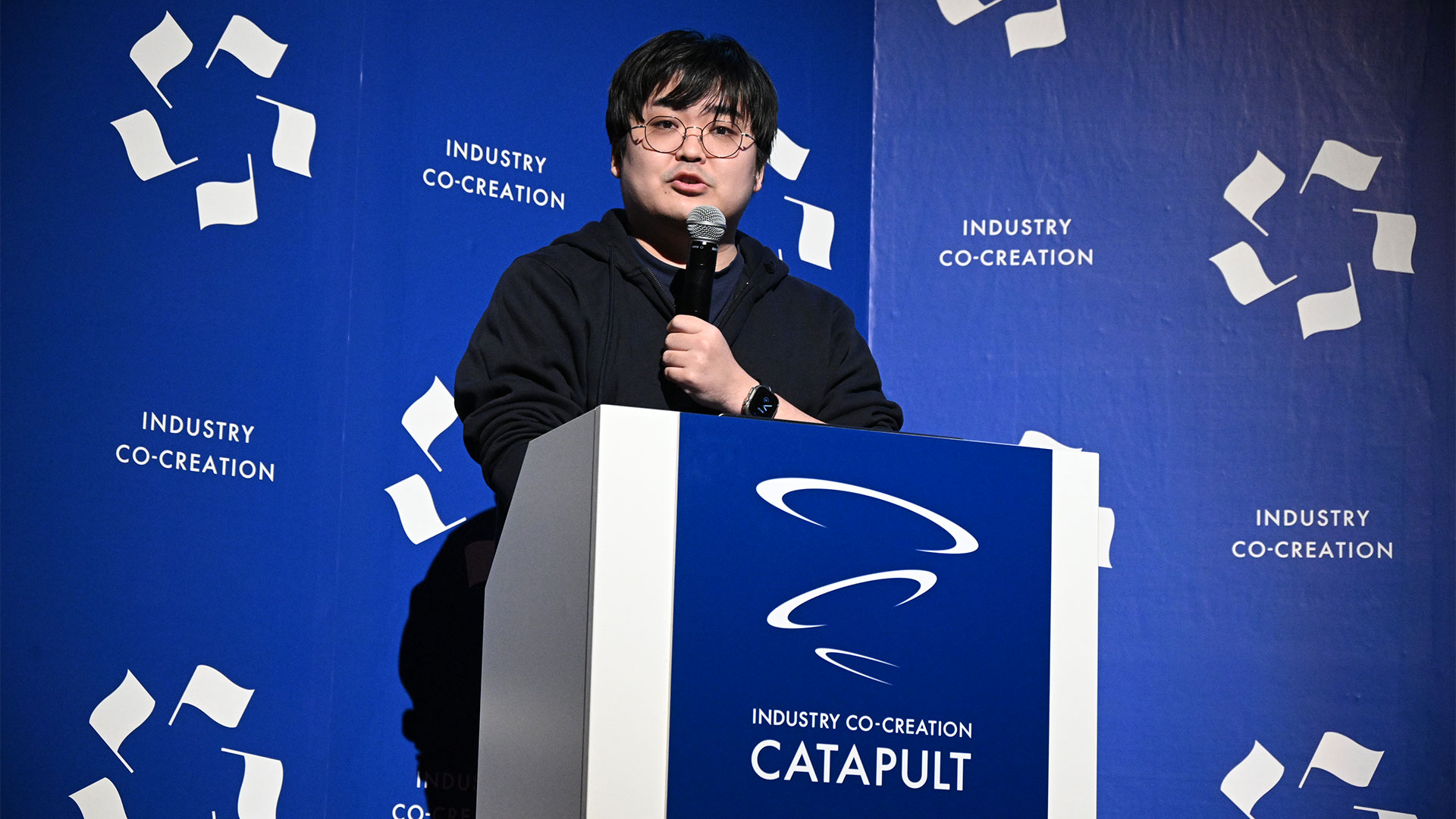
日本は良くも悪くも国立大学は補助金が出ており、その心配がなかったんです。アメリカのプライベートスクールはむしろちょっとビジネス的に考えているので、元から卒業生や寄付者がクライアントに見えていたんですが、日本は文部科学省を見ていればよかった。
それでも風向きが変わってきて、いざ海外大学のようにしようという指導が日本でも直近20年くらい来ているんですが、それを自分たちでやるのはリソース的にも厳しいんです」
なぜ大学関係者でもない中沢さんが、それをやろうとしたのかというと……。
「大学を何なら中退しちゃったんですが(笑)。 小さい頃アメリカに住んでいてアメリカの大学に行きたいと思っていたけれど、家庭の事情で行けなかった。海外大学はなぜあんなかっこよくて、日本の大学はこんなにモチベーションがわかないんだろうと調べてみたところ、大学経営の構造や日本の大学の課題を知ったんです。そこからアイデアを掘り起こして」
寄付の文化がなかなか根付かない日本、大学が心配すべきなのは生徒減だけかと思っていたが、経営の課題にも直面していたのである。
「寄付を集めないと、今までもらえていた補助金がもらえないというようなインセンティブや競争の仕組みが施行されたのはここ数年ですから、大学が実際に意識し始めたのはここ数年でしょう」
そうなったときに、今のところ頼れるのは他に競合のないAlumnoteしかない。
「そもそもお金がないところが出発点になっている事業ですし、基本的には成功報酬。逆に言うと経済面を解決しようとするお客さんを相手にしているので大学からはお金をそこまでもらえなくて、最初の数年に事例を作るまでは難しかったですね。
でも今後は間違いなく大学、寄付で言うと、当然若者や支えられたい側の数が減り、支える側が増えるので、寄付自体の行動は増えていくと思う。
大学の強みは若者がたくさんいるところです。自治体からしてみれば大学が無くなったら街が壊れてしまうし、企業も同じく労働不足に陥るので、そのアセットを持っている大学がマネタイズすることは全然できるんじゃないかと思っています」
そんな中沢さんが描く日本の大学の理想像とは?
「まずはサステナブルなビジネスモデルになって初めて、前向きな投資が色々できる。僕が目指すところは、若者にたくさんお金や投資が行われている状態です。例えば海外では修士や博士を取るために給料が出て学びに行きますが、日本はむしろ、給料が出ないどころか学費を自腹で払わなきゃいけない。
そもそも今後少子化で、こんなに貴重な人たちにお金が回ってないこと自体がすごく変です。教育は時間軸は長いですけど、投資すると絶対に回収できる。今投資が回ってないのは、もうそういうことを考えられないぐらい余裕がないっていうことです」
話を聞いていると年長者からの教えに耳を傾けている気分になったが、中沢さんはやる気十分、大学経営に新たな収益源を作り、ひいては日本の大学をカッコよくする気満々の若者である。
優勝「emome」の社名の意味

今回から加わった、全セッション会場の冒頭の「激励の拍手」と議論が終わったあとの「共創の拍手」は、おそらくカタパルトのチャレンジャーへの激励の拍手に由来する。この恒例の”セレモニー”は、応援の力を伝えるだけでなく、課題や議論に耳を傾け、どんな未来をこれから作っていくのかをともに考える、方向性を揃えるような効果がある。
カタパルトの中継映像では、プレゼンはもちろんのこと、そんな会場の一体感が伝わる様子もぜひご覧いただきたい。拍手はプレゼン開始の直前と、結果発表が終わった最後に行われる。
カタパルトの結果は既報のとおり、森山さんの優勝に決まった。審査員席も会場も総立ちで参加した色読みゲームのエンタメ性だけでない、事業を作り、事業に支えられ、そして産業を創ると宣言した森山さんの強い意思が伝わった。森山さんは、優勝スピーチで社名の由来をこう語った。

「emome(エモミー)という社名には、良い感情を循環させたいという想いを込めています。右から読んでも左から読んでも同じで、誰かのemotion がme、私を動かして、また次の人を感化して動かしてそれが循環していく。
運営スタッフとして参加していた2年前のこの会場で、大学の先輩でもあるユーグレナの出雲 充さんのエフィカシー(自己効力感)という言葉を生で聴いて、これが自分の存在意義だと思いました。
それから2年、必死にもがいて頑張ってきたけれど、うつ病になったり起業は甘くないと思う日々の連続でした。でも支えてくださる方々のおかげで、この場に立つことができました。
少しでも次の世代が見て、2年後にこの場に登壇してくれたらいいなと思います。私もこれから3日間たくさん学んで、次のみなさんに伝えられる立場になれるよう頑張っていきたいと思います」

運営スタッフ出身のカタパルト優勝者は、ログラスの布川 友也さん、サグリ坪井 俊輔さんに続いて、3人目。起業に限らないが、運営スタッフは優秀な人材の宝庫なのである。
ICC小林 雅はスタッフコミュニティを活性化すべく、運営スタッフのクロージングパーティで開催されるチーム・カタパルトに、登壇者たちを審査員としてたくさん招待した。
ここからはそのときに聞いた、森山さんのカタパルト後日談をお伝えしよう。
優勝後の3週間は記憶がないくらい忙しかった
「優勝してから、今日でちょうど3週間でしたっけ? 審査員の方たちから、点差が大きかったというのをすごく言及されるんです。高い期待をある種いただけているけれども、そこに応えなければいけないプレッシャーがすごく大きいと感じています」
3週間、ほとんど記憶がないくらい忙しかったというが、自分は優勝できると思っていたかどうかを振り返ってもらった。
「自信は……、できるかできないかで言うと、できると思っていましたし、狙っていましたけど、確率で言うと30%ぐらいかなって感じではありました。
自分のプレゼンを終えてFacebookを見てみたら、僕が苦しかった時に、全然違う業界だけどこの業界もちょっとかじってみたら?と誘ってくれた人が、ものすごく長いメッセージをくれていたんです。
それを見た時に、もう賞はどうでもよくて、プレゼンを通して感謝の気持ちを伝えられたのが一番良かったな、と思ったことを覚えています」
そうはいっても、優勝の威力をその後から知ったという。
「お問い合わせが増えました。投資家の皆さんからのお問合せが一番多かったです。次に、ビジネス的にはこれから日本で一番大きい市場になっていくので、高齢者に向けた商品を作りたいという会社さんのお問い合わせが多かった。
スタートアップの打ち合わせって、基本的に営業か投資家しかないじゃないですか。だけど営業でも投資家でもなくて、何でもいいからあなたの会社に貢献したい、という企業さんが3社あったのに驚きました。もちろんその企業さんなりに思いや考えをお持ちだとは思いますが、そういうアプローチは今まで全くなかったんです。
そのときに、自分たちがこういう会社をやっているのにもかかわらず、emomeと何もやっていないのはおかしい、という話をされたんです。それぐらい社会を変える、同じ方向を目指している方々がICCに集まっているというのを改めて感じました。
今は良くも悪くも考える時間がなかなか取れないという感じ。本当にすごくて、人生で一番忙しいかもしれない。実は今日のために一瞬東京に戻って来たんですけど、直近で大阪の介護施設のM&Aをしたので、ずっと大阪にいたんです。
問い合わせてくださった方に大阪にいると伝えると、ぜひ見にいきたいということで、もうすでに介護施設を実際見に来ていただいた方もいらっしゃいます」
磨き抜いた優勝プレゼンの秘密については、内容に加えて得点の獲得についても注意を払っていた。
「ICCが終わったあとに、どの方が何点入れてくださったのかを共有いただけて、僕らの投資家の1人が審査員にいて、その方は僕に投票できなくて、1名ご欠席されていたのですが、全審査員34人中の30人に投票いただいたんです。
2点が決して多かったわけではなくて、皆さんから1点頂けたのが大きかったと思うので(※)、最初から狙ってはいたんですけど、こいつはよくわからないけどデカくなりそうというオーラを見出していただくことを、すごく意識していました。それはうまくいったかなと思います。
▶︎編集注:カタパルトの審査員は、最も応援したい1組を選んで2点、2組に各1点を投票する
1点を必ず入れていただくようにすごく意識していました。絶対記憶には残していただけると思っていたので、そこを一番頑張ったとは思っています。

内容を変えてはいないのですが、1週間ぐらい前に全部ばらして、再設計をしました。自分の言葉で伝えられていない部分がたくさんあり、本心ではない部分がまだいっぱいあった。もう1回、今、自分がどんな気持ちを持っているのか、どういう事業をやりたいのかを改めて考えて、作り直したのがすごくよかったかなと思ってます。
その結果、皆さんがプレゼン内容を見ていただいて、この会社はどういう事業をやりたくて、私自身がどういう社会を描いているのかをくみ取った上で、こういうことを一緒にやりたいとお話を持ってきていただけたのはすごく良かった。プレゼンを磨いた甲斐がめちゃくちゃありました。
その後、採用のスカウトメールを送って見に来ていただくこともすごく増えたんですが、僕が思い描いている社会像と、プレゼンを見た方の僕らの会社へのイメージが、ほとんどずれていない。このICCの空間が生み出した、カタパルトに向けて磨いていただいたおかげだと思っています。改めてすごいなと思いました」
「自分の人生により夢中になれている」
そんな状況を喜びつつ、それに浮かれすぎないように、むしろこれからが大事と気を引き締めている。
「でも、”ICC芸人”みたいになってはいけないなとも思っています。これが起業家として最高の成績というのは違う。あくまでオポチュニティだと思っているので、これをしっかり活かして次のステップでずっしりと実績で地に足着けるのが、すごく大事だと思っています」
忙しくなった、その合間をぬってスタッフ向けのイベントに参加いただいたが、ICCの場に戻ってくるのが「嬉しいけれど怖かった」と言う。優勝を通過点にしてそれより上を目指している日々、振り返って足元を踏み外したくないのだろう。

「だから、ものすごく良い緊張感をもって毎日生活できていると思っています。優勝してもちろん嬉しいんですけど、浮かれるのは正直、あの1日目で終わった感じがしていて、今度はしんどいっていうか……すごく責任を感じています。
社会的にこういうことを求められている会社になったというのであれば、そこに追いつかせるだけですから、わかりやすい状態だと思いますし、ここでふんばれるかどうかが、実はカタパルトで優勝すること以上に経営者としての腕の見せ所なのかなと思っています。
終わった後がさらに充実していますし、自分の人生により夢中になれているのかなという気がしています。まだ何も終わってない。また明日から一生懸命頑張りたいなと思います」
落ち着いた風貌だがまだ22歳、時間はたくさんある。優勝でこの産業への注目が高まり、参入が増えるのでは?と言うと、慌てて「だめです!」と制止した。もちろん冗談だが、それは自分がこの産業を変える、そのための具体的な計画を持つ当事者だという強い自信の表れでもある。
「まだ一番を取りたい」そう森山さんは言葉に力を込めた。実績が伴わなければ意味がないことも知っている。絶対に成果を出さなければという決意が、言葉の端々に見えた。
社名のように、良い感情が次の人に伝播して巡りゆく社会の実現、老若男女、エフィカシーにあふれる豊かな未来を目指して。今まで彼を支えてきた人たちに加えて、emomeの描くビジョンを知り、応援する人が格段に増えた今、カタパルトを通過点に、彼はより夢中になって事業に取り組み、次にICCで会う時にはその進捗を伝えてくれるに違いない。
(終)
▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEで配信しています。友だち申請はこちらから!
▶過去のカタパルトライブ中継のアーカイブも見られます! ICCのYouTubeチャンネルはこちらから!
編集チーム:小林 雅/浅郷 浩子/小林 弘美/戸田 秀成


