2月17日〜20日の4日間にわたって開催されたICC FUKUOKA 2025。その開催レポートを連続シリーズでお届けします。このレポートでは、LEDGE 亀石 倫子さんが優勝を飾ったDAY3、ソーシャルグッド・カタパルトの模様をお伝えします。ぜひご覧ください。
ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。
「あなたが見たいと願う変化に、あなた自身がなりなさい」
これは前回、このカタパルトで優勝を飾ったLivEQuality大家さんの岡本 拓也さんが、優勝後に事業が加速度的に進んだことを報告したスピーチの締めで紹介した、ガンジーの言葉である。
▶︎「大家×NPO×ファイナンス」で、シングルマザーの課題を住まいから解決する「LivEQuality大家さん」(ICC KYOTO 2024)
日本版アフォーダブルハウジング市場を切り開くと宣言した岡本さんは、優勝によって覚悟が決まったことや、プレゼンで伝えた政策提言やファンドの組成などのtodoリストが、たった半年で信じられないほど進捗したことを伝えた。

思い願う未変化を、いち早く体現しようとする人たち。今回のソーシャルグッド・カタパルトは過去最高レベルといっても過言ではない登壇者たちが集結して、渾身のプレゼンを行った。こういう世界になるべきじゃないか? これが実現すべきじゃないか? その呼びかけに、会場に集まった人々は共感し、激励の拍手を送った。
今回登壇したのは13人、時間の許す限り登壇前に話を聞いた。それぞれ紹介したい話がたくさんあるので、プレゼン動画とともにご紹介していこう。
カタパルト史上最年少、15歳の世界への挑戦
登壇者の多様性には自信があるICCサミットだが、今回のソーシャルグッド・カタパルトは最高にバラエティに富んでいる。下はNIJINアカデミーの学生である小中学生の子どもたちが、上はフード&ドリンクアワードでも大活躍したジーバーで働く皆さんがいる。
子ども天才ドラマーとして名を馳せていたYOYOKAさんは現在15歳。この登壇の約1年前に、シンクロの西井 敏恭さんの紹介でICCのオフィスにやってきた。エンターテインメントの本場、アメリカで挑戦するため家族で渡米して活動しており、タイミングが合ったICC FUKUOKA 2025での登壇となった。

スポンサーの協力を得て用意されたドラムセットはステージ右手に設置され、前夜に確認済みだ。7分のプレゼン時間中、5分はプレゼンで2分は演奏を披露する。1年前はミュージシャンのジュニアたちとバンドを組むと聞いていたが、現在の活動状況を聞いた。
「同世代のバンド作ろうと思ってるんです。前に一度作ったけれど、身近な人たちとじゃないと続けられないので、もう一度やろうかと」
最新アルバム『For Teen』は、ヘビーロックからジャズ、アンビエントなものからレゲエまでジャンルを越えた14曲を収録、演奏はもちろんのこと作詞作曲、ボーカルを担っている曲もあり、日本同様に、本場アメリカでも名だたるミュージシャンが才能と実力を認めている。ライブ経験も豊富で、小柄な体はエネルギーに満ち、ドラムスティックは2~3日で折ってしまうという。しかし本人は至って謙虚だ。
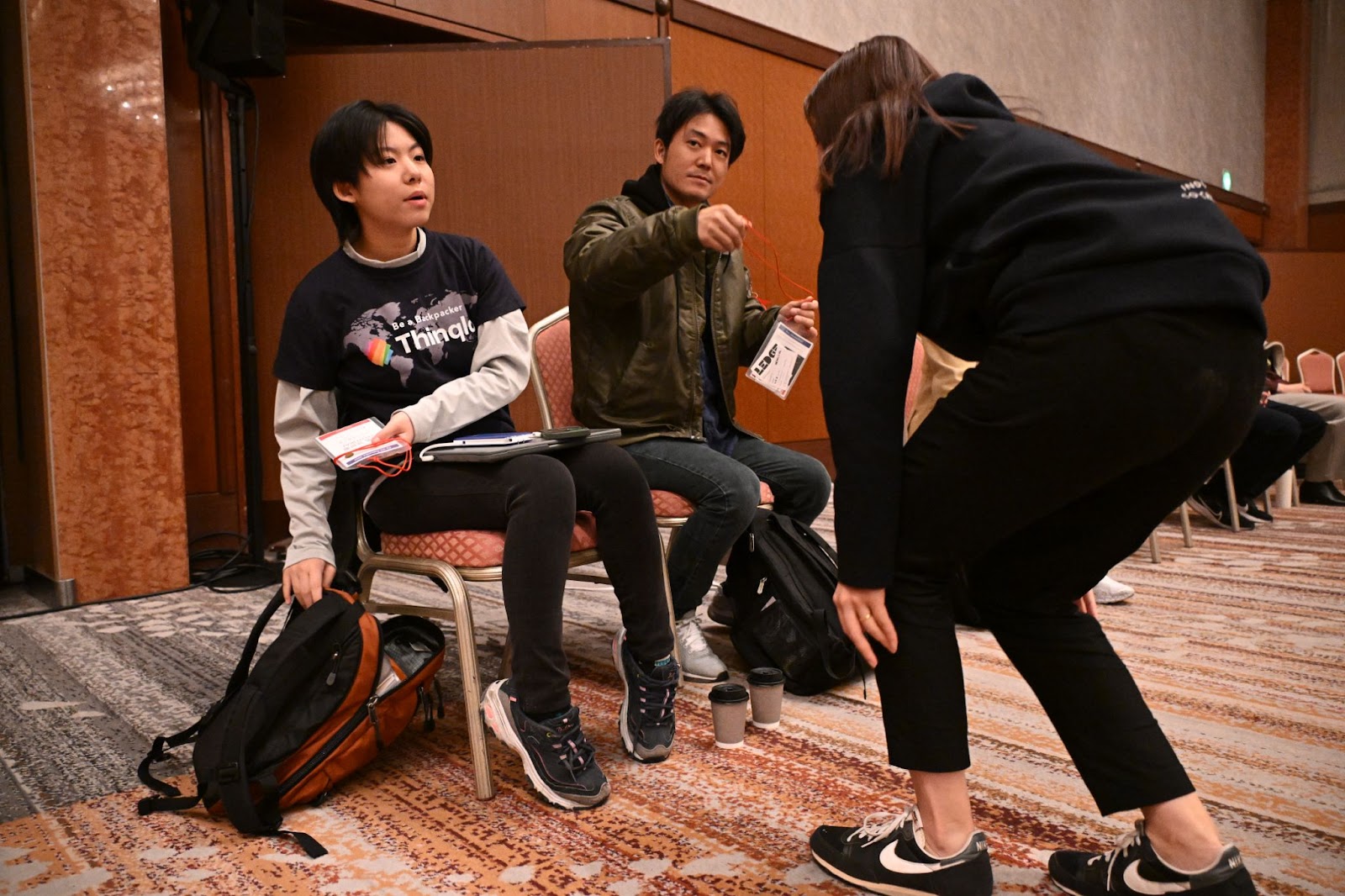
「5分しかないし、喋るのは演奏と別ものじゃないですか。でも、若い時に世界に挑戦するのが大切ということを伝えたい。現状の問題として、若すぎると奨学金やサポートしてくれるようなところは本当に少なくて、条件がすごく限られるので、私は何も受けられませんでした。それがもっと広がって、支援する人がもっと増えればいいなと。
アメリカでの日本の好感度の高いものは、今は野球やアニメですけれど、音楽っていないんですよ。私はそこに挑戦したい。サーフィンとか、他にもこれから挑戦したい人がいるので、本当にいろんな、ありとあらゆるジャンルで日本人が活躍してくれるといいなと。私も挑戦中です!」
才能あるミュージシャンはクレバーなのを証明するように、YOYOKAさんはプレゼンも上手で、当事者による説得力は他にはないものだった。世界水準の才能を応援してほしいという純粋な願い。それはスポーツ選手のようなウェアを着ている教育の環の鈴木 健太郎さんとも共通するメッセージである。

鈴木さんは、日本の未来を支えるSTEM(科学技術などに優れた理系人材)の卵たちを支援している。海外のコンテストや大会に帯同して痛感していることを伝えたいという。
「シリコンバレーや中国がすごいということを、大人の文脈でみんな知っていたり語っているんですが、その土台は若年層の育成。日本と海外、そこから差がついていることを知っているのは、実は世界で勝負している子どもたちなんです。
日本トップの子どもたちを育成していると大人は言うけれども、子どもたちがどれだけ歯がゆい思いをしていることか。日本の大人の都合で実力が発揮できない。そこを皆さんに知っていただいて、子どもたちと一緒に社会を変えていけたらと思っています」

心が動く瞬間が毎分あるような場所
ICCサミットや、福岡に出張で来たことのある方は、博多駅前の広場にたくさん農産物などが並ぶファーマーズマーケットのようなものを目にした人もいるかもしれない。Tryfeの境 美希さんは、今回のICCサミットの開催地、福岡市内で地元の生産者さんたちを盛り上げる「福マルシェ」を運営している。
「これまでのプロセスが本当に宝物だなと思っていて、7分間にこの数年間のすべてを込めてお話できる機会をいただけたことが、本当に光栄だと思っています。今日は生産者の人たちの想いを一緒に連れてきていると思っているので頑張ります」
さぞ地元愛が深いと思いきや、境さんは東京育ち。福岡が好きになって移住をして、ホテルを作り、そこで提供する食事を考えるために農家を訪ねて「こんなにかっこいい人たちいるんだ」と衝撃を受けた。
「東京ってそれこそ1時間、1週間で結果が出る仕事って多いじゃないですか? 農家さんたちは年単位で、80歳の農家さんが、あと10回しか挑戦できないと言う。そういう人たちと普段触れ合うこともないし、存在さえも知らないから、その人たちと一緒に生きていける街を作りたいと思って始めたのが福マルシェです。
ICCサミットは憧れの存在として知っていたけど、私には遠いものと思っていたんです。でもマザーハウスの山崎さんがご紹介くださって、その推薦に応えて全力を尽くしたいと思っています」
フード&ドリンクアワードでは審査員としても参加した。登壇はこれからだが、初めて参加したICCの感想を聞いてみると、
「想像以上でした。こんなに人の心が動くものなのかという瞬間をたくさんたくさん見て。登壇者も受け手側も、心が動いてる瞬間が毎分毎分あるような場所なんて、世界に他にあるのかなって思うぐらい」
と前日のアワードファイナルを思い出して感動が込み上げている様子。しかし、境さんのプレゼンも同じくらいに心がこもった、言葉から感情があふれるようなもので感動的だった。生産者が消費者がつながる場を作り出した境さんもまた、変化を起こしている人なのである。
人生の、自分との約束みたいな場所
この2日前に開催されたチャレンジャーズナイトで北三陸ファクトリーの下苧坪 之典さんから聞いたのは、驚くような話だった。
「前回カタパルト・グランプリに挑戦してから2年越し。2年間ここまでスピード感を持って日々を過ごして、形になるとは思っていなかった。自分が思ったより進んじゃった。2年前のグランプリでコミットしたことが、それ以上の形となって、もう僕じゃ手に追えないほど(笑)。
仲間もすごく増えて、資金も12億ぐらい調達していて、今年はその10倍調達したいと思っています。グローバルでそれぐらいやらないと間に合わない内容です。
自分自身もコミットしているし、助けてほしいというニーズがそれだけあると理解している。ソーシャルチェンジャーの事業だと思うので、世の中を本気で変えていかないといけない。そういうタイミングに僕は来たのかなと思っていたんです。だから今回お声がけいただいた時に、ぜひと言って。
ICCがなければ、今はないです。22年、23年で登壇して、そこで自分の未来との約束をちゃんと公衆の面前でしたことが、今にすべて活きている。だから今回のプレゼンで未来をもう一度改めて、予測しに来たっていう感じです。
これまでやってきたことを言うんじゃなくて、これからこうしていかなきゃならない社会とビジネスの両方を宣言。言葉にすると、本当にそうなる。本当に実現するからマジで怖くて、この1カ月くらい、資料が作れなかった。やりたいことが多すぎるんです。
ICCは投資家に対するプレゼンじゃなくて、本気で一人の経営者、一人の起業家が、どういう人生を歩んでいくのかっていうところを含めて評価していただける場所。僕にとってはビジネスも大事ですけど、それ以上に人生の、自分との約束みたいな場所なんです。なんかビジネスコンテストという感じではないですよね」

ここで伝える言葉が実現する、そう2日前に語っていた下苧坪さんは今、穏やかな表情で会場でプレゼン資料を眺めている。
「今回はある意味 ICC のピッチの集大成かな。僕は死ぬまでチャレンジをし続けたいと思っています。社会課題を解決することがライフワーク。オーストラリアやアメリカ、いろんな人たちの思いを背負ってきている。未来を宣言して、そこに向けて走るための意気込みを伝えます」

悲観するよりプラスに変えていく機会に
それぞれにかける思いがあってこの場に集まっている。下苧坪さんの話を聞いていたら、ジーバーの皆さんが台車で足早に運び込んできたものがある。何かと思ってバックヤードまで追っていくと……

プレゼンのときに審査員席に配布する豚汁であった。今回のフード&ドリンクアワードで話題騒然、優勝を飾ったじいちゃんばあちゃん手作りの自慢の豚汁である。登壇のタイミングで温めて、刻んだネギを添えて配られることになっている。永野さんは言う。
「シニアが活躍する場をたくさん作る事業ですが、高齢化社会は僕の課題というよりは日本全体の課題であり、解決するわけのない課題です。社会を変えるのは無理なので、それに向き合って、悲観するよりプラスに変えていくという気持ちで、ここにいる素敵な皆さんとCo-Creationしていけるような機会になれば嬉しいです」
前日のアワードでの優勝は予想していただろうか?
「恐れ多すぎます! 昨晩もCo-Creation Nightでも言いましたが、自分が1位になれなくても、何も悔しくない本当に素晴らしい方々ばかりでした。とにかく美味しくて、尊敬に値する方々で、全く予想外でした。(小林)雅さんから言っていただいて、じいちゃんばあちゃんを連れて来れなかったら絶対なかったと思う。


でも、美味しさは舌で感じるだけじゃなくて五感で感じるもので、その場の雰囲気や、料理人との会話でより美味しくなるというのが絶対あると思う。ばあちゃんのあの笑顔とあのトークで100倍ぐらい美味しく感じたんじゃないかと思います。
昨夜はうちのマネージャーとじいちゃんばあちゃんで、優勝のあと飲みに行ったという動画と写真が送られてきました(笑)。来てくれた3人以外もみんなで準備を手伝ってくれたんですよ」
じいちゃんばあちゃんがいないと成り立たない事業。アワード会場で大活躍したはつゑさんは「若い人たちに混じって若い人のパワーをいただいて、元気をもらってやる気が出ました」と言っていたが、若い人たち側は、自分たちはまだまだ甘い、敵わないと思ったのではないだろうか?

生まれてきた時の元気いっぱいな子どもに戻す

転がるようにして、子どもたちが会場になだれ込んできた。修学旅行として参加、デザイン&イノベーションアワードに出展したNIJINアカデミーのブースで大活躍した6人の子どもたちである。これから登壇する校長先生、星野 達郎さんの姿を見つけて次々にハイタッチしている。
子どもたちは審査員席のすぐ後ろ、客席の最前列に陣取って腰掛けた。豚汁を届けたジーバーの皆さんも、客席の最前列でスタンバイしており、その姿を見つけた子どもたちは自分の名刺を配りはじめた。




ICCサミットのカタパルト会場といえば、緊張感あふれる雰囲気が特徴だが、子どもたちがたった数人いるだけで、ほっとするような雰囲気も加わっている。彼ら・彼女らを見ると、みんなが笑顔になる。その存在感がもたらす穏やかさに、これがあるべき社会の姿かもしれないと感じる。

子どもたちが自分の席に戻ったあと、校長先生でもある星野さんに話を聞く。起業家としての自分のプレゼンについてよりも先に出たのは、子どもたちへの思いだった。
「昨日のアワードファイナルで、5年間学校に行けていない子が生まれて初めて人前でスピーチをして、その時はめちゃくちゃ泣いていたんですけど、夜の打ち上げで見たことないような笑顔をした。今回ICCでCo-Creationさせてもらって彼女の人生が変わったので、校長として本当に感謝の思いでいっぱいです」
子どもたちが配っている名刺には名前と顔写真に加えて、広報大使など肩書きが入っていたと伝えると「え、本当ですか?知らなかった」と笑う。子どもたちは屈託がなくのびのびとしているように見えるのに、入学当初は自分を出せず、死にたい、消えたいなどと言っていたと言う。
「生まれてきた時はみんな元気いっぱいだったはず。だから、生まれてきた時に戻してあげるというのにこだわっています。会場の皆さんも一緒に教育を変えていけるという具体像を示したいと思います」
アワードでの大活躍で、すでにCo-Creationが17決まっているといい、この登壇で目標の20に達したいと意気込む。星野さんの熱意を見ると、それは容易なことのように思われた。

超凡人でも、インパクトは生み出せる

教育系の登壇者が多いソーシャルグッド・カタパルトのなかでも、Timedoor Academyの徳永 裕さんは異色だ。IT企業のサラリーマンとして訪れたフィリピンでストリートチルドレンの姿を見たことと、人口2億8000万人のインドネシアのポテンシャルに賭けて、まずは現地でシステム会社を作った。
それがバリ島最大級のIT企業に成長したのち、IT教育事業をスタートさせ、現在はスマホ経由で学べるAIを活用したITスクールでプログラミングや、語学、アントレプレナーシップなどさまざまな教育を提供している。生徒は世界5カ国50拠点、6,500人いるという。
「生徒たちは8歳〜12、3歳ぐらい。今は地域のコミュニティにスクールがあるという状態を作りたいので、オフラインで店舗を作っています。現地の人を雇って働いてもらって、地域の方に受け入れていただけるようなスクールを目指しています」
学校に行けない子どもたちがいる場所に学校を作る日本人、建物だけじゃなくて、学校そのものを作るなんて本当にすごいことである。
「僕は普通の日本人で、超凡人だと思ってるんですけど、そういう人間でも勇気を持って海外に踏み出して挑戦すれば、社会貢献というかインパクトを与えられるということを10年間かけて学んだので、その軌跡を見ていただいて、何か自分にもできるんじゃないかと勇気を与えるようなことをプレゼンでお話できたらと思います」
タイミング合わず話を聞くことはできなかったが、fondiの野原 樹斗さんも東南アジア・アフリカを中心に、英会話教育のメタバース空間を作っている。
登壇時のプレゼン動画とともに、野原さんが、英語を学んだユーザーたちの人生をどれだけ変えたのか、その成果がわかるので、ぜひご覧いただきたい。日本の大学との取り組みも始まっている。
▶︎運命に抗う自信を、ここから─196カ国200万人に届けた「英会話メタバース」|fondi代表 野原(note)
On-Co水谷 岳史さんは、「さかさま不動産」という事業で空き物件を借りて挑戦したい人をその内容とともに紹介して、それに共感し条件の合う大家とマッチングする。メディアでも取り上げられている新しい形の不動産業を営む水谷さんの主張はこうだ。
「人口が増えていった時代のまま、新しい建物を作り続けて、人は新しいものを探している。でも実は逆で、空き家を使いたい人を探さないといけないんじゃないかと思うんです」
やっていることは、借りたい人と貸したい人のマッチングで賃貸不動産だが、ウェブサイトには物件情報ではなく、人情報が並ぶ。登壇を目前にしてもなお、思いをいかに伝えるべきかと頭をひねっている。
「人生でこんなに文字と向き合ったことは初めてです。伝える言葉や文章の調整をこんなにギリギリまで考え尽くそうとすることだけでも、プレゼンに挑戦する価値はあったと思います」
難治性のがんを治療するための経口薬を開発しているFerroptoCureの大槻 雄士さんは、リアルテック、スタートアップとカタパルトを転戦していて、これが3回目の挑戦。登壇して伝えることでこういった薬の開発や、その進捗を知らせることが大事であると、以前に語っていた。
治療で患者本人だけでなく、家族の生活も壊れてしまうこともある。経口薬であれば、治療にまつわるさまざまな負担を大きく減らすことが期待でき、患者や家族のみならず、ひいては医療システムを支える社会にも大きな良い変化をもたらすために、大槻さんは登壇を続けている。
どうやらRICE MEDIAのトムさんこと廣瀬 智之さんは、ひどい体調不良から復調したようだ。会場を元気に歩き回り、「完全復活です!」と笑顔を見せている。初日のスタートアップ・カタパルトでは入賞ならなかったが、制作配信している1分動画は社会課題を扱っているから、むしろこちらがメインフィールドだ。
動画同様の歯切れのいいトーク、熱の入ったプレゼンで結果は6位に入賞。冒頭の自己紹介こそ同じだが、途中からスライドを入れ替えて、若い人に社会課題を伝えるメディアとして存在したい強い意志を伝えた。カタパルト後には次回のソーシャルグッド・カタパルトで、事業を紹介する1分動画を賞品として出したいという提案までしてくださった。
地域に変化を起こして、明るい未来の夢を描く

NEWLOCALの石田 遼さんは、各地域に“新たな地元の人”として入って、地域活性のスーパー助っ人を担う。ICCにも参加している稲とアガベの男鹿や、ローカルフラッグの丹後などで、まちづくりを行っている。日本の各地で八面六臂の活動を続ける石田さんが、登壇で伝えたいこととは。
「いま地域の希望があるっていうことを伝えたい。人口が減っていって、やっぱりみんなあまり明るくはないです。それを僕らが各地域のリーダーと一緒に実際に変化を起こして、明るい未来を描いていくと変わっていく、ひいては日本が変わっていったらいいなと思っています」

石田さんはカタパルト事前のワークショップでの投票ではふるわなかったが、そこからプレゼンを磨き上げて2位に入賞した。石田さんの会社名でもあるが、地元外の人たちが地域活性に関わることが、ICCの参加者を見るだけでも最近顕著な傾向である。
「人たちの種類というか、地域の課題に興味がある層が変わってきたと思います。私も東京出身でコンサルやったりと、プロフェッショナルキャリアですが、少し今までとは違う系の人が増えてきた。しかもただ口を出すだけじゃなくて、しっかりがっつり行ってやる人が増えてきたかもしれません。
僕らは地域のリーダーと一緒に組んでいて、その人たちの思いに触れて、場合によって一緒にやっていく。その地域の夢を一緒に作っていくみたいなことは非常に楽しいですね」
今回の登壇は、ともに男鹿でまちづくりに取り組む稲とアガベ岡住さんの紹介によるもの。ICC初参加の印象は?
「あの……こんなに真剣に、がっつり時間を使うことになるとは思わなかったです(笑)。この熱狂がすごいですよね。それを皆さんやられてるのがすごいなと思いますし、(小林)まささん何人いるんだみたいな感じですね(笑)。
昨晩も(Co-Creation Nightで)社会課題の部屋にいましたがすごく楽しくて。友達が多かったんですが、半分ぐらいは初めての方で。考えていることや目線が近くて非常に仲良くなりました。本当はもう少し話したかったんですけど、今日があったので。でも本当に素晴らしい場だと思います」
古くからの運営スタッフで、石田さんの知り合いの上野 純平さんが様子を見にやってきて「珍しく緊張している!」と驚いている。百戦錬磨のプレイヤーであっても、いざ想いを伝える7分間を与えられると緊張するもの。伝えたいことがたくさんあるならばなおさらである。
司法は社会を変える可能性のあるツールだと伝えたい
そして、今回優勝となったLEDGEの亀石 倫子さんである。ICCサミットのカタパルトやセッションでは「既存のやり方、ルールを変える必要性」がよく議論され、それに挑戦する人たちが多くいるが、法律側のプロフェッショナルがついに現れた。大歓迎というモードでお話をうかがおうとしたら、亀石さんはむしろ肩身が狭そうな様子だ。
「日本において司法の存在意義、存在価値、市民の司法に対する期待はまだまだポテンシャルがあるというか、使われていません。司法というのが、社会を変えるための1つのツールになるとはなっていないし、人々もそう思っていないし、期待もしていない。
でも非常にポテンシャルのあるツールであって、実際私たちLEDGEのメンバーが関わった訴訟で法律や、制度が変わることを経験してきて、それを本格的に持続可能な組織としてやれないかと、海外でもそういう活動があるので、日本でもやろうと志を持った人が集まって始めたんです。
皆さんと違ってこれはビジネスではなく、結果でお返しするしかないので、寄付だけで成り立たせないといけない。だから私たちの活動の意義を知っていただくのが。今日お伝えしたいことです」
話すことは慣れていても、この場に緊張もしているようだ。
「こういう場を知らなかったので、場違いな気もしつつ、こういう場で多くの方にお話をさせていただくのは非常にありがたいし、おそらくほとんどの人が初めて聞くような話だと思うんです。すごく嬉しいなと思っています。でも…若干場違い感が(笑)」
みんながきっと話をしたがる、こういう場に来てくださることにとても意味がある、と重ねて伝えると、やはりこのカタパルトに出るべきと推薦してくださった方がいて、今回登壇を決めたという。
「寄付をしていただくたびに、こういう活動を多くの人が知らないということに気づいて。いろんな起業家の方や、今までお会いしたことのないような方々に向けて、プレゼンテーションする機会が何度かあった時に、カタパルトに出るよう勧められたんです。
分野が違うので本当に場違い感があったんですけど、セッションを聞くと、やってることは全然違うのに、課題と感じることや人材に関してなど非常に共通していて、伝え方や言葉の選び方もとても勉強になって、共有できる話題と知識と経験もあるんだと思って、それが自分でも意外でした。
昨日の夕方からしか来ていなかったんですけど、これからはぜひフルで参加したい。それでこんなにICCサミットにはたくさんの方が来ているのかと理解できました」
カタパルトでは13人の最後に登壇。それまでのプレゼンターたちも多様でそれぞれに素晴らしく、そのなかでもLEDGEは異色だったが、押し殺したような声で語る亀石さんに、会場は集中して聞き入り、これはとても重要な活動で必要なものと皆が腑に落ちて、応援の空気に変わるのが見えるようだった。
審査員たちも学び、勇気づけられるカタパルト
13人のプレゼンはあっという間に終わり、会場はさまざまな感情があふれるような雰囲気になった。感想を言いたい審査員が多いのもこのカタパルトの特徴で、審査や講評を伝えるというより、新たに加わった仲間を歓迎し、新たな課題を伝えてくれたことに感謝し、取り組む勇気を讃え、改めて自分の決意を語るようなものばかりであった。


AgeWellJapan 赤木 円香さん 3人目のピッチ(fondiの野原さん)からずっと泣いていて、ちょっと感想を言える状況じゃないんですが、まずは豚汁が本当に美味しかったです! 作ってくださった方、いらっしゃいますか? ありがとうございました! あとドラムも最高でした。
今日、諦めてはいけないんだという言葉に本当にそうだなと思いました。社会問題や課題に向き合っていると、小さな諦め、孤独が積み重なってしまうけれど、私たちが諦めてはいけない。私は三度の飯よりシニアの笑顔が本当に見たい。皆さんも皆さんなりの使命感でここに立たれている、その勇気を改めて感じましたし、私もまたここから頑張っていきたいなと、ただただ勇気をいただく時間でした。
ReBuilding Center JAPAN 東野 唯史さん まちづくりをやっていて、社会課題、空き家など色々なものを勉強してきたつもりだったんですが、改めてまだまだやれる手があるんだと勇気づけられました。
公共訴訟の話もそういう活動、努力があって僕らの生活って変わっていくことを僕は初めて知りました。今までボトムアップ型でやっているけど、究極のトップダウンで国と戦っていくという話はすごい元気をもらえて、感動しました。


LX DESIGN 金谷 智さん なぜそんな面倒くさいことやってるの?とか、なんでそんな難しいことやっるの?という話が何度も皆さんの中からありましたけど、僕も同じように公教育領域をやっていて、本当に同じ気持ちです。
僕はこのソーシャルグッド・カタパルトに登壇したことで、自分のパーパスとかビジョンみたいなものが受け入れてもらえるという信頼を場や社会に持てるようになった経験があります。皆さんにとっても今日が、参加されている皆さんとの対話を含めて、そういう素晴らしい1日になるんだろうなと思います。
CHEERS 白井 智子さん こういう場で私1人の方をピックアップしないように気をつけているんですけど、今日はあえて、15歳のYOYOKAさんのプレゼンにすごい心が動かされてしまって。
ICCはビジネスの場、ビジネスの延長と思ってたんですが、YOYOKAさんのお話を聞いて、このICCっていう場は挑戦者たちの場なんだということを感じて、自分がCHEERSって言っているのに、と突きつけられました。お礼をさせてくださいという気持ちです。

テラ・ルネッサンス 鬼丸 昌也さん 「天職」って英語で言うと、「calling」って言うんですよね。だから自分の内側に囁きかけてくるものに素直に従ってる人の言葉は響くんだと思います。ここにいらっしゃる皆さんそれぞれが、それぞれの内側に響いてくる声に従っているからこそ、みんなを動かし、自分を動かし、社会を動かしていくんだと思っています。
改めてここにいる審査員や聴衆の皆さんは、皆さんの内なる声を聴いて自分の内なる声を確認した、そんなひと時だったと思ってます。そういう場にいさせていただいたこと、そう思わせてくださったことに感謝申し上げたいと思います。
優勝はLEDGE亀石さんへ
「ありがとうございます」
優勝が発表され、胸元を押さえて感無量の面持ちの亀石さんは言葉を続けた。

「嬉しすぎて……。いつも私たちは国とか、ものすごく巨大なものと戦っているので、すごく戦いモードに入ってしまって。いつもはニコニコしているんですが、こういう場に来ると、いつも怖い顔で、怖い感じで話してしまうんです。
最後の締めくくりなのに非常に怖い感じで終わってしまったと思って。非常に暗い雰囲気にさせてしまったと思って、登壇が終わって舞台の横のところで落ち込んで。せっかくこのような素晴らしい会をシリアスな感じにしてしまったと思っていました。
私たちの活動、ビジネスでもなく場違いと思ったりしたんですが、司法によって社会を変えるという取り組みがあって、それを支えてくれる市民の方がいれば、確実に社会が変わっていくということのを皆さんに知っていただけたこと、こういう場をいただいて、それを評価してくださったこと、本当に嬉しくて、ありがとうございます。
今回初めてICCという場を知って、皆さんの抱えている課題や志が共通していて、学ぶことが非常に多い場であることを知って、ぜひこれからはフルで参加したいと思います。本当にありがとうございました」
司法を変えるという、国民の声を代表する大きな挑戦を続けている亀石さんは、”シリアスな怖い声”をネタに笑わせながら、心の底から嬉しそうな笑顔を見せた。私たちの社会をよりよくするために、利益を追い求めず改正に尽くす活動を私たちが応援しなければ、誰が支えるのだろうか。
こうやって亀石さんが知らせてくれなければ、私たちは今もまだ、公共訴訟の活動のことを知らなかっただろう。
「皆さんに知っていただけたこと、こういう場をいただいて、それを評価してくださったこと、本当に嬉しくて」ここで亀石さんは、一瞬声を詰まらせた。見るからに気丈な亀石さんが声を詰まらせたときに、人知れず続けている戦いの大変さが垣間見えて、会場の空気も一瞬揺れた。

ソーシャルグッド・カタパルトが終わると、続いてソーシャルグッドのラウンドテーブルがある。登壇者も審査員も一緒になって、話し合いたいテーマを少人数でディスカッションするという場のため移動をすればいいのだが、カタパルトの余韻を惜しむように、会場からはなかなか人が動かなかった。4位に入賞したNIJINの星野さんもその一人だ。
「教育を変える責任をいただきましたし、変えられるという勇気もいただきました」と、星野さんは噛み締めるように言った。
カタパルト冒頭にナビゲーターを務める豊島 里香さんが「たった一人の願いがやがて本当に世界を変えていくんだということをICC、特にソーシャルグッド・カタパルトを見ていると信じさせてもらえる」と語っていたが、それは本当だ。
変化は容易に起こらず、むしろAgeWellJapan 赤木さんの言うように、自分の小さな諦めや孤独と戦う日々のほうが多いのだろう。亀石さんのように数年がかりで1つの司法を動かすような、恐ろしく根気のいる仕事なのだろう。
しかし、下苧坪さんのように、地球温暖化に真っ向から挑み、変化を信じて実現しようとする人、平凡なサラリーマンだったのに、バリ最大のシステム会社や学校を作って感謝される徳永さんのような人もいる。
ICCに初参加のじいちゃんばあちゃんがアワードの優勝を勝ち取ることもできるし、不登校の子どもが校長先生にハイタッチし、大人に名刺を配りまくることだってできる。変化は実現できるのだ。ここは、よりよい社会を求め、体現する人たちが集まって刺激を与え合い、変化の実現への力を得る場となるのだ。
今回は欠席だったが、ユーグレナの出雲 充さんがずっと言ってきた「2025年にミレニアル世代が中心となり社会が変わる」というのは本当だったのかもしれない。2021年の京都のソーシャルグッド・カタパルトが歴代最高と考えてきたが、今回はその時にはいなかった大勢の観客がいて、それを超えるレベルの高さと感動があった。
時代が変わり、変化への風が吹いてきた。ソーシャルグッド・カタパルト2.0ではないが、ソーシャルグッドを取り巻く環境も含め、次のステージに入ったことを感じる9回目の開催であった。
(終)
編集チーム:小林 雅/浅郷 浩子/小林 弘美/戸田 秀成


