▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!
▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!
ICC FUKUOKA 2024のセッション「ファンに愛されるサービスを生み出すマーケティングとは?」、全5回の②は、「ファンの定義とコミュニティを作るために意識していることは?」。社内で「ファン」という言葉を使わないと決めたクラシコム 青木さんと、ファンとしか呼ばないというヤッホー 井手さんの話から、熱量高いコミュニティの生まれ方へと話は進みます!ぜひご覧ください!
ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2024は、2024年9月2日〜9月5日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。
本セッションのオフィシャルサポーターは プレイドです。
▼
【登壇者情報】
2024年2月19〜22日開催
ICC FUKUOKA 2024
Session 3D
ファンに愛されるサービスを生み出すマーケティングとは?
Supported by プレイド
(スピーカー)
青木 耕平
クラシコム
代表取締役社長
秋元 里奈
ビビッドガーデン
代表取締役社長
井手 直行
ヤッホーブルーイング
代表取締役社長
大槻 祐依
FinT
代表取締役社長
(モデレーター)
遠田 健
istyle me
代表取締役
▲
ファンの定義とコミュニティを作るために意識していることは?
遠田 では、まず1つ目のテーマです。
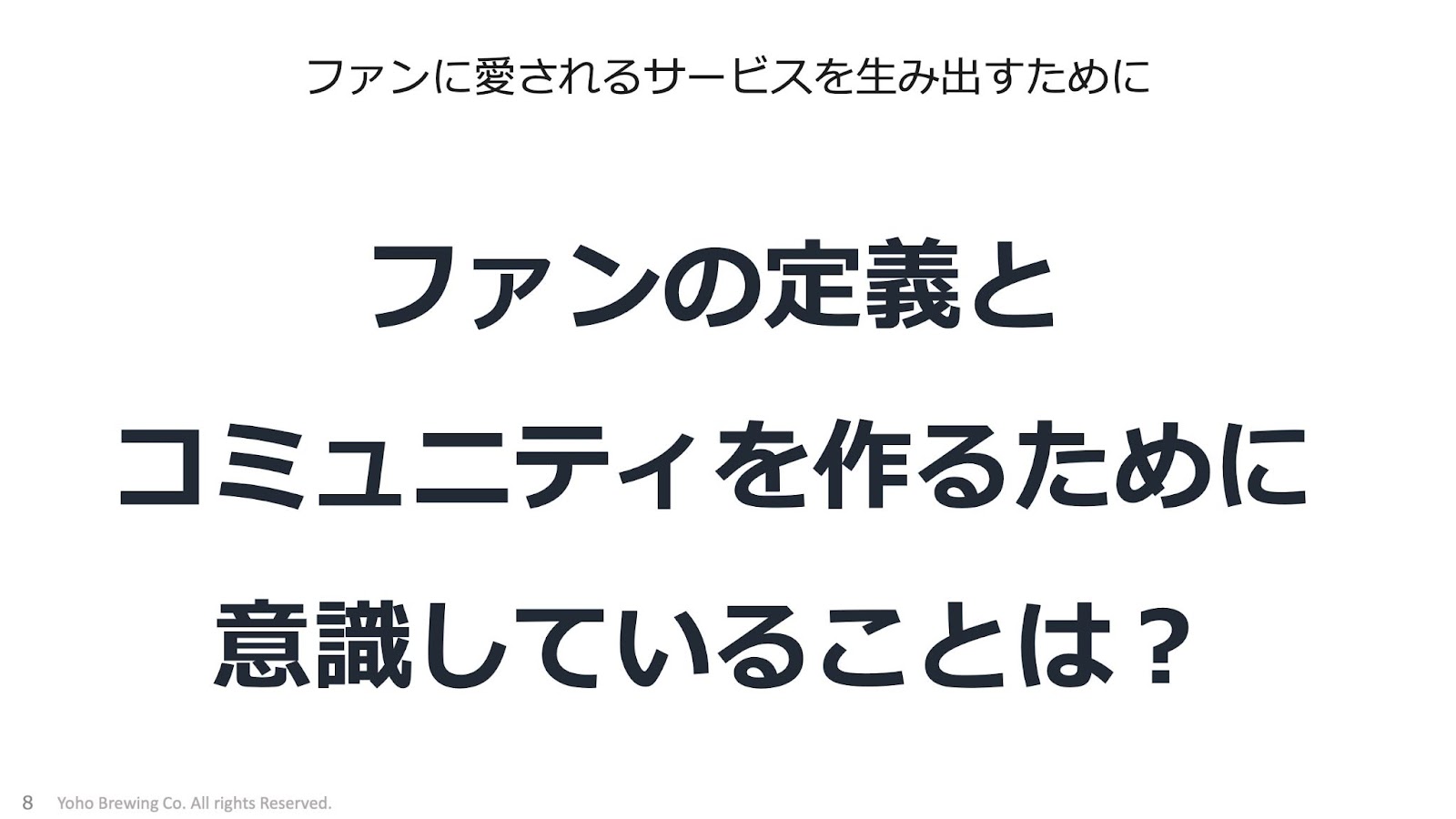
ファンに愛されるサービスを生み出すために、ファンの定義とコミュニティを作るために意識していることは何ですか?
大槻さんから、ご意見をうかがってもいいですか?
大槻 これは、私が出させてもらったテーマです。
私たちはSucleという女性向けメディアを運営していますが、コミュニティを作っており、Sucleファンの皆さんが集まって今のトレンドを話しています。
コミュニティの作り方には色々あると思います。
セッションテーマは「ファンに愛されるサービスを生み出すマーケティングとは?」ですが、ファンというものをどう捉え、そのコミュニティを作ろうとしているのかについて、お話を伺えればと思いました。
「北欧、暮らしの道具店」はすごく愛されているブランドだと思うので、青木さん、いかがですか?
社内で「ファン」という言葉は使わない理由
青木 ありがとうございます。
難しいですね。
テーマをひっくり返してしまうようですが…まず、僕らは社内で「ファン」という言葉は使わないと明確に決めています。
「ファン」という言葉が悪いと思っているわけではないのですが、ただ、僕らの目の前にいるのはお買い物をしてくれるお客様であり、SNSでアカウントをフォローしてくださっているフォロワーであり、また、コンテンツの視聴者や読者です。
ファンという、何だかよく分からないけれど、何のファクトもなく総合的に僕らのことを好きという人は存在していないはずだという前提に立っています。

ですから、読者やお買い物をしてくださるお客様から、我々が時間やアテンション、お金などの対価を頂いていて、その対価を超える価値を提供できていれば、信頼関係やエンゲージメントが色々なチャネルで生まれると考えています。
ただ、ファンという言葉を雑に使ってしまい、結果的に社内の意識が変になってしまうのが怖かったので、ファンという言葉を使うのをやめたという感じです。
大槻さんが言ってくださっている「きちんと定義をしよう」という考え方に、ベースはすごく近いと思います。
曖昧な定義のまま、ファンという言葉を使うと、すごく支持されているように思う、つまり皆さんがついてきてくれると勘違いして独りよがりになってしまうのが怖いと思っています。
ですから、あくまでも、頂いた対価を超える価値を提供できているからこそ維持できている関係です。
それは貯金みたいなもので、すぐになくなる関係ではないと思いますが、もし貯金がなくなると、離れていってしまうのだと思います。
貯金はしなければいけないのですが、その貯金を下ろさなければいけない局面もあると考えています。
貯金は、ただ増えていくだけでは意味がなく、増えたら運用することが大事です。
信頼関係の貯金ができたら、例えばブランドの意義を拡張するチャレンジをする時に、貯金を少し下ろすことになるかもしれないけれど、成長に投資しようと考えています。
関係性の貯金をどう運用し、投資し、より大きく育てていくかを常に考えています。
コミュニティというより、課題のソリューションを個別に提供

青木 コミュニティを作るという感覚も、僕らにはあまりありません。
基本的に我々は、情緒に関する課題を解決するサービスを提供していると考えています。
情緒に関する課題とはつまり、「このままでいいのかな」というモヤモヤであり、それにソリューションを提供しているということです。
ソリューションには2種類あって、「そのままでいいよ」と言ってあげるパターンと、「変わりたいならこういう方法があるよ」とお手伝いするパターンです。
コンテンツや商品を使って、お客様にソリューションを提供しています。
そして、相互にそれを行う場がコミュニティであると思っています。
しかし我々は、困っている、もしくは課題を持っているお客様に、個別にサービスを提供している方法を選択しているので、コミュニティというよりも、ラジオパーソナリティとリスナーの関係ですね。
リスナー同士が結びついて、お互いに便益を交換し合う場というよりも、皆さんにラジオ番組を配信して、「このままでいいのかな」という夜のモヤモヤした時間を癒す時間を提供している感覚ですね。
ヤッホーはファンを「ぞっこん度」で5段階に定義
井手 話していいですか?
ファンとは呼ばないようにしている、の対極で、我々は「ファン」としか呼びません(笑)。
(会場笑)
ですので今、青木さんに怒られている気がしました(笑)。

青木 そうなってしまうのが辛いなと(笑)。
井手 いやいや、冗談です(笑)。
我々はファンとしか呼んでいなくて、それが当たり前すぎて、取材などを受ける時に、「ビールメーカーが、お客様のことをファンと呼ぶのは珍しいですね」と言われて、ハッと気づくのです。
一般的なことではないのだな、と。
お客様という呼び方は、あまりしないですね。
ただ、青木さんが言っていたような問題に途中で直面しました。
ファンと言っても色々なレベルがあるので、ファンという言葉を使って社内で会議をしても、噛み合わないのです。
「それはファンが望んでいることなの?」「そうだよ」「ええっ!?誰を指してファンって言ってるの?」みたいな(笑)。
そういう問題に直面する機会が度々あり、3、4年前から、ファンという言葉をちゃんと定義しようと取り組み始め、現在、ファンを5段階に分けて定義しています。
例えば、5段階の一番上のレベルの人は、よなよなエールに、ヤッホーブルーイングにぞっこんである人です。
色々な調査やアンケートから分析したり、顧客管理システムへの投資もあり徐々に把握できるようになりました。
2番めのレベルは、ぞっこんまでいかないけれど、すごく好きである人です。
そういう風に、分かりやすい言葉で5つに分けて定義しています。
去年(2023年)までは、1から5の「熱狂度」という言い方をしていました。
ただ、熱狂という言葉も…何か、狂っているみたいじゃないですか?
「イエーイ!!」みたいな(笑)。
(会場笑)

まあ、僕はどちらかと言えばそういうタイプではあるのですが(笑)、熱量が高いファンもいれば、ふつふつと思いを湧き上がらせるファンもいます。
ですので、「熱狂度」という言葉は合わないと考え、昨年末にリーダー何人かで「ぞっこん度」に変えることに決めました。
どう思うかと社内に聞いたら、若い女性からは「昭和っぽいですね」と言われたようです(笑)。
(会場笑)
最終的に「ぞっこん度」に決まったらしいですが、我々はそういう区分けをしています。
レベル3の人を4に、レベル1の人を3に上げるための施策などを言語化できて、お互いに共通認識を持つことができるようになりましたね。
ファンが喜ぶ環境を作れば、コミュニティは自然と広がる
井手 あと、コミュニティを作るためにというと、おそらく、この場に集まっているような方の多くは、コミュニティを作りたいと思っていると思います。
現場スタッフもそう思っていると思います。
でも僕は、コミュニティを作りたいとは思っていなかったのです。
ここは青木さんにも似ているかもしれません。
我々は、ファンイベントをよく開催します。
▶最新イベント情報(よなよなの里)
その際、ファン同士がすぐに仲良く、友達になるのです。
イベント後に飲み会に行ったり、後日再会の場を作ったり、イベントがきっかけで出会って結婚したというすごいケースもあります。
結婚したカップルのさらにすごいところは、結婚指輪によなよなエールの月のマークをデザインして指輪を作っていいか、私に許可を求めてきたのです(笑)。
そんなの、良いに決まっているじゃないですか!
遠田 それは、ぞっこんレベルですか(笑)?
井手 マックスですね!
遠田 レベル高いですね。
井手 そんなことが起きた時、この人たちは環境を整えると喜んでくれるのだなと思い、それなら、環境を整えるためのイベントの作り方をしようと思いました。
もう一つ、ファンについてまだ整理できていなかった、14、15年前に、「たかがビールなのに、なぜお客様はこんなによなよなエールが好きなのか」という顧客調査をしました。
2時間くらいかけた、デプスインタビューです。
はじめは「美味しいからよなよなエールが好きだ」ということを言っていましたが、それを深掘りしていくと、「美味しい」の先には、本人たちも気づいていない5つのベネフィットがあったのです。
その5つのうちの1つが、仲間を作ることでした(※) 。
▶編集注:「よなよなエール」の5つの情緒的ベネフィットは、「理想像の実現」「癒される」「自己確信」「共感する」「仲間を作る」(日経BizGate記事参照)。
本人たちは気づいていないのですが、よなよなエールを飲んでいて楽しいと思うシチュエーションを聞くと、それは仲間と一緒にわいわい飲んでいるシーンでした。
そういう意見が複数あったので、彼らは、気づいていないけれど仲間を作るというベネフィットが,よなよなエールのブランド価値に寄与していることが分かりました。
友達を作る機会を増やせば、ますますよなよなエールへのロイヤリティが上がると10数年前に確認したので、何かを設計する時に、喜んでもらうため、好きになってもらうために設計していると、勝手にコミュニティが広がっていきました。
ですから、コミュニティを作るために何かをするというのは…言葉尻を捕らえて申し訳ないですが、こちらがコントロールするというのは、あまり好きではなくて……。
遠田 「できた」みたいな感じですか?
井手 そうですね。
環境を整えればみんながハッピーになるということであれば、全力でそうしたいと思って取り組んでいますね。
遠田 なるほど。
秋元さん、いかがですか?
秋元 すごい話だったので……。
遠田 左右からでしたからね(笑)。
秋元 (笑)。
ファン=購入者ではない「食べチョク」の場合

秋元 実は、私たちもあまりファンとは呼ばないのですが、私たちのサービスのファン=購入者ではないことも多いのです。
サービスをすごく応援してくれているけれど、メインの商材が生鮮食品なので…例えば、料理しない人の場合、情報を拡散はしてくれても頻度高く買ってくれるわけではないのです。
今、ユーザーの8割以上が女性で、全体の半分以上が50代以上です。
このICCサミットの場に来ている人の中に、サービスを応援してくれている、けれど顧客ではない人も多いです。
そういう人もファンだと言ってしまうと定義が広くなってしまうので、ユーザーの購入回数などで切り分けて考えることが多いですね。
コミュニティについては、食べチョクのコミュニティを作ろうとか、約9,000軒の生産者を集めてコミュニティを作ろうとか、何回かチャレンジしたことはあります。
しかし人数が多いとテーマがばらけてしまうので、井手さんの例にも近いのですが、意図して作ろうとしたコミュニティは熱量があまり高くなかったです。
蓋を開けてみると、食べチョクの中に小さいコミュニティがたくさん出来ていました。
食べチョクというサービスが好きな人もいるのですが、多いのは、特定の生産者のファンですね。
約9,000軒の生産者にそれぞれのファンの小さなコミュニティができている感じです。
ですので、どちらかと言えば、そういった小さいコミュニティが生まれやすくするためにはどういうサービス設計をすればいいかと考えており、生産者とやり取りできる機能や、他のユーザーの反応が見られてコメントできる機能などを追加しています。
気づいたらコミュニティができていたので、それをより自然に生み出すためにはどうするかという思考でサービス作りをしていますね。
遠田 なるほど、ありがとうございます。
「美味しさ」×「情緒的価値」がファンの熱量を高める
青木 このテーマは大槻さんが出しましたよね。
我々は自分の事業しか見ていないですが、色々な事業に関わっている大槻さんは、ファンの定義についてどう考えているのかすごく聞きたいです。
大槻 ありがとうございます。

ファンと言えば、熱量の高いユーザーであると聞くことが多いです。
例えば、セールの時に買ってくれる人はファンではないという意見もあります。
クライアントからは、どんな時でも製品を愛して買ってくれる人、応援してくれて口コミを書いてくれたり他のユーザーを送客してくれたりする人についてヒアリングをすることが多かったですね。
彼らが何を好きで買っているのか、SNSで投稿をしたりコメントしたりしている理由は何か。
そうさせているのは理念や商品力であり、そういう話をクライアントから聞かせていただくことが多いです。
秋元 井手さんの例は、「美味しい×仲間作り」でしたよね。
ですので、「機能的価値×情緒的価値」が大事なのかと思います。
機能的価値だけだと、ファンにはならないと思っています。
なぜなら、他社でより良い機能が出てくれば、そちらに動いてしまうからです。
我々も、美味しいことは前提として、ストーリーへの共感や、生産者に貢献したいという社会的欲求が、背中を押す要素として存在します。
ベースには「美味しい」があるのですけど、「×何か」が大事かと思います。
井手さんは、5つのベネフィットがあるとおっしゃっていましたよね。
井手 僕も、秋元さんと全く同じ考えです。
ビールが美味しいことは大前提で、そこが崩れると、そもそも買ってもらえません。
日本の会社の製品は品質がすごく良いので…嗜好品なので好き嫌いはあると思いますが、大手メーカーも含めてどのビールも美味しいです。
でもそこに情緒的価値が付加されると、ファンの熱量が高くなっていくことを感じます。
僕らはビール屋ですが、事業ドメインを「ビールを中心としたエンターテインメント事業」と定義しています。
ビールメーカーはたくさんありますが、ビールを中心にしたエンターテインメント事業はありません。
大手ビールメーカー4社は競合だと思っていますが、僕らの中では、ディズニーや劇団四季も強烈な競合だと捉えていて、参考にしています。
ビールを中心に、コト消費に一生懸命取り組んでいたら、ファンの熱量が高くなっていきました。
何となくイメージはしていましたが、実際に調査をしてみると、熱量の低い人たちには情緒的価値が一切伝わっていませんでした。
例えば、僕らの発信していることが全く届かない、福岡県のコンビニで、よなよなエールというビールの機能的価値しか知らずに買っている人たちは、美味しいから買っています。
でも美味しい以外の情報が伝わっていないと、5段階の上の方のレベルにはならないなと実感していますね。
コミュニティは売上以外の利潤を創造
秋元 エンターテインメント事業という言葉で思い出したのですが、クラシコムでは映画を作られていましたよね(※) 。
▶編集注:「北欧、暮らしの道具店」初のオリジナル映画となる『青葉家のテーブル』(2018)に始まり、以下の映像作品を発表しています。『ひとりごとエプロン』(2019)/『スーツケース・ジャーニー』『リヴィングライフ』(2021)/『庭には二羽』『離ればなれになっても』(2022)。
青木 はい。
秋元 D2C事業だと思っていたので、あれにはびっくりしました。
どうしてそういう施策を行ったのでしょうか?

青木 やり始めたのは偶然というかノリというか…そんな大した理由はありませんでした。
いくつか要因はありますが、コミュニティに絡めて話すと……「コミュニティを作れば売上が上がるのか、利益が出るのか」という議論がよくありますよね。
企業が得る利潤のうち、売上や利益は一部です。
会社とは、社会から有利な条件で経営リソースを引き出して運用することで富を増やしていく仕組みだと考えています。
売上を上げることも利益創出も、資金調達の手段の一つですよね。
我々の提唱するライフカルチャーを表現するための様々なコンテンツに興味を持ってもらい、どこかのチャネルで我々からのアプローチを受け取ってくださるという許可、つまりフォローしてくださったりダウンロードしてくださったり、を得るとします。
そうすると、人材を募集した時、100人がすぐに応募してくるという状況になります。
僕らは、エージェントも採用媒体もほとんど使わずに採用ができています。
また、僕らのB2Bのお客様は、B2Cを通じて僕らを好きになってくれた方が、勤めている会社を通して話を持ってきてくれるというケースが多くなります。
お客様として好きでいてくださる方が、投資家として株を買ってくださる状況も起こり得ます。
僕らの場合、それをコンテンツやIP(知的財産)で実現しようとしています。
皆さんのビジネスにも、そういう要素が何らかの形であるのだろうと思っています。
コミュニティとは社会の縮図だと思うので、その中には、会社でタイアップコンテンツを発注する人やファンドマネージャーや仕事を探している人など、色々な人がいます。
商品やサービスだけでお客様とつながっていると、他のルートでは、他社の力を借りないと経営リソースを調達できなくなり、全体的な利潤が減ってしまいます。
ですから、具体的に何のためにコミュニティを作るかと考えると、売上や利益だけではない利潤を創造するためかと思います。
結果論ではありますが……。
井手 深い!
遠田 通常、こういう流れだと、そのために何をするかなど、HOWの話になると思うのですが、今回は冒頭にも言った通り、大きなテーマの、ふわっとしたセッションなので、次のテーマに移りたいと思います。
青木 ポエム、すみませんでした(笑)。
(続)
▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!
▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!
編集チーム:小林 雅/星野 由香里/小林 弘美/浅郷 浩子/戸田 秀成


