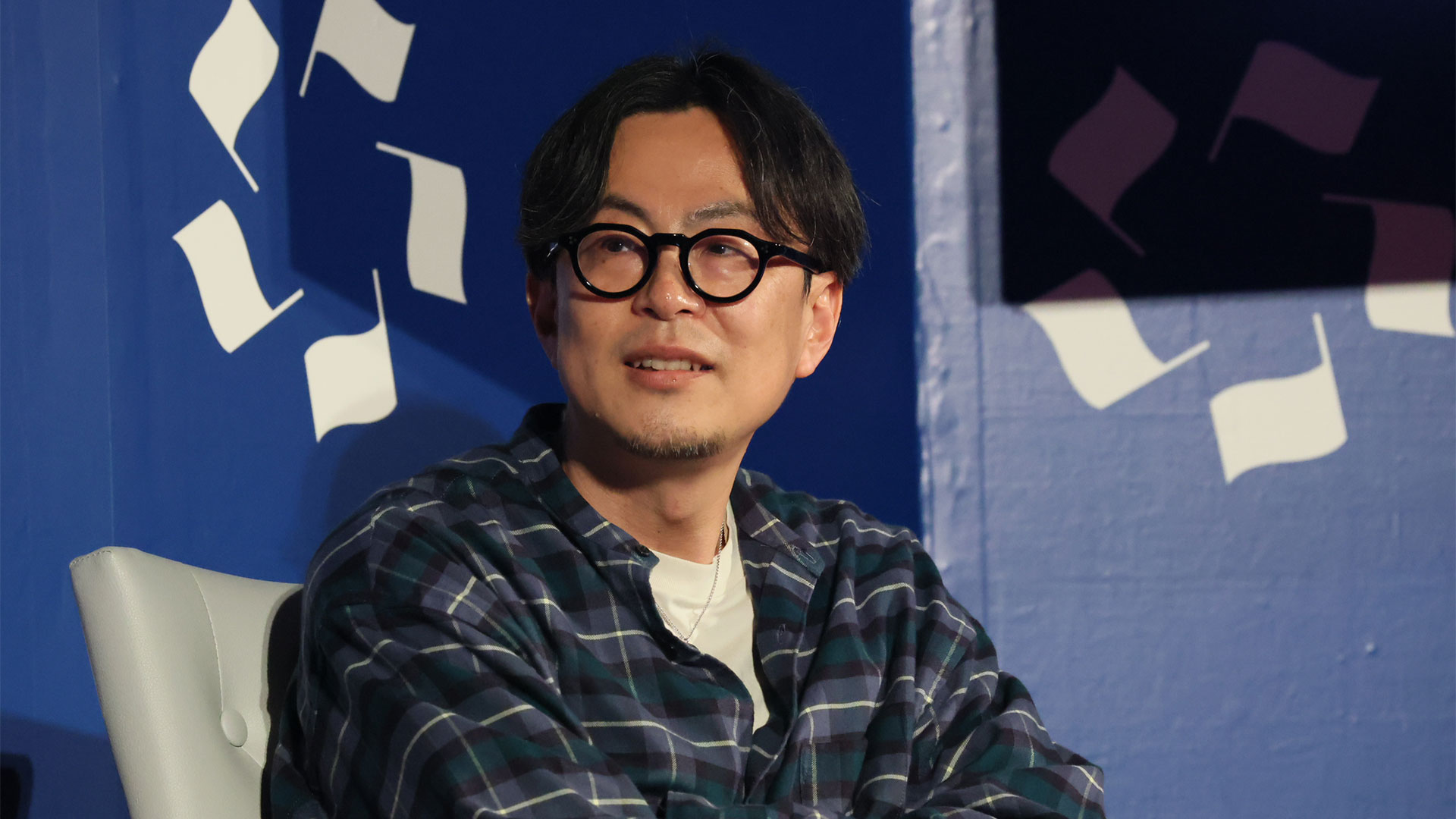▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!
▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!
ICC FUKUOKA 2024のセッション「ファンに愛されるサービスを生み出すマーケティングとは?」、全5回の④は、「一番大事にしていることは?」。ビビッドガーデン 秋元さんは生産者ファースト、FinT 大槻さんはN1を大事にすること、クラシコム 青木さんは顧客と愛し愛される関係性を築くこと、ヤッホー 井手さんはファンが幸せになることを挙げます。ぜひご覧ください!
ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2024は、2024年9月2日〜9月5日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。
本セッションのオフィシャルサポーターは プレイドです。
▼
【登壇者情報】
2024年2月19〜22日開催
ICC FUKUOKA 2024
Session 3D
ファンに愛されるサービスを生み出すマーケティングとは?
Supported by プレイド
(スピーカー)
青木 耕平
クラシコム
代表取締役社長
秋元 里奈
ビビッドガーデン
代表取締役社長
井手 直行
ヤッホーブルーイング
代表取締役社長
大槻 祐依
FinT
代表取締役社長
(モデレーター)
遠田 健
istyle me
代表取締役
▲
一番大事にしていることは?
遠田 では、次のテーマに移りましょう。
愛されるサービスを作るために、一番大事にしていることは何ですか?
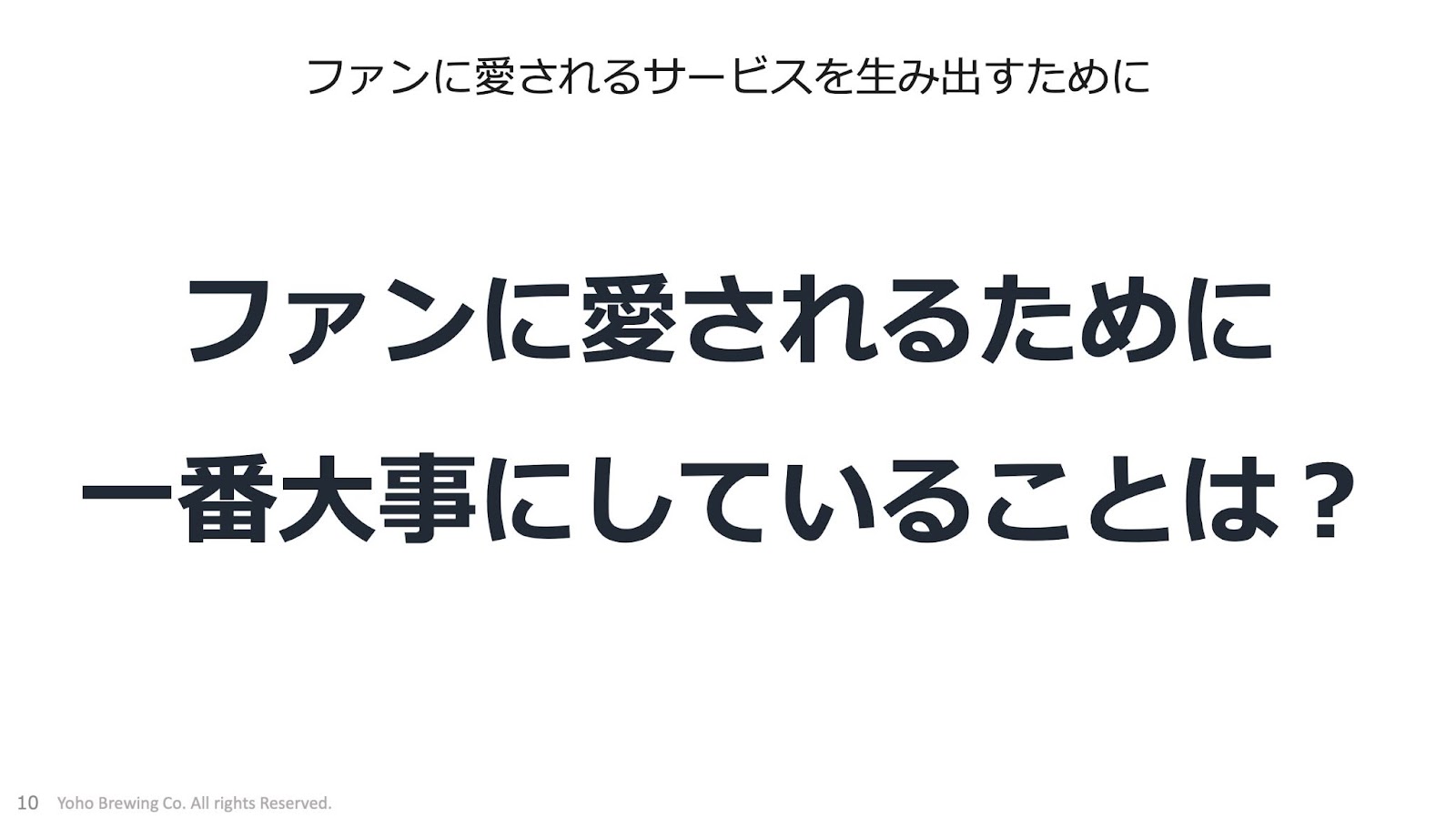
これは、井手さんからの質問です。
井手 はい、皆さん色々気をつけて活動されていると思いますが、その中で「ここは特に大事にしている」というものがあれば、参考までにお聞きしたいです。
「生産者ファースト」を貫く

秋元 先ほども話しましたが(前Part参照)、やはり一貫性をすごく大事にしています。
私たちは、「生産者ファースト」という考え方をとても大事にしています。
私自身の発信もそうですし、社内の会話も全て、生産者を主語にするよう意識しています。
企業の活動は、目先の売上をKPIにしているとどうしても、大事なものを失ったり一貫性がなくなったりしてしまいますし、一つの打ち手でファンが離れることがあると思うのです。
私たちは「生産者ファースト」を創業期からすごく大事にしていますが、ユーザーを置き去りにしているわけではありません。
もちろんどうすればユーザーに買っていただけるかという普通の議論もしますが、生産者の立場に立ってその施策が大丈夫かどうかを、必ずセットで確認します。
短絡的に「売上を上げるにはランキングを公開すべきだ」とはならず、「それだと困る生産者がいるけれど、こういうやり方ならできるだろう」と調整します。
生産者ファーストは、行動指針のベースにも入れています。
▶ビビッドガーデン新章突入。新しいValueを発表します。(ビビッドガーデン公式note)
経営陣から業績について話す際も、基本的には生産者ファーストで話すように意識しています。
会社の人数が増えてくると、代表1人の発信だけではなく、メンバーの発信も見られるようになります。
これまではありませんが、生産者を下に見たり、「もっと安い価格で」みたいに言ってしまったりすると、食べチョクはもうだめだねと思われて、お客様は離れてしまいます。
ですから、社内の日々の会話でもそこはすごく大事にしています。
遠田 大槻さん、いかがですか?
一人一人のユーザーの声を聞き続ける
大槻 私たちは、N1をめちゃくちゃ大事にします。
つまり、一人一人のユーザーの声を聞き続けることを大事にしています。

「Sucle(シュクレ)」の編集部のメンバーとユーザーはオフラインイベントで会う機会がすごく多いので、ユーザーに共感してもらうため、その際に言ってくださった意見やコンテンツを大事にしてどんどん作り続けることを大事にしています。
ですから、一緒に作れるようなイベントが良いという意見も出ます。
今の若者には、リアルで集まれる場があまりないので、私たちが提供する場に集まってくれていると思っています。
その時に、何がしたいか、どんなことに困っているかを聞いて、それらを解決できるであろうイベントを開催しています。
一人一人の声を大事にするということをし続けている気がします。
遠田 青木さん、いかがですか?
青木 色々あるので、一番というのが難しいですね(笑)。
愛し愛される関係性を築き、変化を厭わない
青木 愛されるよりも愛したい。
…マジで。
(会場爆笑)
遠田 KinKi Kidsですよね(笑)!?(※)
▶編集注:KinKi Kidsの楽曲『愛されるより 愛したい』のサビに、「愛されるよりも 愛したいマジで」という歌詞があります。
青木 (笑)。
遠田 誰かが歌い出さないか心配です、とさっき言っていました(笑)。

青木 そうそう(笑)。
どう愛されるかというよりは、我々が素直に愛せるユーザーはどこにいるのか発見することに最も力を入れています。
そうすれば必然的に彼らの気持ちは分かるし、できることは何でもしてあげたいと思う一方で、こちらが彼らを愛しているからこそ、相手にもフェアであることを求めますよね。
従属する関係性ではなく、こちらが愛して愛されたいと思えれば、「こちらとしては不本意だけれど、お客様が喜ぶならあれもやります、これもやります」という状況にはなっていかないです。
ですから、愛せる状況を担保するというか…サービス過剰になると、相手を愛せなくなりますよね。
「愛せないけどお金をくれるから」という関係になってしまう。
まず愛せる相手を見つけて、愛せる状況を維持することが、結果的に愛されることにつながればいいと願っている感じですね。
そういう関係性だからこそ、こちらのスタンスとしては、顧客や読者、ユーザーとの相互コミュニケーションの中で、自分たちも変化することを担保しています。
もともとヴィンテージの北欧食器屋として始まった事業ですが、「これもできる、これもやったら面白い」と色々しているうちに、どんどん変化していきました。
▶「北欧、暮らしの道具店」が生まれるまで──代表×店長が振り返る、クラシコムの歩み(1) 2006年〜2010年社史(クラシコム)
節操ないとも言えますが、ある意味、対話とはそういうものだとも思います。
コミュニケーションの結果として変化することを受け入れた上で、テーブルについて交わされるものを、対話と呼ぶのだと思っています。
ここは変えないぞ!と思って臨む場合、それは交渉や説得になりますよね。
ですから、対話的であるということは、自分が変化してしまう可能性があることを受け入れることだと考えています。
何かを言われて、御用聞きのように対応するのではなく、何かを要望されたわけではないけれど気づくとか、「確かに」と思うとか、そこからの変化を厭わない方が、愛という文脈において、結果的には一貫性があることになると思います。
行っていることは一貫していないですが、愛しているかどうかでは一貫しているということです。
ある人たちのことが好きで、彼らのために何かしてあげたいという思いのもと全ての行動をとっているという点での一貫性は担保されるので、自分たちでは、この変化を肯定しています。

井手 愛することは変わらないということですが、クラシコムらしさ、クラシコムの考え方や世界観は基本的には変わらないのでしょうか?
青木 いや、そんなことはないと思います。
「クラシコムらしさを大事にしよう」なんて、社内で言ったことはないですし。
ステークホルダー誰もが不満と喜びを分け合っている、健全な状態であることが何よりも重要で、それがいわばクラシコムらしさなのかもしれません。
秋元さんの言っていた、生産者とお客様の関係もそうですが、双方が少しずつ不満を分け合うことになりますよね。
フェアな状態でありたい、美しいものに取り組みたいというこだわりはありますが、「らしさ」が自分の中にあるわけではないです。
フェーズによって、何に取り組みたいかは変わりますし、目の前にいる方がどういうリアクションをしているか、自分たちがどういうことをしたいかによって、自分の中のらしさや美しさはどんどん更新していきたいと思っています。
ですので、こだわりのなさと素直さには結構定評があります。
しれっと何かを始めたり、しれっとやめたり。
目的は、うまくやりたいのではなく、それぞれ利害を持つステークホルダーの輪を閉じておきたいというか…伝わっていますかね(笑)?
変化には時間と手間をじっくりかける
遠田 会社のミッション、ビジョン、バリューは置いておいて、セールス、エンジニア、企画部にかかわらず大事にしている、言語化されたサービスとしての方針や指針はあるのでしょうか?
青木 理念体系として整理しています。
経営陣には、ミッションに基づいた会社経営のマニフェストがあります。
そのマニフェストのもと判断のポリシーがあり、ポリシーのもとどう振る舞うかについてのフォームがあります。
それらは全て言語化していますが、常にマイナーチェンジし続けているので、絶対的なものというよりも、今はこういう感じでやろうというものです。
▶「北欧、暮らしの道具店」を生んだクラシコムは、理念体系をどう整備してきたのか?(ダイヤモンド・オンライン)
秋元 従業員もその変化を受け入れる姿勢を共通して持っているから、数年前に言っていたことが少し変わっても、受け入れるべき変化だとみんなが納得できる状態ということでしょうか?

青木 それはわからないですけれど、ただ、雑にするのはダメですよね。
言葉を尽くしてめちゃくちゃ丁寧に説明し、時間をかけるからこそ変化させられるものだと思っています。
変化するということは不確実性が高まるということなので、ストレスが増えるのは当然です。
ですから、時間と手間という必要なコストをかけて、顧客にもサプライヤーにも投資家にもコミュニケーションするに尽きると考えています。
遠田 伺っていると、皆さんそれぞれですが、信念というか「私たちはこうです」と言い切れるものがあるから、人がついてくるのでしょうね。
今まで色々あったと思いますが、振り返って、アップデートして、信念を強固にしてきたのだと思います。
ファンが喜ぶこと、幸せになることを第一に
井手 「愛されるサービスを作るために、一番大事にしていることは?」というテーマは僕が出したのですが、僕からも一言いいですか?

皆さんのコメントに共感しています。
この質問への我々の回答は、「ファンが喜ぶこと、幸せになることを第一にすること」ですね。
ビジネスなので、お金や儲けが先に来ると、どうしても自社都合になってしまって、自分の都合の良いようにサービスや製品を作り、お客様が望んでいるかどうかという点が置き去りになってしまいます。
世の中ではむしろそういうことの方が、多いのではないかと思います。
僕らのビールやサービスを好きになってくれている人を考えて取り組み、満足度が高くなると、売上は後からついてきます。
この順番を間違えて、先に売ろうとし、売れる製品やサービスはこういうものではないかと考えて実行した瞬間、変な状態になるし、それはファンから見えてしまうのだと感じています。
それはそうだよねと思うかもしれませんが、色々な話を聞く限り、「ファンが喜ぶこと、幸せになることを第一にすること」を徹底している方は少ないと思います。
今日登壇の皆さんからは、それをすごく大事にしているというお話を聞けて、すごく安心しましたし、自分たちもこれでいいんだと思えました。
遠田 ありがとうございます。
(続)
▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!
▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!
編集チーム:小林 雅/星野 由香里/小林 弘美/浅郷 浩子/戸田 秀成