▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!
▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!
ICC FUKUOKA 2025のセッション「インパクト・スタートアップ(社会課題の解決と経済的な成長を両立するビジネス)のビジネスプランニングとは?」、全6回の最終回は、CHEERS 白井 智子さんの「数字へのコミットが薄いメンバーへの対応は?」という質問からスタート。壇上にいる人もそうでない人も同じ志を持つワンチームであること、ともに悩みながら発展することの大切さを再確認した本セッションを、最後までぜひご覧ください!
ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。
本セッションのオフィシャルサポーターは リブ・コンサルティングとスマートニュース です。
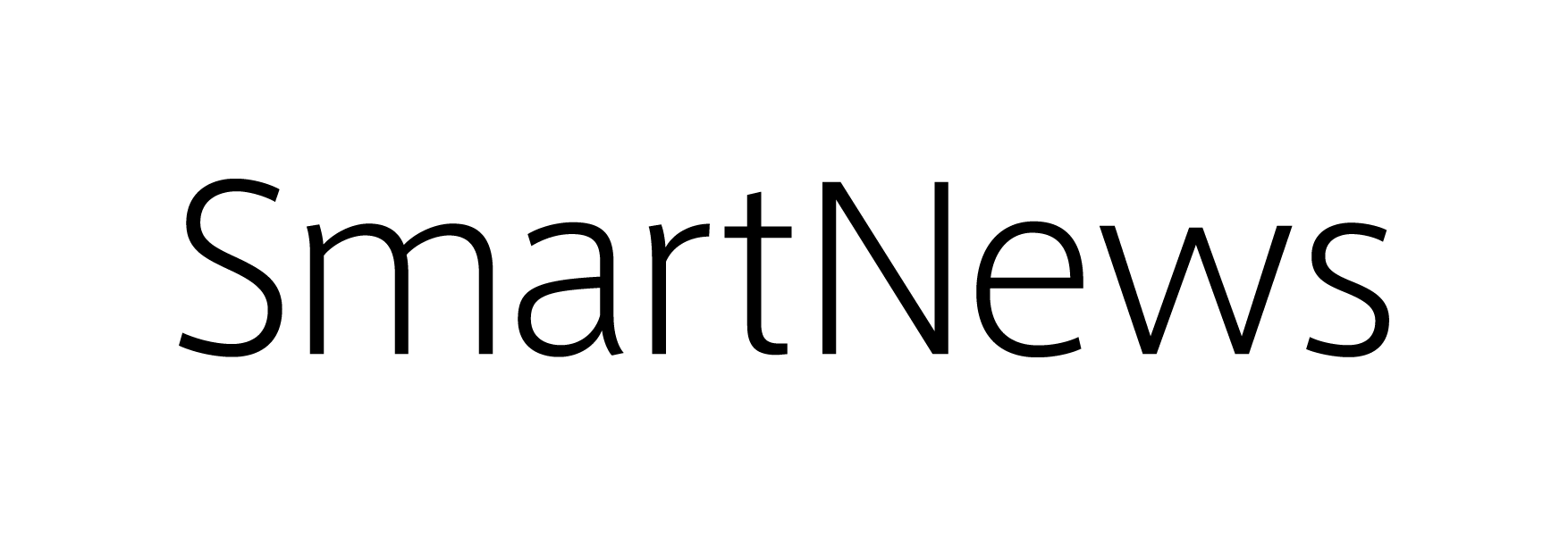
▼
【登壇者情報】
2025年2月17〜20日開催
ICC FUKUOKA 2025
Session 10B
インパクト・スタートアップ(社会課題の解決と経済的な成長を両立するビジネス)のビジネスプランニングとは?
Supported by リブ・コンサルティング
Co-Supported by スマートニュース
スピーカー・質問者・モデレーター
(スピーカー)
岡本 拓也
LivEQuality大家さん
代表取締役社長
田口 一成
ボーダレス・ジャパン代表取締役CEO
松田 文登
ヘラルボニー
代表取締役Co-CEO
(質問者=リングサイド席)
白井 智子
CHEERS
代表取締役
園田 正樹
グッドバトン
代表取締役
冨田 啓輔
HelloWorld
代表取締役Co-CEO
福寿 満希
ローランズ
代表取締役
(モデレーター)
江口 耕三
鎌倉投信
創発の莟ファンド運用責任者
山崎 大祐
マザーハウス
代表取締役副社長
▲
▶「インパクト・スタートアップ(社会課題の解決と経済的な成長を両立するビジネス)のビジネスプランニングとは?」の配信済み記事一覧
Q 数字へのコミットが薄いメンバーへの対応は?
山崎 では、白井さん、お待たせしました。
白井さんの質問の内容をを簡単にまとめると、松田さんも言ってくれたことですが、ベンチャーなのでゴリゴリ事業を推進していかなければいけないけれど、ソーシャルグッドを目指して来てくれる仲間は、数字へのコミットが薄いということがあります。
このあたりのギャップをどうやって埋めるべきか、KPI設定も含めてそういう人たちをどう動かしていくかという話だと思いますが、白井さん、お願いします。
質問者は子ども向けの体験をデザインするCHEERS白井 智子さん
白井 智子さん(以下、白井) ありがとうございます。
CHEERSの代表をしております白井 智子と申します。
▶無料で参加できる職業体験で、子どもが夢ややりたいことに出会うきっかけを創る「CHEERS」(ICC FUKUOKA 2023)

▼
白井 智子
CHEERS
代表取締役
幼少期に難治性疾患に罹患、15歳まで生きられないと言われた原体験を元に、全国の子どもたち向けに体験機会の提供を行なっている。2016年、息子が3歳の時に渋谷で保育事業を開始、8年で約2万人にプログラム提供。2022年、「ワクワクする大人になろう!」をコンセプトにCHEERS株式会社創業。全国の小中高生向けにキャリア教育事業xブランディング領域で事業を展開。現在は様々な企業や自治体との連携で子どもたちに無償で機会提供を行なっている。
▲
弊社は全ての子どもたちが今と未来にワクワクできる社会を作ることをミッションに、体験デザインの事業をしています。
向き合っている社会課題を一言で言うと、地方の子どもの体験格差というところになります。
ソリューションとしてどういうビジネスモデルかと言うと、教育では珍しい100% BtoBかつCSR予算ではなく、PRやマーケットといった営業予算をしっかり頂いて、今年で言えば、全国20カ所で約5万人の子どもたちに無償で体験機会を提供しています。
福寿さんの質問に答えられていたところとも近いかなと思うのですが、私としては1組織というところで皆さんがどう向き合われているか教えていただきたいと思います。
一言で表すと、本当に優しすぎる人たちがたくさんエントリーしてきてくれるのですよね。
でも、やっていることで言うと、多分ベンチャーの中でもすごく難しいことをやっていると思います。
CS側やオペレーション側はすごく頼もしい面はありつつも、ビジネスサイドにライオンやチーターのような人がどれだけこちらの界隈に興味を持ってくれるかという、組織戦略をどう描いているかと、かつCS側に対しても、自分たちも社会を前に進めるんだというところでのKPI設定を、皆さんがどうやられているのか、お聞きしたいなと思います。
山崎 ありがとうございます。
時間の関係で最後の質問になってしまうと思いますが、皆さん、いかがですか?
人のことは、本当に大きいなと思っています。
A サイトに載せている言葉が適切かどうか問い直してみては

松田 ヘラルボニーは、ウェブサイトからの見え方、伝わり方や、どう出していくかという捉えられ方に対しては、かなり意識しているつもりです。
「ソーシャルグッド」という言葉は絶対使わないとか、「インパクト・スタートアップ」という言葉をあえて使わないとか、あとは「社会課題の解決」という言葉は使わないとか。
今の時代においては、それは甘えになる可能性があると、私はまだ思っているのですね。
もちろんそういうものを目指している人たちは多いと思いますが、そういう言葉を使うことによって、そこまで儲けなくてもいいよねという甘えが見え隠れする人たちが現れる可能性があると、私自身はまだ思っています。
ですから、サイト上にそういう言葉を書いていないかとか、そういう人たちが勝手に来るような状態を自ら呼び寄せてしまってはいないかとか、一度問い直してみるのもいいと思います。
白井さんの人間性や雰囲気はもちろん存じていますし、世界観を非常に大事にしていると思うのですが、本当にこの人たちを呼びたいと思った時の呼び方があるとは思います。
そこは非常に大事だと思いますし、数字面へのコミットメントをする人たちをまずは業務委託として配置して、会社をかき回すということを、意図的にやってもいいかもしれません。
そういうものをあえて回すという考えを腹に据えることは、結構重要なのではないかと思いました。
山崎 ありがとうございます。
A ソーシャルがっちりの優秀な新卒を採用するのもあり

田口 すごく難しいと思いますが、1つは今の話で、見せ方です。
どう見られているかについては、よくよく注意を払うことです。
多分そういう人が集まっているということは、そういうメッセージを発信しているということが1つあると思います。
会社側が発信を変えることによって、反応が変わることがあると思うのですね。
僕らが「社会課題」から「SWITCH to HOPE」にパーパスをチェンジしたのも、まさにそれが理由で、それは1つあり得るかなと思います。
もう1つは、人材に関しては松田さんが言ったように、ビジネス界でトップ層の優秀な人材を引っ張ることですが、多分CHEERSの場合は、結構難しいと思うのですよね。
そうした時にもう1つの選択肢になるかなと思うのは、ソーシャルがっちりなんだけど実は新卒という人がいいのではないかと思っているのですよね。
学生でガリガリやっている人は、だいたいソーシャルと言っているのですよ。
松田 確かに。非常に優秀な人が多いですよね。
田口 優秀な人が多いですが、彼らはやはりインパクト・スタートアップに行ってしまいます。
でも、そうでもないぞというのが、すごく重要な選択肢になると思っています。
先ほどのボーダレスファウンデーションは、実は卒業したての非常に優秀な新卒2名が事業ヘッドとして採用が決まっているのです。
彼らは銀行と話をさせたりしても、新卒だと分からないですよね。
一切トレーニングもしていない、こういう層がたまたまいるのですよね。
多分、ソーシャルガチの中途は難しいけれども、ソーシャルがっちりの新卒がビジネスデベロップメント(事業開発)できる可能性は、ちょっと見ていいのではないかと思いました。
松田 すごく分かります。新卒は全然違いますよね。
山崎 新卒のほうが全然いいですね。それはうちでもそうです。
松田 こちらが圧倒されるくらい優秀な人が来ます。HelloWorldもそうですか?
冨田 うちもそうです。
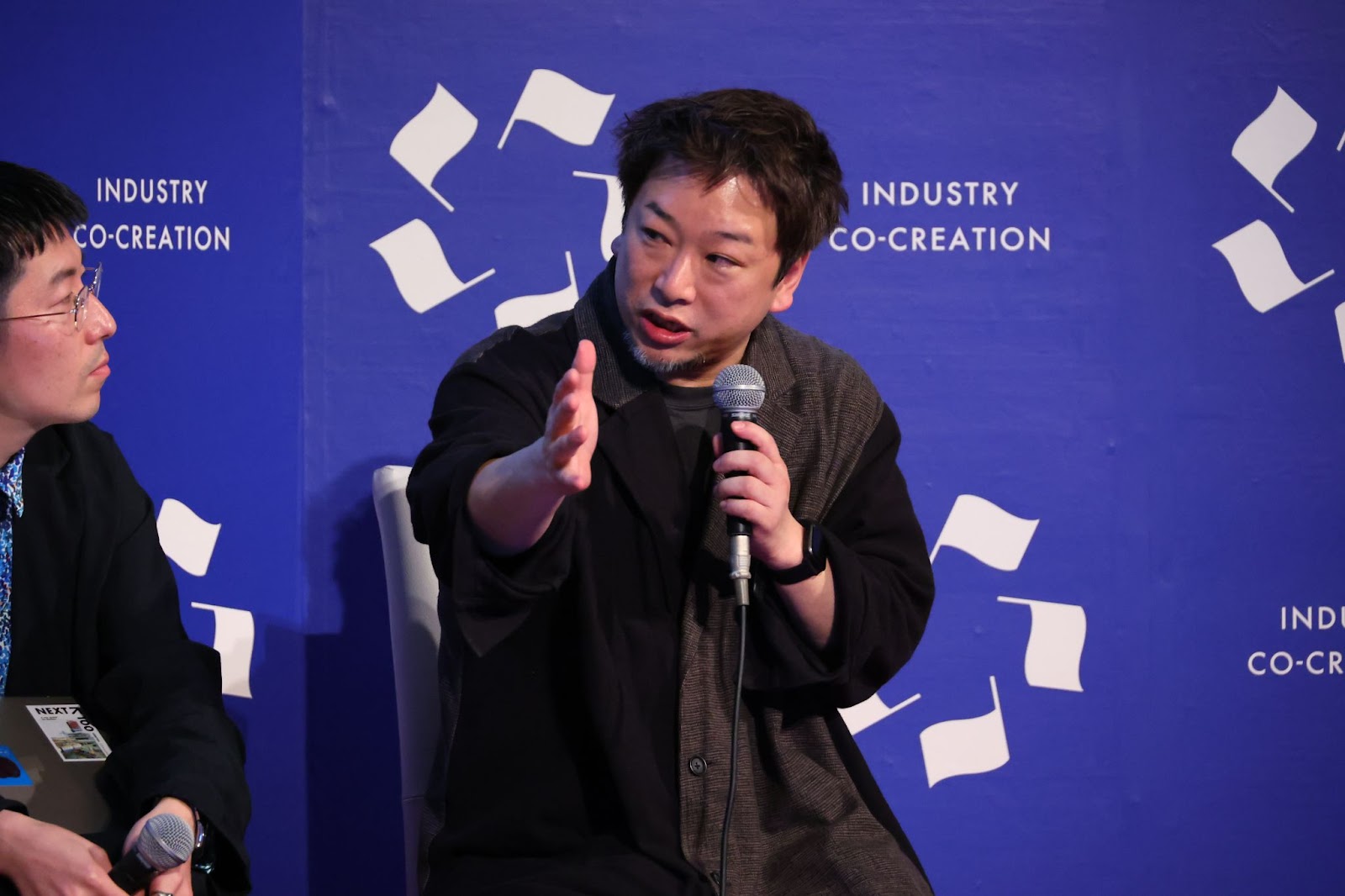
山崎 マザーハウスでは、新卒と中途を交ぜて、同じコンディションで、一緒に面接しています。
幹部候補生ですらそうです。
そうすることによって間違いなく分かるのですが、新卒のほうが深く物事を考えていたりもするので、そういうことはあると思いますね。
田口 あとは任せる職種だと思いますが、事業開発系では逆に経験値が邪魔するケースがあって、中途採用者でたくさん見てきています。
事業開発系の場合は、下手をすると新卒のほうがという感じがします。
白井 へえ。
田口 専門領域は中途採用者でしっかり。事業開発は新卒のほうがいいよということもあっていいかなと思います。
白井 ありがとうございます。
A ビジネスへの意識が高い人に接するとマインドは変わる

岡本 私からも、一言よろしいですか。
私もどちらかと言うと創業期なので、ちょうど先週、採用のnoteを書いて募集したところです。
皆さんの話を聞いて、新卒もそれでやってみようかなと思ったので、参考にさせていただきます。
その上で、私の場合で言うと、この人、本当にいいなという人全員を、結構それなりの給与で僕から一本釣りしました。
声を掛けたのは10年、15年来の友達なのですが、もともと友達の時はもちろんいつか一本釣りしてやるなんて全然思っていたわけではないんですよ、当たり前ですが(笑)。
そんな中で、みんなそれぞれ独立したりして、僕もLivEQualityという事業を始めて、お互いにいいタイミングでちょっと手伝わない?みたいな感じから入ってもらった人たちが、今コアメンバーになっています。
その上で、さっき少し触れましたが、我々も次のフェーズに入っているタイミングで、少数精鋭でやってきたのですが、今後はそれでは無理だなというところで、まさに白井さんと同じ局面を迎えています。
そこに関してはすごい参考になりました。
あともう一つ、我々が特徴的なのは、組織を分けていることです。
掲げているミッションは一緒ですが、つながりを届けるというのと、住まいを届けるというのはもともと全然違うので、つながりを届けるほうは組織形態にNPOですし、非常にソーシャル的な人を採用しています。
非常にソーシャル的な人を採用するのですが、ビジネス的でマインドが高い人と接すると、彼女たちは変わっていくのですよね。
ビジネス的な人もソーシャル的な人たちと出会うと、なるほど、本当の現場に価値があるなということに気づくのですよ。
組織の8〜9割は、丁寧にやってくれる人が大事
山崎 うちは組織体制が、岡本さんと全く一緒だと思います。
全員優秀な人を入れればいいというわけではなくて、むしろ8〜9割は丁寧にやってくれる人がいることが大事です。
それで儲かることをやれるかどうかが、経営者の仕事なのですよ。

岡本 それは本当にそうですね。
山崎 だからすごく分かります。
岡本 難しいことを言わずに、ひたすらやってくれる人が、隣にいるとめっちゃ癒されるんです。
(会場笑)
松田 そうですね。
岡本 本当に。
山崎 うちもそうで、接客が数字ばかり追っていたらいやじゃないですか。
多分、そういう話なのですよ。
岡本 あとは、皆さん、そうだと思いますが、経営者がご機嫌でないと組織が良くなくなります。
白井さんはいつもご機嫌そうですが、白井さんがご機嫌でいられる組織をいかに作り続けるのかが大事かなと思います。
山崎 ありがとうございます。ということで、残り5分を切りました。
江口さん、人に関して何かありますか?
新人を採るのは怖くもある

江口 「白井さん、類は友を呼んでいるんじゃないの?」という厳しいご指摘かなと思いました。
あともう一つは、新人の可能性はある一方で、新人を採るのは怖いですよ。
でも、壇上の皆さんは優秀な新人が入ってきたら、さらに優秀にできるパワーがあるからやろうということだと思います。
特に15%の営業利益がマストだとなった時に、15%の営業利益を出すようなビジネスモデルを描けという話なのです。
田口さんはこう見えてスパルタというかマッチョだなと思っていて、静かなるマッチョの中で鍛え上げていくという組織作りも必要かなと思いましたね。
山崎 ありがとうございます。
もうまとめの時間に入ってきておりまして、リングサイドの皆さんが主役だと思いますので、一言ずつ、何が学びだったか言っていただいて、終えていきたいと思います。
福寿さんから一言ずつ、順番にお願いします。
採用方法を変えてみる良いきっかけになった

福寿 ありがとうございました。すごく勉強になりました。
まずはビジネスの幹を見つける、育てるということと、あとはソーシャルグッド企業はビジネスに強い人をどれだけ巻き込めるかも重要だなと感じました。
まさに私たちの組織も優しい人が集まって、どうしようかなみたいなところもあったので、採用の仕方を思い切って変えてみるという意思決定ができそうな、良い機会を頂いたなと思います。
ありがとうございます。
利益率15%という目安を得た

冨田 私も利益率は重視していて、サステナブルに教育事業を展開している企業はどこだろうと考えて公文さんを見た時に、利益率が13%から15%で、僕もそこの目安を持っていたのですが、今日、田口さんから15%と聞いて、やはりそうだなと思いました。
あとなぜ15%なのかというところも、これからもっと深掘りしていきたいなと大変勉強になりました。
ありがとうございます。
自分のリソースを新規事業開発に注ぎたい

園田 組織ポートフォリオを考える際に、全体を考えながらやるということ、それに伴うガバナンスは、冨田さんがおっしゃられたように、僕も気にしてしまっていました。
そこに僕のリソースを何に使うべきかということに対しては、田口さんもおっしゃるように、僕は現場に出て、新規事業を作る人間として努力を注ぐべきだと思いました。
また、経営者として、お金の入りと出に関する大きな絵を描く必要があると、一つ視座を上げられたのかなと思いますので、本当にありがたかったです。
ありがとうございます。
ソーシャルグッドという言葉に甘えていた

白井 最後に質問させていただいて、自分自身がソーシャルグッドという言葉にめちゃくちゃ甘えていたなと思いました。
ご機嫌でいることをすごく大事にしていますが、大事にしすぎたかなと思いました。
最近いい意味でソーシャルグッドの垣根がなくなってきているからこそ、自分でゴリゴリにやろう、以上!と思いました。
本当にありがとうございます。
山崎 ありがとうございました。
では、岡本さんから、一言ずつお願いします。
NPOの素晴らしい経営者からぜひ学んで

岡本 会場の皆さん、リングサイドの皆さん、そしてスピーカー、モデレーターの皆さん、本当にありがとうございます。
素晴らしい時間を過ごさせていただきました。
最後に2つ端的にお話ししますと、NPOの経営者から学べることはたくさんあるということです。
目の前にテラ・ルネッサンスの鬼丸 昌也さんと日本承継寄付協会の三浦 美樹さんという1年前の福岡でのサミットで優勝された素晴らしい2人がいますが、おふたりから学べることはたくさんあります。
▶元子ども兵の社会復帰支援で、紛争の平和的解決を目指す「テラ・ルネッサンス」(ICC FUKUOKA 2024)
▶亡くなった後に自分のお金を寄付する「遺贈寄付」で、思いやりが循環する社会を目指す「日本承継寄付協会」(ICC FUKUOKA 2024)
あともう一つは、今日はPLの話が多かったなと思ったのですが、僕が見ているのはどちらかと言うと、BSとキャッシュフローです。
BSとキャッシュフローを見ていくことはすごく重要だなと思っていて、今日このセッションは終わりますが、経営者としてそこを見ていくことは重要かなと思っています。
本当に学びになりました。
どうもありがとうございました。
ここにいるみんなはワンチーム

田口 事業の伸ばし方は色々あると思うのですが、営業利益15%というのは、15%あると自己キャッシュでやるという選択肢を残しながらできるからです。
もっとスピードを追いかければ、利益率を減らしてもっと振ることもできると思いますが、どういう経営の選択肢を持っておくかと言った時に、自己資本でやるという選択肢が今後色々な可能性を作ると思っている場合は、それがよいと思います。
そうでないのであれば、出資を受けて一気に伸ばすというのはもう判断かなと思いますが、僕はソーシャルの領域でやっていくにあたって、資本市場も含めて、まだこの世の中の状況は激しく変化しているじゃないですか。
色々な変化がたくさん起きている中において、自分はまだ新しい選択肢を残しておきたいという意味で、営業利益15%、自己投資でどこまで伸ばせるかという体質を1本選択肢として持っています。
あと、今日このセッションで、僕はついつい本当に真剣に考えたのです(笑)。
みんな知り合いですけれど、それだけでなく、やはりワンチームですよね、このみんなは。
みんなの事業が大切だなと思って、ついつい本当に真剣に考えてしまったのですが、これが大きな特徴だと思うので、ぜひこの場に限らず、困った時はみんなで相談し合うことがよいと思います。
ぜひ一緒の作戦会議を定期的にやれたらいいなと思いました。ありがとうございました。
「優しい体育会系」という採用基準

松田 この前、採用のことで、COOの曽根(秀晶さん)というメンバーが提示してくれたのですが、ヘラルボニーのメンバーにフィットする「優しい体育会系」という言葉を作ったのですよ。
優しくて、マインドは体育会系で、青い炎が強く燃えていて、本当に反骨心のある人たちが、ヘラルボニーでは活躍しているなと思うので、そういう人たちの採用基準で、質問票などを作って、そこに対してちゃんとフィットする人たちを採用していこうと思っています。
意外とこういう定義を作ることが大事なのではないかと思っていて、このフィルターがあるから採用だという基準と、私たちの場合は双子が2人とも納得しないと採用しないと決めて、それを続けているので、2人の意見が一致しない時は、議論する時があります。
ただ、そういう会社独自の基準があることが多分独自性になって、結果として非連続な成長を生んでいけるような価値観を作れる会社になり得るのではないかと思いました。
ありがとうございました。
山崎 ありがとうございました。
最後に江口さん、まとめをお願いします。
印象深いのは3人の覚悟の決め方
江口 3人ともすごく頑固だなということに改めて気づいて、何に頑固かと言うと、自分たちの会社において一番大切にしたいことを大切にし続けるという頑固さが強いなと思いました。
ぶれないところや、そういったところの覚悟の決め方が、すごく印象残って学びがありました。
ありがとうございます。

みんなで悩みながら、みんなで発展していこう
山崎 皆さん、ありがとうございました。
僕も最後に一言だけ言うと、やはり稼ぐということなのですよ。
本気で解決するということは、稼ぐということなのです。
稼ぎ方を真剣に考えているということですよね。
マザーハウスも利益水準が厳しいのは、稼ぐことに対する限界突破を生むからです。
稼がないと社会課題解決はできないので、その仕組みを皆さん、やはり考えているんだなとすごく思いました。
会場にも、多分同じような悩みを色々抱えて、聴いてくださった方がたくさんいらっしゃると思うのですよ。
一番大事なのは、最後田口さんも言ってくれていましたが、みんなで悩みながらみんなで発展していくことです。
そういうことも願って、立ち上がっていただいて、みんなで拍手で終えたいと思います。
皆さん、頑張っていきましょう。
ともにこの社会課題を解決していかなければいけないと思う仲間なので、皆さんつながっていきましょう。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。

(終)
▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!
▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!
編集チーム:小林 雅/小林 弘美/浅郷 浩子/戸田 秀成


