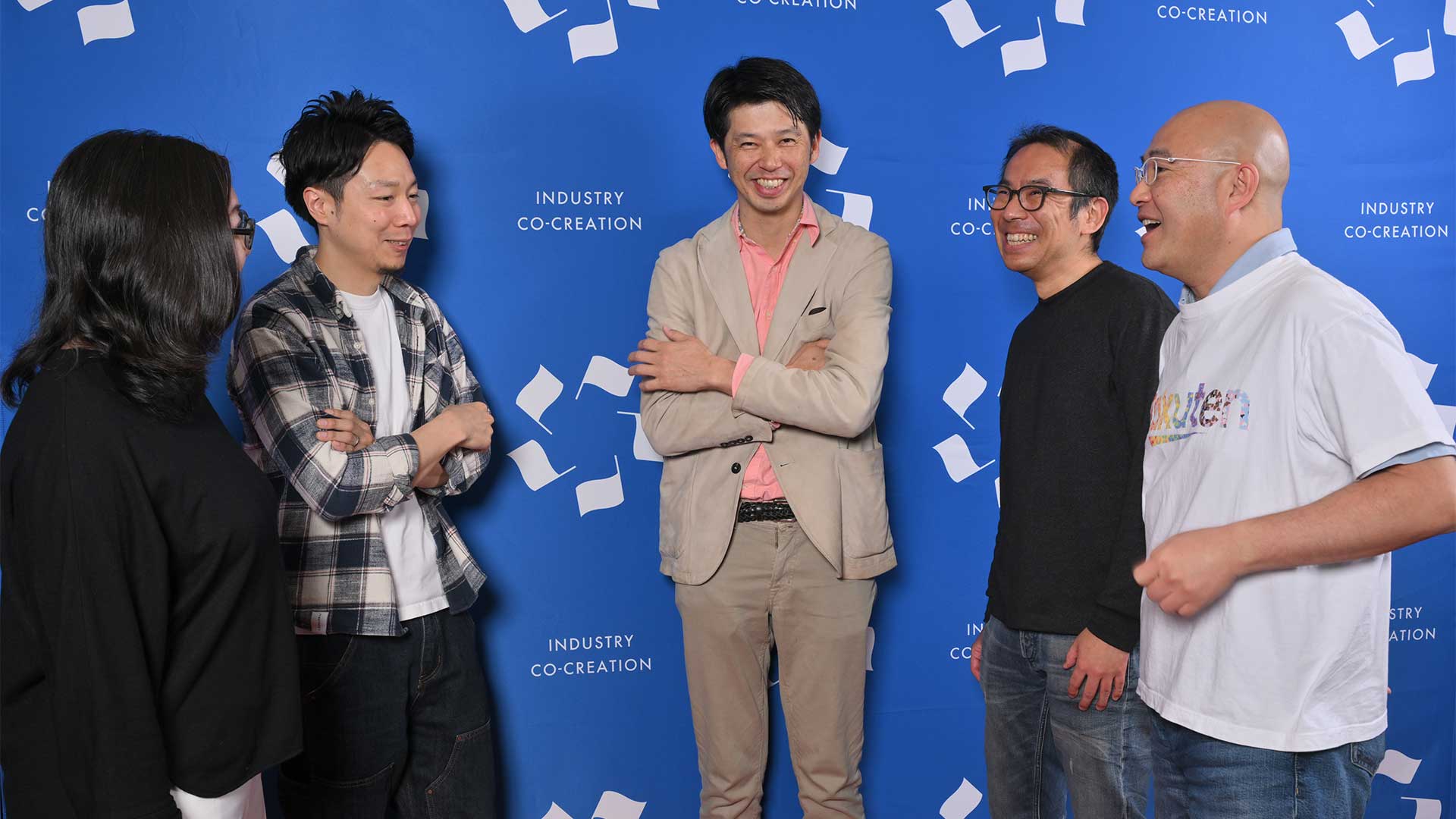▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!
▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!
ICC FUKUOKA 2025のセッション「-徹底議論 – 働き方はどう変わっていくのか?」、全4回の最終回は、メルカリ宮川 愛さんが、多様性ある組織において重要なのは言語化だと語ります。HRテックとAI活用によってホワイトカラークライシスは起こるのか?テクノロジーが発達する時代に必要な組織のあり方とは?「働き方」の前に立ち止まって考えるべきこととは?熱い議論を、最後までぜひご覧ください!
ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。
本セッションのオフィシャルサポーターは EVeM です。
▼
【登壇者情報】
2025年2月17〜20日開催
ICC FUKUOKA 2025
Session 10C
-徹底議論 – 働き方はどう変わっていくのか?
Supported by EVeM
(スピーカー)
小林 正忠
楽天グループ
常務執行役員 Group CCuO (Chief Culture Officer)
芹澤 雅人
SmartHR
代表取締役CEO
服部 穂住
relate
執行役員
宮川 愛
メルカリ
執行役員CHRO
(モデレーター)
権田 和士
リブ・コンサルティング
常務取締役COO
▲
▶「-徹底議論 – 働き方はどう変わっていくのか?」の配信済み記事一覧
多様性ある組織で重要な言語化

権田 日本のスタートアップもグローバルを目指す動きがありますが、宮川さん、メルカリは今、グローバル社員はどれくらいいるのでしょうか。
宮川 外国籍を持つ社員、という意味でしたら3割以上です。
権田 日本の組織とグローバルの組織において変わらないものもあると思いますが、調整しているようなことはあるのでしょうか。
宮川 メルカリにおいて、「グローバル組織が多いから、何かを調整するか」という意味ですか?
権田 はい、日本の組織とグローバルの組織で、変わるものがあるのかと。
宮川 日本の組織は、ベースにあるのが同質性です。
みんな同じような見た目で、アジア人で、黒い髪で。
そうなると、ハイコンテクストと言って、コミュニケーションにおいて、言葉の中に前提が含まれていることが多いのです。
メルカリでは外国籍を持つ社員もいるので、それらをあえて、全て言語化するようにしています。
バリューの1つの言葉を聞いた時、日本人であれば「こういうことかな」と想像、解釈できることがあったとします。
でも年齢も含めて多様性があるので、その言葉が会社として具体的に何を意味するのかについて、カルチャードックといって、結構長い文章にして公開しています。
権田 多様性のためには、曖昧にしないということですね。
宮川 そうです。言語化するということです。
ホワイトカラークライシスは起こるのか
権田 残り10分間となりました。
最後に、AIやHRテックに少し触れた上で、総括に向かいたいと思います。
HRテックで言うと、ぜひ芹澤さんに、今どういう状況になっているのか、それによって何が変わるのか、AIにつながるものがあればそれも含めて、お聞きしたいと思います。
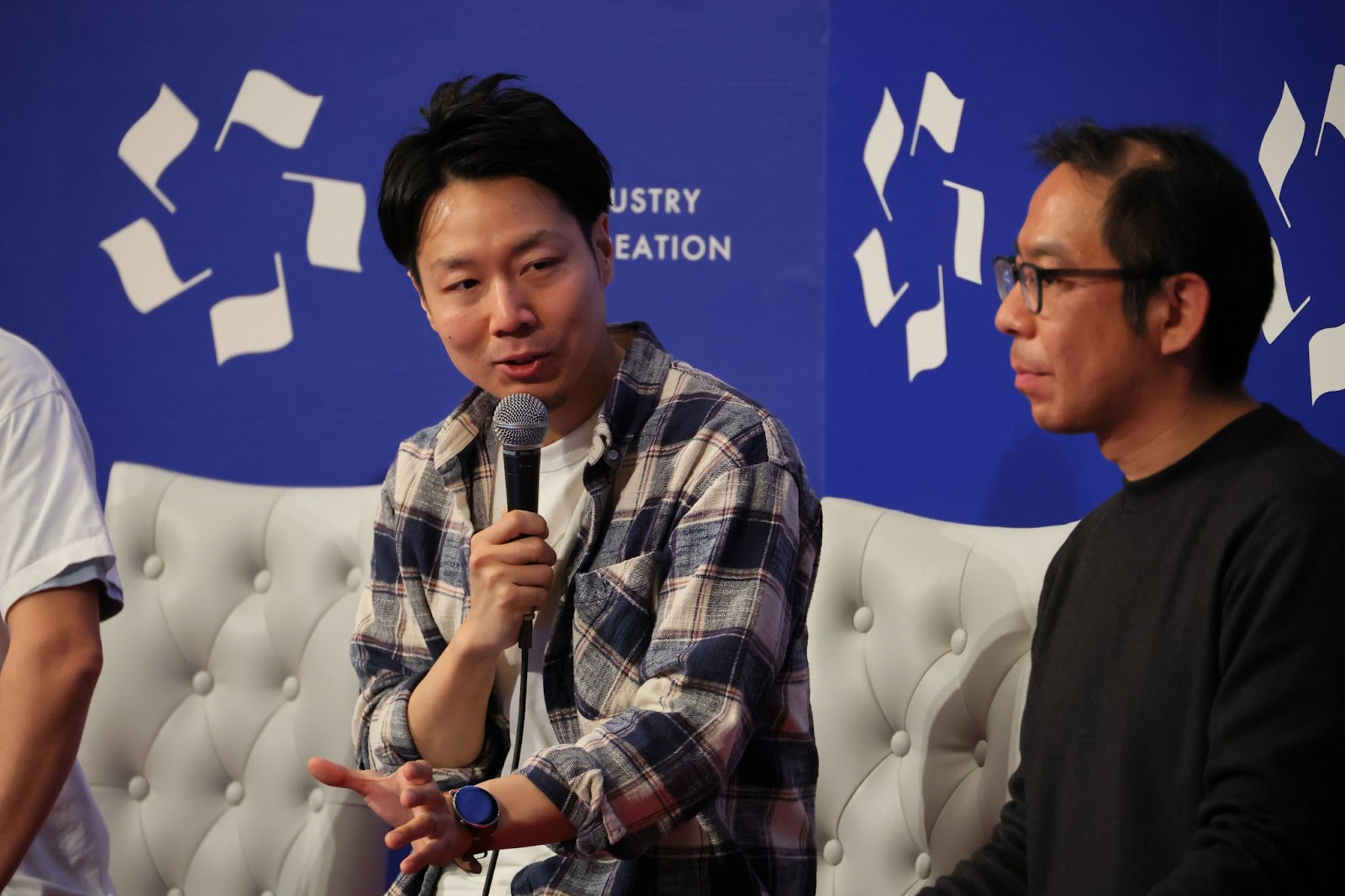
芹澤 外国に比べると日本は遅れていますが、この10年ほどは日本でも、特に効率化の文脈ではHRテック領域は伸びています。
効率化の先にあるのは、データドリブンなHRや科学的なマネジメントで、それが広がることを後押しするのがAIかなと思います。
データとAIはすごく相性が良いので、HRテックで効率化されて溜まったデータがAIによって分析され、AIによるレコメンドができるようになる、というのはあと1~3年で起こると思います。
そうなると、その技術を使いこなせるかどうかで格差が広がるのではないかともよく言われます。
最低限、効率化を実現しつつ、その先にある、AIを活用したデータドリブンで科学的なマネジメント、組織作りを見据えるのがポイントかと思います。
権田 効率化がされると、いわゆるホワイトカラークライシスが起こるのか、それとも共存する未来があるのか、どちらなのでしょう。
芹澤 個人的には、歴史を見ても、技術が発達するほど、より高度な知的労働が残ると思っています。
ホワイトカラーがなくなることはないだろうと思います、ただ、より高度な知的労働が求められるようになるので、僕たちが、そのレベルをもっと上げていかなければいけないという感覚を持っています。
権田 宮川さんは、いかがですか?

宮川 もっとEQを高めていかないと、EQの低い人にはクライシスが起こると思います。
ほとんどのことがAIでできるようになるので、冒頭、関係性やコミュニケーションに言及がありましたが、それができない人材は、今どんなに優秀とされていても、多分5年後、10年後要らなくなってくるだろうと。
ですから企業として、コミュニケーション能力が非常に大事だととらえ、それを高められる経験を社員に与えられるかどうかが、今いる社員が将来的に価値ある人材として残れるかどうかの大きなキーワードとなるのではないでしょうか。
権田 なるほど、つながりや関係性の質を高めていくことが、より組織の競争力になっていくのではないかということですね。
セイチュウ それは、鍛えられるものなのでしょうか?
権田 EQですか?
セイチュウ 大まかに言うと、今、ホワイトカラーがしている仕事の9割以上はなくなると思います。
でも今、現実問題として、人を雇用してしまっています。
1,000人いたら900人を解雇するのか?」という話になると思うのですが、どうするのでしょう。
宮川 EQは性格ではなくてスキルですから、高められるものです。
今EQがものすごく低い人は、頑張ってもそれなりのレベルにしかならないかもしれませんが、スキルを高める努力を会社がすれば、高められると思っています。
AIをフル活用し挑む楽天グループ
権田 セイチュウさんの捉え方は、新しいマッチングが始まるということでしょうか。
組織としての雇用というよりも、もう少し広い範囲で人と組織の最適なマッチングが進んでいく感じかと思います。
AI時代の働き方や今後の共存の仕方について、楽天はどう考えているのでしょうか?

セイチュウ 全員が(AIを)毎日フル活用していこうというモードに入っているので、いろいろなものを開発し、今は、仕事をどんどん作っています。
権田 フルに有効活用した上で、自分たちの仕事をなくさないように、戦っているわけですね。
セイチュウ 仕事をなくさないようにというよりも、新しいことができるように、ですね。
常に進化し続けるために、今まで時間やお金をかけていたことを最小限にし、その時間を他に充てるということです。
権田 目的は何か、ということかと思います。
雇用を守ること、優しくすることは目的ではなく、より高みを目指すにあたり、個と組織のマッチングをする。
その軸がぶれると、不都合な真実が生まれていって、スライドの左上に書かれている会社のような状況になってしまうので、気をつけましょうということなのだと理解しました。
今後必要な組織のあり方とは
権田 白熱した議論でしたが、残り5分間となったので、最後の一言として、一番伝えたいメッセージを宮川さんからお願いします。
宮川 組織はフェーズや時代によって、必要なスキルはどんどん変わりますが、やはり、組織が向かいたいのはどこなのか、そのためにどんな戦略を支えるための施策や働き方を提供するのかを、経営陣は明確化していく必要があるのではないかと思います。
権田 どこに向かうかを確認し合う作業がとても重要ということですね。
ありがとうございます。
服部 テクノロジーが発達すると、働き方と、人と人の関係性が、より切り離せなくなる時代になるのではないかと思います。
AIでいいやと思われたら、上司の価値が失われます。
でも、人と人が関わること自体は、変わらないと思うので、関係性が強い会社、スーパーチーム、いかに強い組織を作れるかという点が、ますます重要になると思います。
今日この後、Co-Creation Nightに出てFFS理論について話すのですが、席がまだ空いているようなので、ご興味のある方はぜひお越しください。

逆算から働き方を選択してみて
芹澤 いろいろお話ししましたが、「働き方の選択、経営意思決定は本当にそんなに難しいことですか?」と最後に言いたいです。
議論の中にもありましたが、働き方は目的ではなく手段です。
目的は会社をより成長させる、売上を伸ばし利益を上げることであり、そこから逆算をすれば自然と選択されると思うので、そんなに難しくないですし、周りを見なくてもいいのではないかと思います。
それに関連して、僕が感銘を受けた、オムロン創業者の立石 一真さんの言葉があります。
その内容は、「売上と利益を上げることなくして会社は存続できないので、売上と利益を上げることは人間にとって呼吸をすることと同じで非常に重要だが、息をすることは手段でしかなく、息をするために生きている人間はいない」というものです。
▶︎オムロン管理職が「会社で実現したいこと」を見失わない訳 人生100年時代で考える働く喜びとは(日本実業出版社)
会社にとって、より良い目的は社会に貢献することなので、社会にどう影響を与えて、より良い社会をどう作っていくか、から逆算をして、どう組織成長すべきか、から逆算をして、どういう働き方がいいかを考える。
そう考えると、働き方というのは、すごく小さなことだと思えてくるのです。
それくらいの心持ちで考えていただけると良いのではないでしょうか。

権田 目的を考え、向かうところを定めましょう、ということですね。
ありがとうございます。
「働き方」の前に「生き方」を考えて
セイチュウ 本当にその通りだと思います。
今日のテーマが働き方ですが、人は働き方よりも、もっともっと生き方をきちんと考えた方がいいと思っています。
働かなくてはいけないはずはなく、違う人生もあるので、一人ひとりが「どう生きたいか」をもっと定義できたならば、芹澤さんが今おっしゃったようなことを会社が発信してくれていると、「この会社は私の生き方に合う」と選びやすくなるはずです。
人が生き方を考えたとき、選ばれるような会社である、というのが、我々の考える働き方なのだろうと思います。
権田 なるほど。
なぜ働くかの前に、なぜ生きるかがあれば、本来は正しいマッチングが起こり、幸せにもなるし、組織の目的に向かっていくはずだということですね。
皆さん、働き方やどんな組織を作るかについて、いろいろと考えていると思います。
今日セッションで聞かれた通り、どんな会社になりたいかという目的がとても重要ですので、いろいろなバズワードには惑わされず、どこを目指し、どんな組織になりたいかを考え、話し合っていただくきっかけにしていただければと思います。
とても素晴らしい4名にお話しいただいたので、改めて、スピーカーに拍手を頂ければと思います。
ありがとうございました。
(終)
▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!
▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!
編集チーム:小林 雅/小林 弘美/浅郷 浩子/戸田 秀成