▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!
▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!
ICC KYOTO 2024のセッション「デジタル民主主義を徹底議論!」全7回の②は、引き続き「民主主義とは何か」がテーマ。東の食の会 高橋 大就さんは「民が課題解決に参加すること」、東京都知事選挙に出馬した安野 貴博さんは「権限を広く分散して持つ状態」、村上 臣さんは「意思決定に関わりながらより良い社会をつくっていくプロセス」だと回答。デジタル化が進むと情報吸い上げの量が増えて、人々の意思が社会に反映される可能性が高まるという意見も。皆さんはどう考えますか? ぜひご覧ください!
ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2025は、2025年9月1日〜 9月4日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページのアップデートをお待ちください。
本セッションのオフィシャルサポーターはYappli UNITEです。
▼
【登壇者情報】
2024年9月2〜5日開催
ICC KYOTO 2024
Session 5B
デジタル民主主義を徹底議論! ともに政治の仕組みを考えよう。
Supported by Yappli UNITE
(スピーカー)
安野 貴博
合同会社機械経営
代表
安部 敏樹
株式会社Ridilover 代表取締役 / 一般社団法人リディラバ 代表理事
高橋 大就
一般社団法人東の食の会 専務理事/ NoMAラボ 代表
永田 暁彦
UntroD Capital Japan株式会社代表取締役/リアルテックファンド代表
村上 臣
(モデレーター)
琴坂 将広
慶應義塾大学
准教授(SFC・総合政策)
▲
▶「デジタル民主主義を徹底議論! ともに政治の仕組みを考えよう。」の配信済み記事一覧
琴坂 次に、高橋さん、いってみましょう。
民主主義とは民(たみ)が課題解決に参加すること(高橋さん)
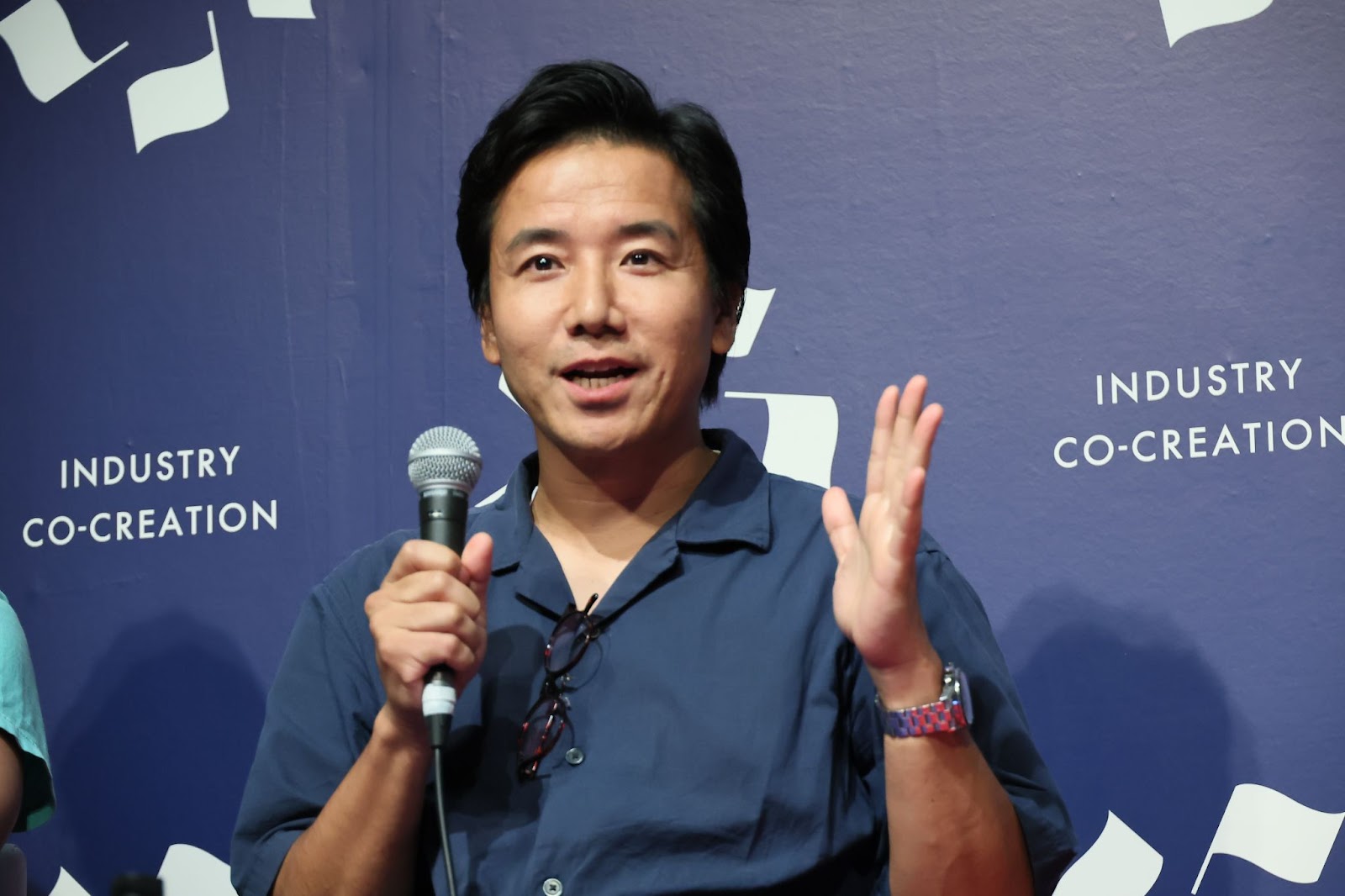
高橋 大就さん(以下、高橋) 今回のメッセージは極めてシンプルで、とにかくみんな民主主義を諦めないでいこうということしかないと思っています。
▼
高橋 大就
一般社団法人東の食の会 専務理事/ NoMAラボ 代表
1999年に外務省入省。日米安全保障問題や日米通商問題を担当した後、2008年にMcKinsey & Companyに転職。 2011年6月、一般社団法人東の食の会を立ち上げ事務局代表に就任。その後、並行してオイシックス株式会社執行役員(海外担当)に就任。東の食の会では「サヴァ缶」などのヒット商品や多くのヒーロー農家・漁師を生み出すと同時に、オイシックスにて日本の食の輸出事業を展開。 2021年4月、全町避難からの復興を進める福島県浪江町に移住。 現在、東の食の会にて福島の食のブランドづくりや「なみえ星降る農園」の運営を行うと同時に、NoMAラボにて住民主体のまちづくりに取り組み、更に、人と馬と自然とが共生する自律分散型コミュニティ「驫(ノーマ)の谷」を立ち上げた。
▲
その時に、民主主義というものを代議制、間接民主主義ととらえないことがすごく大事だと思っています。
そうとらえてしまうと、結構絶望するのも分かります。
先ほどもSlidoで、「民主主義は今後も成立するのか」という質問がありましたが、多分意識しているのは選挙で、「政治家の質」というのもありましたが、民主主義になると選挙や政治家の話になってしまいます。
しかし、それは本当に民主主義のごく一部で、選ぶのではなく我々自体が民主主義なのです。
我々が選挙で投票すること以外で何をするかのほうがよっぽど大事だし、よっぽど可能性があるし、その公共の領域をどれだけ広げていけるかというところにすべてがかかっていると思います。
その意味で、安野さんがやったことはすごく革命的だと思っています。
安野さんの得票数を見て、もう絶望だ、あれだけ革新的なことをしても無駄なんだと思ってしまったら絶対に間違っていると思っていて、あれを我々の日常にどれだけ実装していけるかが非常に重要だと思います。
▶︎東京都知事選挙2024(NHK)
琴坂 なるほど。今における民主主義とは、民が公を選ぶ状態なのですか?
高橋 多分ほとんどの人は、「民主主義」と言われた瞬間、投票のことを考えていると思うのですよね。
でも私が民主主義で好きな定義は、民(たみ)が課題解決に参加することで、投票の話とは全く異なります。
投票はごく一部だと思っています。
琴坂 その根源的な定義が、一番重要だということですね。
高橋 むしろ代議員の役割をどれだけ減らしていけるかが、これから重要だと思います。
琴坂 ありがとうございます。
権限を広く分散して持つ状態が民主主義(安野さん)
琴坂 安野さん、お願いします。

安野 私は、神や王様、貴族が権限を持っているのではなく、人々が広く薄く持っている状況が民主主義なのかなと思っています。
▼
安野 貴博
合同会社機械経営 代表
AIエンジニア、起業家、SF作家。東京大学、松尾豊研究室出身。 ボストン・コンサルティング・グループを経て、AIスタートアップ企業を二社創業。 デジタルを通じた社会システム変革に携わる。日本SF作家クラブ会員。 2024年東京都知事選に出馬、AIを活用した双方向型の選挙を実践。
▲
あとは所有の部分も、ある意味、分散して所有している状態なのかなと思っています。
ただ、この「みんなが権限を持っている」というのは、ふわっとした概念としては分かりやすいものの、それを具体的に実装するにあたっては、結局どういうふうに実現するのかというアーキテクチャが重要になってきます。
現状、いろいろな国が広く使っているのは間接民主制で、投票という枠組みを通じて情報を吸い上げて決めているということだと思っています。
集団的にどう意思決定をするのか、そのやり方については、ある意味で情報の流れ方の問題ではあるので、形については結構いろいろな可能性がありうるはずだと思います。
ただ一方で、永田さんが会社とのアナロジーについておっしゃっていましたが(前Part参照)、国や自治体が株式会社と違うのは、移住の可能性というのもそうだと思いますが、自然淘汰のメカニズムが、特に20世紀以降あまり国に対しては働いていないというところがあると思います。
意思決定のやり方によって、うまくいかなかった場合でも、(国や自治体は)会社のように自然淘汰されてなくなるという圧力がそれほどないので、そんなにいろいろなものが試されてもいない、という点があるなと思っています。

琴坂 確かにおっしゃるとおりですね。
会社はうまくいっていないガバナンスだったり仕組みだったら消えていくし、新しいものが生まれてきます。民主主義というものが再評価されたのがアメリカ独立やフランス革命の頃とすると、250年前ぐらいでしょうか。その時の基本理念がそのまま流れてきてしまっている状況だと思います。
特に、実装方法の進化が全然進まないような形になっている状況だということですね。
……では、それを受けて。
村上 臣さん(以下、村上) 受けるんだ(笑)。
(会場笑)
琴坂 受けてください。
村上 すごいハードルが上がっていますね。
琴坂 高いですよ(笑)。
意思決定に関わりながらより良い社会をつくっていくプロセスが民主主義(村上さん)

村上 僕は安野さんの意見に似ているのですが、やはり誰かに丸投げするのではなく、主体的、能動的に意思決定に関与しながらより良い自分たちの社会をつくっていくというもの、その総合的なプロセスが民主主義なのかなと自分としては思っています。
▼
村上 臣
青山学院大学理工学部物理学科卒業。大学在学中に仲間とともに有限会社「電脳隊」を設立。 2000年8月、ピー・アイ・エムとヤフーの合併に伴いヤフー入社。 2011年に一度退職した後、再び2012年4月からヤフーの執行役員兼CMOとして、モバイル事業の企画戦略を担当。 2017年11月に8億人超が利用するビジネス特化型ネットワークのLinkedIn(リンクトイン)日本代表に就任。日本語版のプロダクト改善、利用者の増加や認知度向上に貢献し、2022年4月退任。 ポピンズ 及びランサーズの社外取締役ほか複数のスタートアップの戦略・技術顧問も務める。 主な著書に『転職2.0』(SBクリエイティブ)・『Notionで実現する新クリエイティブ仕事術』(インプレス)がある。
▲
もちろん選挙は、代議士、特に間接民主主義においては大事ですけれども、日本の場合は行き過ぎたというか丸投げになっているなと思います。
あとは、会場の皆さんの中で、議員に会ったことや話したことがある方はいらっしゃいますか?
(会場を見渡して)あっ、さすがこのセッションにはいらっしゃいますね。
「代議士」とは、代わりにやる人ですよね。
ですから、一般の人でもいつでも会いに行けるし、いつでも陳情も普通にできるのですよね。
ただそうしている人は、これだけ意識の高い人たちが集まっていても少ないわけなので、1回選んだらよしなにやってくれるだろうという状態です。
ガバナンスとして、そこをチェックするような仕組みも透明性もありません。
デジタルは、情報の透明性であるとか、トラックレコードをしっかりと証明することは得意ですので、そこはデジタルで解決できる余地があって、この辺りからアップデートする必要があるのかなと思っています。
琴坂 ありがとうございます。
おそらくスピーカーの皆さんに共通しているのは、我々が主役であるということですよね。
これは社会の根源的なもので、安部さんの言葉を借りると、中枢神経系の重要なものであるということです。
そして、概念自体は素晴らしいのだけれども、その実装方法が全く進化していなくて、それによって我々はもしかしたら幻滅しているかもしれないし、希望を失っている状態なのかもしれません。
そんなところなのではないかと思います。
トップダウンになるほどアウトカムが脆弱になる

安部 よろしいですか。
中枢神経系の話は、基本的に神経のセンサリングの精度がどれくらい高いかに依存していて、その意味で民主主義は人間の数だけセンサが存在していて、本来的な専制政治みたいなものよりは強いといえます。
デジタルになっていくと、本人の中の分人的な要素まで含めて、あるいはこのイシューにはこういう意思決定をしたいけれど、このイシューにはこういうふうに言いたいというところまで依拠できるので、より滑らかになっていくという意味でいうと、神経系としては今後どんどん発達していくのだと思います。
3〜4日前まで、僕は香港に行っていました。
人工生命のような話をしてしまったので、少し現実的な民主主義に近い話に戻ってくると、香港はまさに民主主義が奪われた地です。
奪われている中でどういうことが議論されているかというと、直近に『High Wire: How China Regulates Big Tech and Governs Its Economy』という本が出版されています。
「High Wire」とはサーカスで高い所に張られたロープですが、これはいかに中国の意思決定がプロセスが危ういバランスの中で行われているのか、というのを表現した言葉です。中国人女性の(Angela Zhang)教授が執筆して、アメリカで出版されました。
内容はすごくシンプルで、政治と意思決定の話においては、まず意思決定のストラクチャー(構造)があり、その次にプロセスがあって、アウトカム(結果)が出てくるという話があります。
例えば、中国がゼロコロナ政策をとった時に、皆さん絶対に自宅の中にいなさいという世界観でした。
ある意味アウトカムとしては非常にしっかり結果が出たじゃないかという言い方もできるけれども、出ている議論としてはストラクチャーがトップダウンになればなるほど、基本的にはプロセスみたいなもののボラティリティ(変動性)がすごく上がって高まっていくというものです。
なぜかというと、たった一人の気分で変わってしまうので、周りの人もそれを見ながら大丈夫かな、どうなるのかなみたいな感じになっていくので、その分だけボラティリティが高いプロセスになっていきます。
その結果、長期的に見るとアウトカムが非常に脆弱になるというのが、むしろ中国に関係している人たちから出てきている議論として存在しているのです。
そういう意味でいうと、大きな話でいえば、より大きなセンサリング能力を持ち、ボトムアップで生命的に創発していくという、長期で見ると民主主義のほうが優勢になる可能性が高いのではないかと思っています。
一方で、それをうまくやり切れるかどうかは、デジタル化できるかどうかみたいなことによって、人類の歴史の大きな分岐点になるのかなと思っています。というのも、ボトムアップでの情報の吸い上げの量という意味ではデジタル社会の民主主義と、それまでの民主主義は違うからです。
普通の民主主義だと、結構中国のほうがうまくいくことのほうが多くあったじゃないですか、ここ最近を見ると。
ここから15年くらいは多分あまり中国のパフォーマンスは良くないと思うので、再び民主主義はやっぱり大事だねみたいな話になっていくのだと思います。
その次に若い習近平みたいな人がまた出てきたりすると、やっぱり専制主義のほうがいいねみたいな話になる可能性がありますが、民主主義とその他の政治勢力の競争においては、まだどちらが良いか確実に決め切れていないタイミングにあります。
これがデジタル的なところまでやり切って、より精緻に、より確実に人々の意思が社会全体に反映されていくようなところまでいくのであれば、人類は民主主義を完全に取り込んで、より発展していく方向にいくのではないかというのが、私が持っている仮説です。
自由選挙だけが民主主義ということではない

高橋 今の香港の話ですが、歴史的にも逆戻りするってなかなかないですよね。
いったん与えられていた自由選挙、言論の自由が奪われるのは、私も香港で事業をやっていたので本当につらいのですが、ただ日本人として考えなくてはいけないのは、では我々は民主主義をやっているのかということです。
▶(社説)民主派に実刑 香港自治 否定する暴挙(朝日新聞デジタル)
あれを対岸の火事とするのではなく、ちゃんと考えなければいけないと思っています。
村上さんが言っていた、誰かに丸投げするのではなくというのを、民主主義の歴史でいうと、ジャン=ジャック・ルソー(1712~1778)が『社会契約論』(1762)でまさにこれを言っていて、イギリスが自由選挙をしていた時にイギリス人は選挙をする時だけ自由で、彼らはその後奴隷に戻っていると言っているのですよね。
すなわち民主主義の父の一人でもあるルソーが、選挙の時だけ投票して、自由選挙があれば民主主義ということではない、その後丸投げをしているのは奴隷なんだと言っていることは、まさに我々の今の日本の状況だと思うのです。
ですから、香港の状況を見ているだけではなくて、我々は本当に本来担保されているはずの民主主義をちゃんとやっているのか、考えなければいけないのだろうなと思うのですよね。
民主主義と資本主義はこのまま続いていくのか
安部 よろしいですか?
どんどん違う方向にいってしまっていて…、会場の方は期待したほうではないと感じる可能性が高いのですが。
(会場笑)
まさに今あった話の中でいうと、民主主義と何をセットにするかは大事で、基本的には民主主義と資本主義がセットです。
専制主義と共産主義は割と相性が良くて、セットになることが多かったのです。
全く別角度から民主主義の未来を議論するのであれば、本当に資本主義はこのままずっと続いていくのかという論点とも結構かぶってくる話だと思います。
資本主義がどういうふうになっていくのか、いろいろ論点はありますが、その分岐点は、いわゆる「ユニバーサル・ベーシック・インカム(UBI)」です。
▶︎ベーシックインカムとは?メリット・デメリット、実現の可能性を解説(朝日新聞SDGs ACTION!)
それが、べーシックではなくてちょっと良いインカムみたいなレベルまで来ると、本当に働く意味がなくなってくるのですよね。
ですから、ユニバーサル・ハイヤー・インカムになったとしたら、みんな働かずにもっと別の形で社会参画したいみたいになってきます。
琴坂 古代ギリシャ、アテネの民主制ですよね。
安部 そうそう、奴隷がいたからという話ですけれど。
そうすると、経済的な考え方も少し変わった仕組みになってくる可能性があります。
その時の民主主義のあり方はどうなるのかというのは、今の時点の資本主義とのマッチングで民主主義がうまく機能しているところも多少あるのですが、100~200年のスパンで見ると、先々に再び共産主義的な世界が盛り返してくるかもしれません。
この観点から見た時の政治体制は民主主義がベストなのかどうかみたいなことは、また別の議論として出てきそうな気がしていますけれどもね。
安野 ユニバーサル・ハイヤー・インカムが発達した時に、共産主義っぽくなるというのは、どういう経路があるとお考えですか?
安部 資本主義と相性の良いものとして民主主義という話があって、専制主義というのが共産主義、ないしはその他のいくつかの経済システムと相性がいいですという時に、資本主義ではなくなってきた時に果たして民主主義なのかという議論ですね。
僕は特に共産主義に戻るとまでは思っていないけれど、もっと言うと、本来カール・マルクス(1818〜1883)が言っていた共産主義の理想状態みたいな話って、結局歴史的には実現されていませんよね。
ですから、それが本当の意味で実現された時に、どんな政治体制なのかという議論かなと思っていますけれどね。
琴坂 1つだけ反応すると、現状における民主主義の制度、特に日本が持っている民主主義制度は1人1票ですが、そこに資本主義が絡んでくると、いわゆる株式会社のように1人100票とか、日本においても普通選挙法以前においては納税金額によって投票権がないということがあったと思います。
▶投票が18歳からできるように~選挙権について知る(日経4946)
そこと絡めたまた別の議論として、一人ひとりが平等であり続けるかどうかという議論も出てくるのかなと思いますし、興味深いのですが、もう1軸加えてしまうと散漫になってしまうので、今日の掛け算は「デジタル」だけにしたいと思います。
(続)
▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!
▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!
編集チーム:小林 雅/星野 由香里/浅郷 浩子/小林 弘美/戸田 秀成


