▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!
▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!
ICC FUKUOKA 2024のセッション「大人の教養シリーズ「美食」について語りつくす(シーズン8)」、全10回の⑥は、いよいよ後半戦。各自が持ち寄った美食に関するおもしろいテーマをディスカッション。平和酒造の山本さんは日本の魚の扱い方の技術の高さを、海外歴の長いシーベジタブルの石坂さんは現地の日本の料理人への評価を語ります。ぜひご覧ください!
ICCサミットは「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。そして参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。次回ICCサミット KYOTO 2024は、2024年9月2日〜9月5日 京都市での開催を予定しております。参加登録は公式ページをご覧ください。
本セッションのオフィシャルサポーターは エッグフォワード です。
▼
【登壇者情報】
2024年2月19〜22日開催
ICC FUKUOKA 2024
Session 9F
大人の教養シリーズ「美食」について語りつくす(シーズン8)
Supported by エッグフォワード
(スピーカー)
石坂 秀威
シーベジタブル
料理開発担当/シェフ
西井 敏恭
シンクロ
代表取締役
長谷川 誠
NTTドコモ
コンシューママーケティング推進担当部長/シニアプロフェッショナル
宮下 拓己
イラルギア合同会社(LURRA°)
代表社員
山本 典正
平和酒造
代表取締役社長
(モデレーター)
榊 淳
一休
代表取締役社長
▲
▶大人の教養シリーズ「美食」について語りつくす(シーズン8)
榊 では、山本さん、お願いします。
山本 はい、私は日本酒の輸出を行っていますので、海外のレストランに行かせていただく機会も多いですし、改めて日本の食の価値を、自分自身が日本酒を造っていることでも感じます。
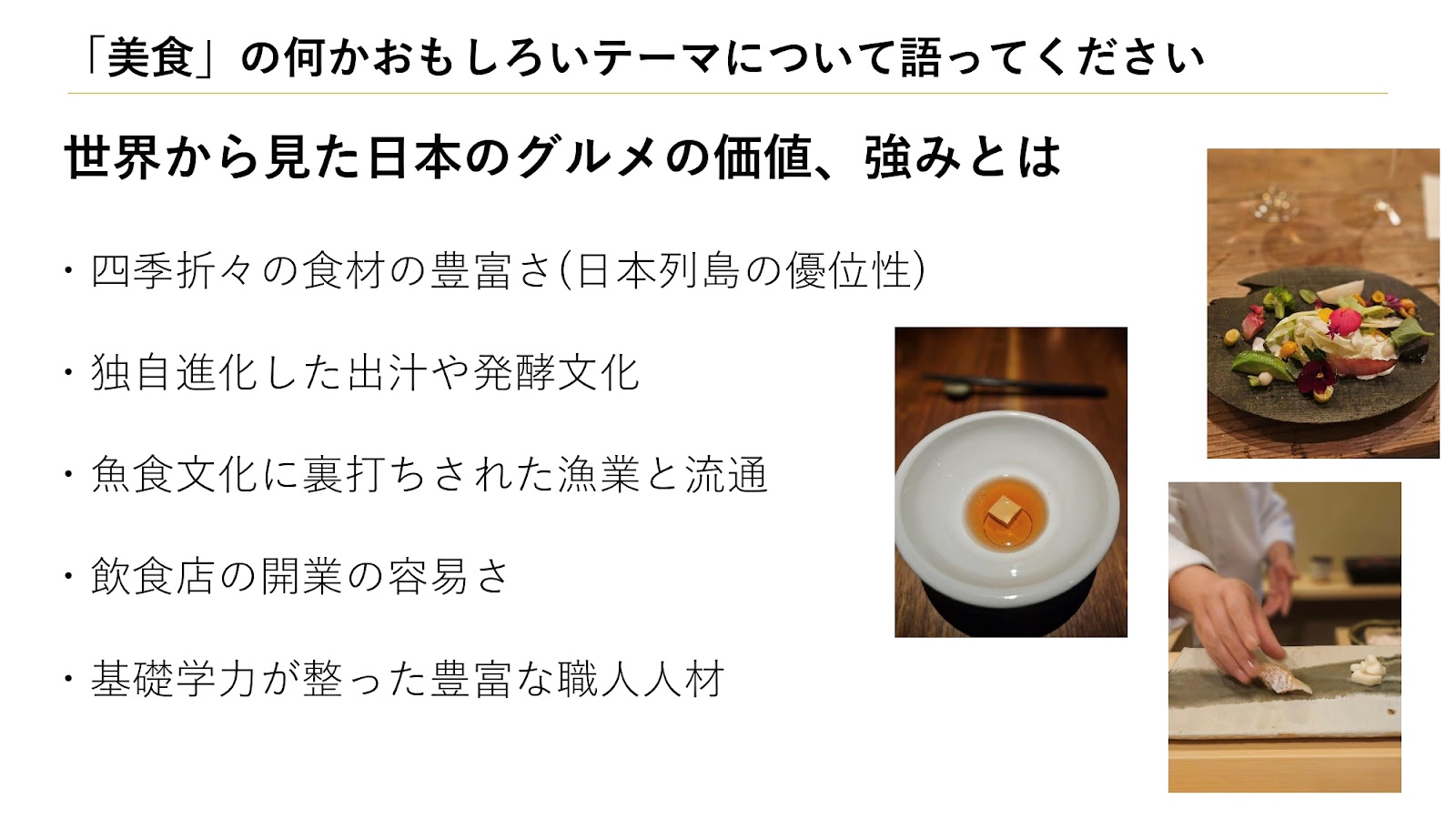
世界から見て、日本は食が非常に素晴らしいと言われているわけですが、それがどういうところなのか分析してみたいなと思いました。
私の仮説で書いているわけですが、ぜひ皆さんのご意見もお聞きしながら語り合いたいと思ったものをテーマに設定しました。
世界から見た日本のグルメの価値と強み
山本 まず日本は、なぜそんなに食文化が発展したのだろうかというと、一つは日本列島に非常に特異性があります。
先ほど海藻のお話(Part.2参照)でもありましたが、南北に広く、そして海洋国であることで非常に食材が豊富で、四季折々の変化が激しく、食材が豊富であることが一つではないかと思います。
2つ目が、独自進化した出汁、それから発酵文化です。
日本酒も「発酵」に入りますが、それだけではなくて味噌や醤油、そして鮨も発酵になるわけですが、そういうものは非常に独自性があって、世界中から来ていただく価値のあるものになっているのではないかと思います。
3つ目に、私は一昨年ニュージーランドに行きました。
世界中に行きますが、私の営業対象は和食店、日本料理のお店で、その理由は、日本酒を置いていただけるのがそういうお店だからです。
ひょっとしたら、僕は日本料理や和食をかなり食べているほうの部類に入っているのではないかと思います。
なぜかというと、日本人はわざわざ海外に行って日本料理や和食を食べないじゃないですか(笑)。
でも私はそういうお店が営業対象なので、レストランを回らせていただくのですね。
そうすると、圧倒的に日本で食べられている生魚のクオリティの高さを痛感します。

ただ、ニュージーランドに行った時に、非常に美味しい魚に出会いました。
ニュージーランドは南半球にあるため、日本とは季節が真逆になります。
昔からオーストラリアと同じように、南半球ということで、季節と逆のものを日本に輸出していました。
かぼちゃを日本に輸出している取引先の会社がインポートビジネスとして日本酒を仕入れるということだったのですが、ニュージーランドは非常に日本列島に近い形になっているのです。
そういうところで、すごく美味しい魚を食べさせていただきました。
なぜ、こういうものが出せるのか聞いたところ、漁師を指導しているそうです。
日本人の方なのですが、締め方、獲り方、氷を入れることがすごく大事なんだみたいな話をされて、なるほどねと思ったのですが、その時にはたと気づいたことがあります。
やはり今の日本の魚文化は、もちろん魚を食べるという文化があったわけですが、同時に流通、コールドチェーンが非常にきっちりできているのです。
例えば船で魚を獲った時に、その瞬間に氷に突っ込み、競りの時も氷に乗せながら競りをしていきます。
その後の流通のトラックも、全部完璧なコールドチェーンで、これは日本酒はまだできていないところです。
日本酒は海外輸出の場合は、ダメージを与えないように理想で言うと0℃以下で保存してもらいたいのですが、コールドチェーンが完璧な魚文化から、私たち日本酒の造り手は学ぶことができますし、日本はそういうことに恵まれているわけです。
日本は非常に競争が激しく、さらに今度は漁師さん、例えば愛媛の漁師さん、そして静岡の魚屋さんたちが獲り方まで指導しています。
神経締めや血抜きを教えたり、船上で処理するように指導して、よそよりさらに美味しい食材を生み出してきています。
▶️新潟越後神経締めについて(新潟県)
それが、レストランで食べる魚が非常に美味しい理由の一つではないかと思います。

4つ目に飲食店の開業の容易さを挙げているのですが、東京の飲食店はコロナ前の2019年に14万軒あり、美食の街と言われているパリが4万軒です。
パリやヨーロッパの国で多くあるのが、飲食店の開業に際しての非常に厳しいレギュレーションです。
パリであればこの場所でしか飲食店を開いてはダメですとか、ロンドンが特にそうですが、営業権の売買価値には非常に価値があって、基本的にはパトロンがいないとできません。
それが日本の場合は、例えば金融機関は国民公庫とかで20代の鮨職人が融資を受けて独立することができるという意味で、非常に日本の飲食店は開業しやすい分、逆に言うと非常に競争が激しいマーケットになっているので、より良いものがお客様に提供されているのではないかと思います。
最後は仮説的な部分ですけれども、世界的に見ても非常に優秀な人材が職人として入られているのではないかと思っていて、そのあたりが日本独自のグルメの発展に寄与したのかなと思っています。
私からは、こんな感じです。
榊 まだありますよね?
山本 そうですね、すみません。
榊 ぜひ!
日本の最高のコンテンツはグルメ
山本 世界から見た日本のグルメの価値ですが、私は海外から日本に戻ってくると本当にありがたいなと思うのです。
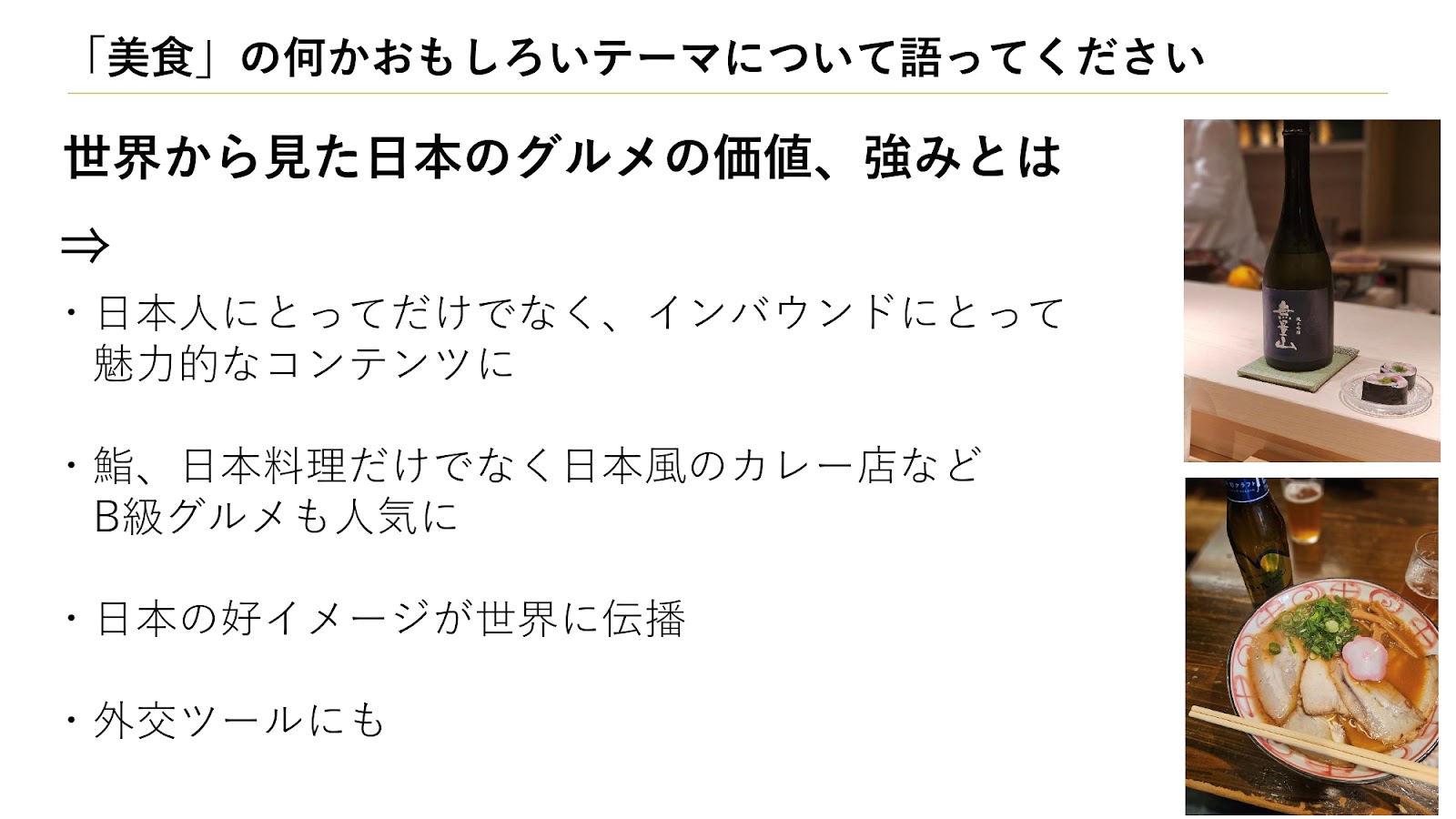
安いファストフードの、例えば吉野屋さんは非常に素晴らしい味を出していますし、ひょっとしたらマクドナルドやスターバックスも海外より、日本の店のほうが美味しかったりするのです。
それは多分、日本の教育であったり、競争が激しいために同じ値段で他の店の美味しいものが食べられるということがあるのではないかなと思います。
世界の人も、日本の食の魅力に気づき始めています。
最近ロサンゼルスに行きましたが、日本風のカレー屋さんが結構ウケていて、現地の若い方がナチュラルワインを飲みながら日本のカレーを喜んで食べているシーンを見て、非常におもしろいなと思いました。
そういう意味で考えると、日本の最高のコンテンツはグルメじゃないかなと思っています。
外交でも日本食が好きな海外トップは非常に日本に親近感を持ちやすい特性があって、政治的に対立している国、韓国や中国にも私は日本酒の営業に行かせていただくのですが、政治的な部分より、日本のカルチャー、特に食の部分に対しての愛情を彼らから感じる時が非常に多いです。
そういう意味では、食は世界の中で非常に武器になるものではないかと思っています。
私ばかり喋ってしまって、すみません。
榊 ありがとうございます。海外暮らしをしてきた宮下さん、石坂さん、どうですか?
宮下 今シドニーのマーケットで、日本人が活締めを教えたりしていますね。
石坂 結構話題になっていますね。
宮下 日本から魚の扱い方を教えるみたいなことは、本当に広がっているなと思います。
日本の料理人に対する期待・評価は高い

石坂 僕はちょっとスペシャルケースですが、日本から来た日本人がシドニーの店に勤めるとなると、現地のスタッフが、「おい、日本人入るぞ」という感じで、日本人の料理人の腕というものに対して、実際評価が高いのです。
でも、逆にちょっと厳しいところがあって、「お前日本人なのに、これができないのか」と言われることが多いのですよ。
だから、みんなの中にある日本人の料理人のイメージ、レベルがそれだけ高いのです。
宮下 でもSaint Peterかな?というお店があって、そこは魚のブッチャーみたいな、肉屋で部位ごとに売られているように、ショーケースに魚のパーツを置いていたり。
▶鬼才、ジョシュ・ニランド・シェフが手掛けるシーフード専門レストランSaint Peter(セント・ピーター)(NICHIGO PRESS)
石坂 そうそう。
宮下 それも本当に日本の食、魚の扱いみたいなところからインスピレーションが来ていたりします。
石坂 今までそういうニッチなところは、誰も狙ってこなかったのです。
でも、まさにオーストラリアでの美食もそういうレベルです。
日本の美味しい魚を知っている客が同じようなレベルのものを求めてくるので、現地の料理人も頑張らないとという意味で、自分が知っている知識だけではなく、日本の魚の扱い方はなぜこんな違うのかという好奇心があるからこそ、知識や技術が輸入されるというのはありますね。
榊 ありがとうございます。
(続)
本セッション記事一覧
- 美食道に励む6人が集結! Netflixの人気番組にも登場「LURRA°」宮下さん
- 海藻の美味しさを追求するシェフ、シーベジタブル石坂さん
- 西井さんに宣戦布告!? 国内外で美食を求める平和酒造の山本さん
- 旅と食を愛するシンクロ西井さん、食べログアワード訪問店数を告白
- 変態美食家ハセマコ、シーズン8では「構成」を深掘り
- 美食家山本さんが力説、世界から見た日本のグルメの価値と強み
- 料理人がただ料理をするだけではいけない時代になってきている
- ハセマコ、新規開拓店と食の「構成」のフレームワークを語る
- 食と飲料の「ペアリング」とは「寄り添う」「ぶつける」「受け渡す」(終)
- 【番外編】大人の教養シリーズ「美食」について語りつくす(シーズン8) 登場したお店リスト
▶カタパルトの結果速報、ICCサミットの最新情報は公式Xをぜひご覧ください!
▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから!
▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから!
編集チーム:小林 雅/浅郷 浩子/小林 弘美/戸田 秀成


